
お金が絡むと、どんなに仲の良い兄弟でも亀裂が入ることがあります。
実際、筆者も近所で評判の仲良し四人きょうだいでしたが、父の遺産相続ではきょうだい喧嘩が勃発。
葬儀中に険悪な雰囲気を生んだことがあります。
その時は、弟の改心で丸く収まったものの、もっと話がこじれていたら、今はもう弟とは音信不通になっていたかもしれません。
相続問題は本当に怖いと感じたものです。
このような筆者の過去を含めて、当時から専門家の先生に早めに頼んでおけば良かったことを記述していこうかと思います。
少し長くなりますが、筆者の身の上話にお付き合いいただければ幸いです。
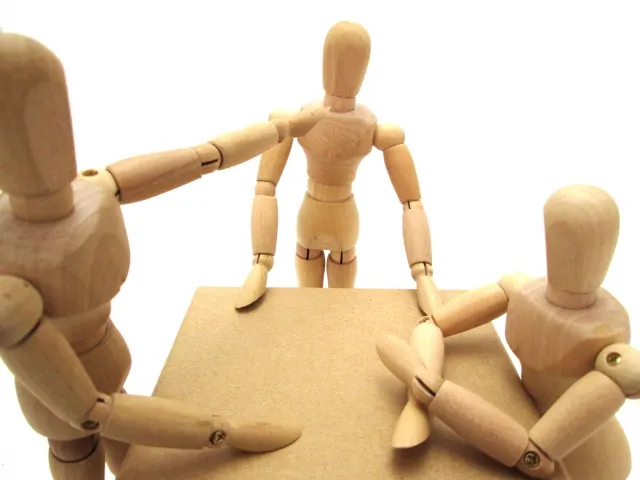
目次
トラブルメーカーの父が亡くなって ~相続問題が起きる原因
筆者(以下、私と記します)の父が亡くなったのは、3年前。
20年以上の闘病の末、60代で永眠しました。
10年ほどは寝たきりだったので、延命措置を数年行ったのち、息を引き取りました。
いつかは亡くなると頭ではわかっていましたが、急なことだったので、母も私たちきょうだいも慌てふためきました。
一番慌てていたのは、母でした。
私にはSNSでしか母から連絡は来ていなかったので、気丈な人だと思っていましたが、弟から
「お母さんがおかしいから早く帰ってきて」
とヘルプのメッセージがきたので、関西空港で頭を抱えました。
やはり母は、最愛の父を亡くして気が動転していました。
ここで母と父について、少し話していきたいと思います。
母と父は、漫画でよくあるコンセプトの
「ヤンキー彼氏と学級委員長彼女」
という感じの夫婦でした。
こんな夫婦が現実にいるのかと幼少期に思いましたが、基本的に合うはずのない二人がくっついたのは、まじめな母が、やんちゃで男前な父に一目ぼれしてしまったからです。
男前でなければ、おそらく母も結婚していなかったことでしょう。
そして、父ははっきり言って現代の「コンプライアンス」に引っかかる、やんちゃという言葉で補えないくらいの人だったので、母はずっと苦労してきました。
この人が亡くなったときは、きっと大変だろうなと、小さい頃から思うほどでした。
実際、母は
「知らない子がお葬式来たらどうしよう…」
とお葬式が終わるまで悩んでいたものです。

もう子どもではない私たち ~諍いが起きるまで
絵に描いたようなやんちゃな父が亡くなり、私は関西から家族を連れ、雪国の田舎へ帰省することになりました。
妹二人も家族も連れ、続々と実家へ到着。
私たち遠方組が帰るまでに、親せきと近所のつながりでお葬式の段取りが完成していました。
喪主をつとめるのは、4人きょうだいの末っ子長男、私の弟です。
当時、弟はまだ20代前半でしたが、結婚を控えていました。
私も当時は結婚していましたし、妹2人も既婚。
妹の1人は2児の母となっていました。
自慢ではないですが、私たち4人きょうだいは集落でも有名な仲良しきょうだいで、皆離れて暮らしているものの、SNSでは4人で繋がって他愛もない話をする仲です。
不謹慎ですが、父の葬儀でもない限り、4人が実家に全員集合することはなかったので、少しだけ嬉しく思いました。
葬儀の段取りで忙しい母と弟には申し訳なかったのですが、実家に4人でいられることが久しぶりで、少し楽しいとさえ思いました。
ただ、この仲の良さは、全員集合3時間ほどで壊れます。
父の遺産相続のせいで。

もめ事をつくる要因 ~相続問題をややこしくさせた環境
私の両親は一時期、流行語にもなった「格差婚」の先駆けとなるふたりでした。
母は今で言う「バリキャリ」で、産後2週間で仕事復帰し、4人の子どもを育てあげました。
芯のある賢い人でしたが、最愛の夫を亡くすと、動揺のためか軽くパニックを起こしていました。
弟曰く長女である私の言うことしか聞かないらしく、実家について早々、母とともに過ごす時間と台所にいる時間が増えました。
私の出身地は、葬儀は会場で行っても、お葬式の期間中は実家で親せきをもてなすので、ごはん支度をしなければいけません。
仕出しもとりますが、基本親せきと家の子どもがごはんを作ります。
弟の婚約者も台所のお手伝いしてくれましたが、私が帰ってきてすぐに、祖母から
「台所の手伝いを変われ」
と指示が出ました。
私の出身地あるあるなのですが、長女は実家に帰るとほぼ女中と化します。
驚くほど閉鎖的で、時間の流れが止まったような限界集落ではよくあることですが、男性は台所に立つことは未だにありません。
関西に出てきて出来た友人たちを私の田舎に連れてくると、決まって言う言葉が
「今、平成やんな?」
であるくらいの風土です。
どれくらい田舎かと言うと、江戸時代に作られた5人組の制度がまだ残っています。
冠婚葬祭はほぼ、この5人組の組織が関わってきます。
基本、なんでも「家」単位で考えている人が多い土地柄です。
家を継ぐというのは、家の面倒を見るという考えに近いのですが、現行民法にはない、明治に制定された民法の「家」制度の考えに近いと思います。
今でも男尊女卑の風潮が強く、長男が家を継ぐものと考えている人が多いのは事実です。
私自身、弟が生まれるまでは跡取り娘と育てられましたが、弟が生まれた瞬間
「嫁にいけ」
と言われたくらいです。
長男第一主義なので、4人きょうだいの末っ子長男は、王様と言っても過言ではありません。
そんな「王様」長男と「女中」長女がこれから相続について大喧嘩します。
大喧嘩の原因となったのは、そんな環境が起因していると、念頭にいれていただければと思います。

相続で起きた姉と弟のバトルロワイヤル
王様はいつでも気軽に暴言を吐いてきます。
それが久々のきょうだいの集まりだろうと、父との最期の別れの日だろうと関係ありません。
弟の爆弾発言 ~田舎の言い分と私の言い分
「遺産全部俺にくれん?」
爆弾発言は突然に。
4人きょうだいとその家族、弟の婚約者と昔話に花を咲かせ、そんな楽しい団らんの時間を壊すのは、マイペースな末っ子です。
弟の話を聞いて、妹たちは一瞬固まりましたが、私はちょっと待ってと、話を止めました。
これからだいぶ言い争いますので、私と弟の言い分をまとめて記載します。
弟の言い分
- ・うちの田舎は家を継いだ人間が親の遺産をすべて相続する。
だから遺産を全部ください。 - ・十年以上寝たきりの父親を田舎に残って面倒見たのは自分と母親。
遺産相続の権利は自分と母親にある。
私の言い分
- ・誰が面倒見ようと遺産は、母と子ども四人で分割するべき。
田舎の風習など関係ない。 - ・私は子どもがいないけれど、これから子どもの世話で大変になる妹たちに父親の遺産を渡さないのはおかしい。
- ・確かに寝たきりの父親の世話をしたのは、弟と母親ではあるけれど、2人だけで父親の面倒を見た気でいるのはおかしい。
父親の世話をするまでに、妹たちの支えがこれっぽっちもなかったとは言い切れない。
・そして、跡継ぎである弟をこれからも支えてくれるであろう妹たちに渡さないのは、おかしい。
せめて妹たちには分割して渡しなさい。
以上です。
先ほども記載しましたが、私の田舎では、まだ家文化が色濃く残っています。
先祖代々の土地を守り、家を大事にする。
長男が家を継ぐのが最も良いことだと考えられています。
よって、弟の言い分は田舎に残った人間としては正解なのでしょう。
しかしながら、私は都会へ出てきてしまったので、弟の言い分は理解できませんでした。
そもそも亡くなった父は、15歳から東京で働き、結婚のために田舎に帰ってきたので、田舎の考えに囚われる人ではありませんでした。
生きているときから、この家は弟(自分の息子)がいるけど、継ぎたければ好きな人間が継げばいいし、継がなくてもいいと言っていました。
田舎の人にしては自由な考え方も持った父だったので、元気で生きていたら、この喧嘩に口出しをしていたと思います。
ただ、亡くなって初めて分かることが多いのが相続問題というもの。
父は口を出したくても、出せない状況にありました。
実際、母は3人姉妹の長女で、男児が生まれないため、長子として家を継ぎました。
祖父や家に同居していた大叔父の遺産は、すべて母が相続していました。
叔母たちは遺産をもらい受けておらず、嫁ぎ先で少なからず苦労をしていました。
その状況を、父が亡くなるまで知らずにいました。
法律が定めようと、田舎には暗黙のルールというものが存在していました。
郷に入れば、郷に従えというものです。
ただやはり、それが田舎の道理だとしても、都会に出てしまった私にはどうしても理解できませんでした。
遺産を自分ひとりに渡してほしい、自分は家を継ぐからという理由で
「全てください」
と言うのはおかしいと思ってしまうのは、おそらく私が都会にかぶれたのでしょう。

長女爆発する ~トラブルメーカーの血を受け継いで
関西からの長旅、ごはん支度、母へのフォロー、フェーン現象で暑すぎる気候…。
私のストレスはマックスでした。
疲れをとるために眠ろうと思っていたのですが、父が亡くなる少し前から実家では怪奇現象が起きていたので、全く眠ることができませんでした(誰かが亡くなるたびに、実家では怪奇現象が起きます)。
色々な要因があいまって、通夜当日の私は疲れがとれることもなく、朝ごはんの支度も上手くできていませんでした。
疲れが溜まっていたせいで愚痴っぽく、弟がいなくなった隙に妹に愚痴をこぼしていました。
すると弟はそんなときだけ耳ざとく
「文句があるなら俺に言え」
と喰ってかかってきました。
喧嘩を売った覚えはありませんが、弟にとっては自分への不満だと感じたのでしょう。
そんなわけで、こうなったら喧嘩です。
妹たちの制止は、もはやこうなると聞こえません。
朝から家の廊下で大喧嘩の始まりです。
殴り合いにならないように祖母も母も止めに入り、弟の婚約者は茫然として階段から見守っていました。
喧嘩の内容はみっともなくてあまり載せられませんが、よくある縁を切るという話にはなりました。
あとは、お金のことばかりに執着して周りのことも考えられない未熟な弟が、結婚して1人の女性を大切にできるのかと、お節介な長女の小言を言ってしまったわけです。
気付けば、妹や姪っ子は泣いていて、私が怒っているのを見たことがない義弟たちは驚いていていました。
しかし、このままだと一生弟と喧嘩しそうだと感じ、喧嘩をやめなければと思いました。
それに、
「死んでも耳だけは聞こえてるって言うじゃん!お父さん聞いてるよ!たった4人のきょうだいなんだから、仲良くしようよ!」
と妹が泣き叫んだからです。
長女ながら、大人げないことを言ったと感じたのですが、おそらくこの大喧嘩がなければ、母は相続について深く考えなかったことでしょう。

大喧嘩の結果
大喧嘩から数時間後、いったん止めたものの、本心では弟を許さないと決めた私は、弟から離れ、妹や母と過ごしていました。
相変わらず母は、通夜の準備などで頭が疲れており、たまにとんちんかんな話をしつつも、父の遺産整理を粛々と進めていました。
妹たちには、
「あの喧嘩は、弟の結婚が破談になってもおかしくないよ」
と言われながらも、私は弟に謝らずにいました。
すると、ほんの数時間もしない間に弟は私のもとへやってきました。
「すみませんでした!!俺が悪かったです!」
末っ子長男の弟は、自分から謝ることができないタイプなので、私はその様子に目を丸くしました。
私は腹の虫がおさまっていなかったので、その様子を静かに見ていたのですが、どうもお嫁さんに諭されたらしく、私に謝ることにしたようです。
「あんたは大したこと言ってないって言われてさ」
よくできた彼女に恵まれたもので(現在でもよくできたお嫁さんをしています)、どうも婚約者の彼女から、お姉さんに頭を下げてきなさいと言われたようです。
自分の信念をすぐ曲げる奴だと最初は呆れていましたが、遺産は分けると本人が決めたようなので、許すことにしました。
これ以上、私も大人げない態度をとっているのも間違いだと思いました。
また弟は、喧嘩のあと母から父の遺産の額を聞き、想像以上に少なかったため、それなら相続してもあまり意味もないし、皆に分けようと考えたようです。
何より、弟自身も反省したようで、これからも仲の良いきょうだいでいたいから、遺産を分けると決めました。
その後、弟はあらゆる場所で私に謝り続け、最後には
「もうええわ」
と言われる始末でした。
私に謝りながらも、きちんと喪主をやり遂げたのは、おそらく親せきの繋がりや、母のサポートがあったからでしょう。
何より弟自身も、家の跡継ぎとしてきちんとやり遂げなければという思いがあったからだと思います。
「なんにせよ、弟の目の上のたんこぶでいなさーい。あの子にはいい薬になるし」
そう笑いながら言ったのは、弟を甘やかして育てた母でした。
もともと厳しい人でしたが、弟には甘かった母が、私にこんなことを言うとは思っていませんでした。
自分がそうであったように、遺産相続はすべて家督を継いだものに全て与えられるべきと考えていた人だったので、最後まで弟の肩を持つと思っていましたが、最終的に、遺産は分配されるべきという考えに変わっていました。
おそらく母にとっても、自分自身の中で認めていた暗黙ルールを壊す、いい機会になったのかもしれません。
画して、父の遺産問題は、私の噴火もといブチ切れと弟の謝罪祭りで幕を引きました。
お葬式ですが、悲しいことばかりではなく、笑い話もたくさんあって、いい葬儀だったのではないかと思います。
ただ私と弟の喧嘩は、やはり母の中ですごく印象に残ったようで、母は葬儀が落ち着くと実家の遺産である、土地の整理を始めるようになりました。

母が始めた土地の整理
父を亡くして、母は抜け殻のようになっていましたが、仕事復帰をすると、徐々に元の母に戻っていきました。
少しでも元気になると、自分の身辺整理
「終活」
を始めました。

家と土地 ~先祖代々の土地と限界集落
私の実家は、母が就職するまで貧しい家でした。
江戸時代には集落でもまだ裕福な家でしたが、その後、家計の厳しい家になりました。
家系的にも体が弱く、男児が早死にすることが多かったそうです。
そのため、自然と女系の家となり、家計が苦しくなったようです。
そのような家で、母は3人姉妹の長女として生まれ、跡継ぎとなり、家を再興していきます。
祖父は体が弱く働いておらず、祖母とふたり、懸命に働いて家を盛り立てていきました。
そして、父は婿とし、結婚した形になります。
父と結婚してから、家の土地の名義は祖父が亡くなるまでは祖父名義、亡くなってからは父名義にしていました。
昔ながらの家ですので、母が家督を継いでも家長は父になるので、名義は父の名前になっていました。
父が亡くなってからは、その名義を変更した方がいいのか悩んでいました。
ようは、弟の名義にするか自分の名義にするかと迷っていたようです。
母は、専門的なことも自分で勉強して片づける人でしたが、加齢と今回のこと(私と弟の喧嘩)で自分だけで解決するのは難しいと考え、司法書士の先生方に相談することにしました。
先祖代々伝わる田畑などがあります。
そちらを、できる範囲で自分が管理しようと考えたようです。
弟が家を継ぐにしても、田舎の土地はそれほど価値のあるものではないし、すでに負の遺産となっているものもあったそうです。
それを如何に、自分の子どもたちへプラスに相続させるかと母は考えていました。

近所の人を巻き込んで ~他人事ではないと気付いて
母が司法書士の先生方に相談していることを集落の方たちが気付くと、自然と母に自分たちの土地のことも相談するようになっていました。
ようは、母だけではなく、集落の方々も同じように相続した土地について悩んでいたのです。
先祖代々の土地は、田畑にし、作物を育てるのに良いのですが、昔から
「あれは○○の家の田んぼで…」
と言い伝えられていても本当に、その家の土地なのか不明なものがたくさん存在していました。
そして限界集落のため、もはや家に誰もおらず、家族も都会に出てしまい、帰ってこない家の土地も多くあります。
その土地をどうするのかも、集落の人たちにとっては大きな課題だったのです。
母がそのように土地を整理し始めたことによって周りの方々も
「自分がまだ処理できるうちに…」
と行動を始めました。
母もできるうちにと、集落の方々と一緒に土地の整理をしていきました。
土地だけでなく、相続するであろう遺産(お金)に関しては、きちんと子どもたちで当分できるように手配をしていました。
手配後は、遺産を分割したことも私たちと共有していました。

餅は餅屋へ。専門家へご相談を!
経験から学んだ結果
父の葬儀が終わってから、終活を始めた母。
先祖代々の土地や、自分が築いた財産で子どもたちが二度ともめないように、各専門家の先生方に相談を始めました。
母は
「多少お金はかかったけど、あんたたちの喧嘩する姿を見なくても済むならなんちゃあないお金よ」
と笑って言っていました。
それを聞くたびに、母に申し訳ない気持ちでいっぱいになります。
キャリアウーマンという言葉は死語かもしれませんが、仕事一筋で生きてきた母が、子どもにきちんと残してあげられることは何か、と考えた答えだとも思っています。
土地をはじめとする相続が絡む遺産は、相続していた方が生きているときに整理してくれていると、残されたものとしては少なからず、重荷にならずに済みます。
私の父の場合は、20年以上病気だったので仕方ないですが。
その分、母が動いてくれて子どもの私たちにとっては、とても助かりました。
母がこうして助けてくれたので、二度と母に嫌な思いはさせたくありません。
よって、これからもきょうだい4人仲良く、どんな苦労も乗り越えていこうと決意しました。
こうして前向きに思えた理由の1つに、母が専門家の先生方に相談してくれたこともあります。
きょうだい間で無用な争いを避けられるように、母が用意してくれたのは本当に有り難いことでした。
日本ではまだ、身内のことを公に晒すことに抵抗感を持っていますが、大事な人と不必要な争いを生まないためにも、第三者に入ってもらうことは、大事なことです。
はじめは恥ずかしい、面倒くさい。
しかしそんなことも、誰かに介入してもらうことで丸く解決することもあります。
私の話を対岸の火事と思わず、いつかご自身に起こることとして、皆さんの頭の隅っこに置いていただけたら幸いです。
そして、むやみな争いを生まないように、私の経験を誰かの糧としてくださればとも思っています。

ご相談はがもう相続センターへ
自分の身近に相続の問題が起きてから、その問題を対応することが多いと思います。
また、私の母のように終活をはじめて、相続について考えはじめた方もいるかと思います。
ご自身で勉強されるのも、とても良いかと思いますが、困ったときには、専門家の知恵を拝借することをおすすめします。
知恵を借りるのは悪いことではありませんし、誰かと問題を分かち合うことで肩の荷が少し落ちるというものです。
弁護士事務所や司法書士事務所は、敷居が高い…と感じられている方も多いかもしれません。
ただ、一度足を運ぶとそうでもないなと感じられます。
蒲生相続相談センターでは、現在無料で相談を受け付けています。
事前予約をしていただき、先生方に相談していただく形をとっています。
さらに、無料のセミナーも開催していますので、そちらにご参加もお待ちしております。
直接的な話はまだ早い、お電話が苦手…という方は、公式LINEもありますので、気軽にお問合せ可能です↓
皆様のお悩みを少しでも解決できればと思いますので、ご連絡お待ちしております。

がもう相続相談センターのサービス
蒲生相続相談センターでは「遺言書残したいプラン」を提供しています。
詳細はこちらからご確認ください。
遺言残したいプラン(遺言書作成)
「遺言残したいプラン」は、ご自身の想いを書面に残し、自分がお亡くなりになった後の全てを決めておきたい方や、残されたご家族が揉めないように笑顔で過ごしてくれることを望む方にマッチするプランです。
遺言書がなく、財産の取り合いで揉めているケースが増加しています。
亡くなった後の相続人が揉めないようにするためにも、あなたの行動が将来の家族を守ります。
まずは、お気軽にご相談ください。
