
今回の記事では、後見人についてお話させていだきます。
「後見人ってそもそも何をする人?」
後見人という言葉は、知っているけれど、どういったものなのか知らない方は多いと思います。
一般的には見守る人、または後ろ盾というイメージが強いかもしれません。
今回お話しする後見人も、「見守る人」の意味合いが強いと感じるかもしれません。
ただこの後見人は、見守るだけではなく、本人の代理として財産の管理を行ったりします。
これだけの情報だと、家族の財産を管理しているだけなので、老後の親の面倒を見ているのとなんら変わりはない気もします。
そのため、別に後見人制度など利用しなくても良いのでは?と思いがちになってしまいます。
しかし、後見人制度は国が制度として認め、推進しているものです。
不要なものを国は制度化しません。
必要性があるからこそ、国が制度化し、推し進めているのです。
このような後見人制度について、聞いたことはあるものの、「後見人」そのもの、その制度内容を理解していないと、活用するにもできません。
今回は、
「後見人が選任された際のメリット・デメリットは?」
など、後見人制度について詳しくお伝えできたらと思います。
この記事で、後見人制度の知識を深めていってください。
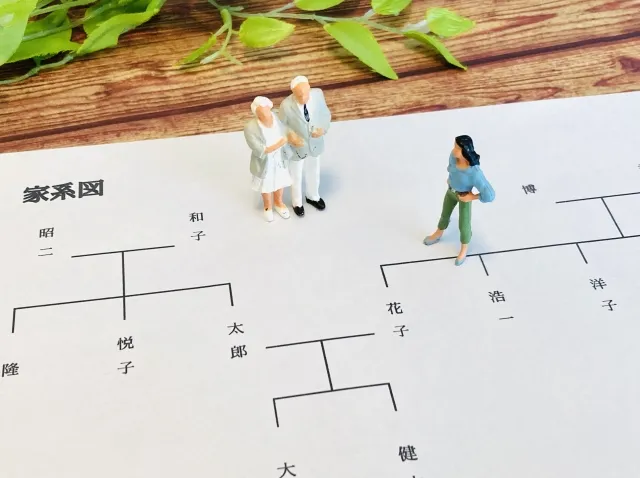
目次
後見人は判断能力が不十分な方の代理人
後見人というのは簡単にいうと、判断能力の不十分な方の代理人ということになります。
認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力が不十分な方は、ご自身で自分の財産を管理したり、身のまわりのことを行うことが難しくなります。
自分で判断したために、悪徳商法の契約を結ばされる場合もあります。
そのような被害から守り、判断能力が不十分な方を保護する制度。
そして、支援していくのが成年後見人制度と言います。
また、後見人といっても、
・任意後見人
・法定後見人
上記ふたつの制度が存在します。
任意後見人制度とは、成年後見人となってもらう人を事前に決めておき、対象となる方の判断能力が不十分と認定された際に、成年後見人となる制度です。
事前に選出された方は、対象となる方がお亡くなりになるまで、成年後見人となります。
法定後見人制度とは、すでに対象となる方の判断能力が失われている、または不十分となっている場合に、家庭裁判所に申立てをして、本人を支援・保護する人を選ぶ制度です。
法定後見は、対象となる方の状況に応じて・後見・保佐・補助の3つの類型に分かれ、対象となる方を支援する人をそれぞれ・成年後見人・保佐人・補助人と呼びます。
これらが本人の代理となり、契約などを結んだり、対象となるご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたりします。
本人の同意を得ないで行った不利益な契約などを、後から取り消したりすることによって、本人を保護や支援を行います。
このふたつの制度ですが、何が違うかというと、
対象となるご本人さまが自分で選任したかどうかの違い
です。
認知症等になってしまうと、判断能力が落ちてしまいます。
ご自身で判断できなくなったり、何もできなくなってしまうと、不具合が生じてしまうので、成年後見人という制度が作られました。
ここまで制度の説明をしてきましたが、いったん説明はここまでにして、次項からは、成年後見人が選任された際のメリット・デメリットを見ていきましょう。
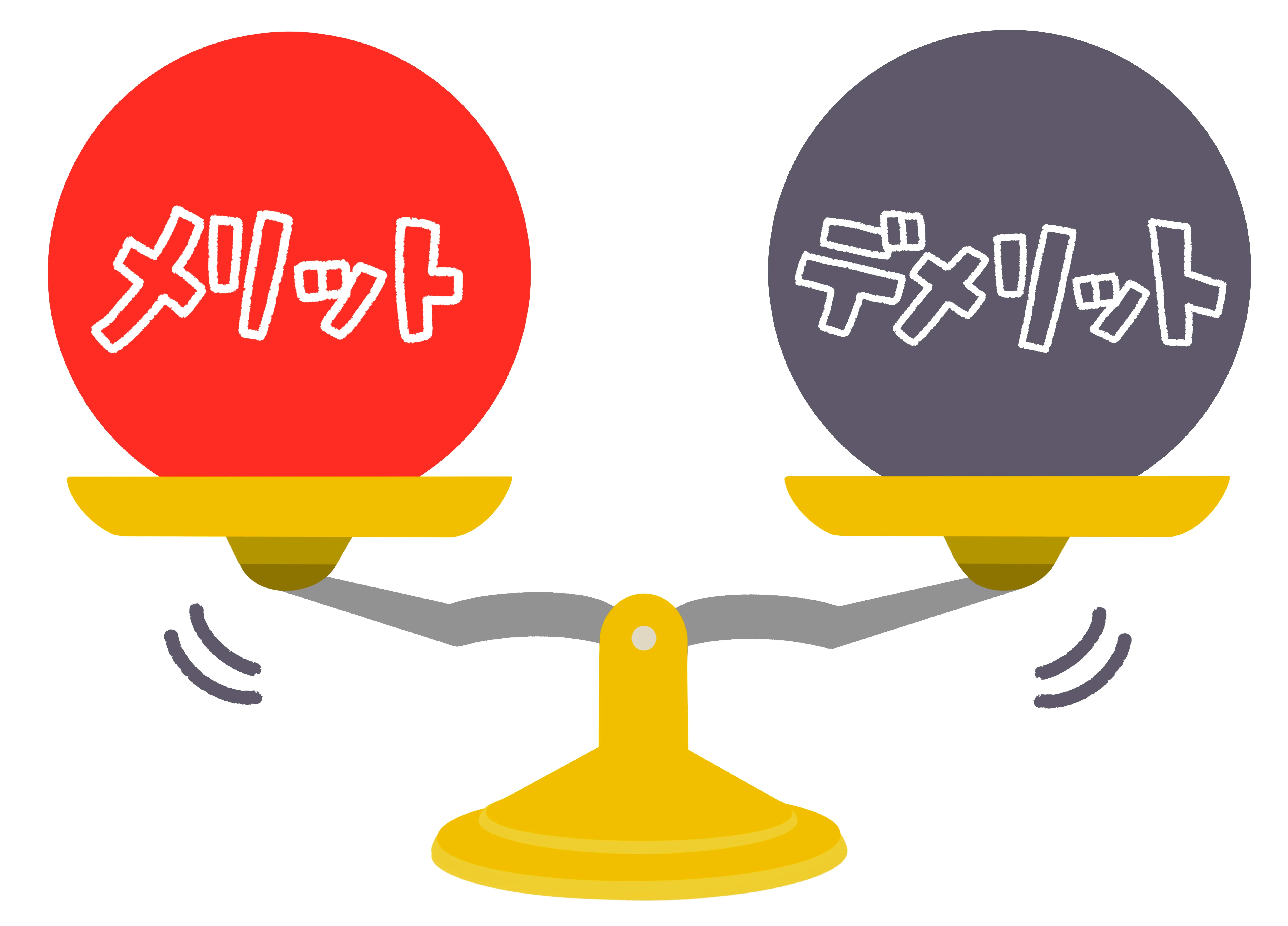
メリット
では、成年後見人が選任された場合の、メリットをあげていきます。
①裁判所が認めてくれたことに対して、ご本人さまの代わりにできることが増える
成年後見人制度は、判断能力が不十分になった方の代わりに契約などのお手続きができるようになります。
たとえば、認知症が発症した際、判断能力が不十分になり、契約手続きや解約手続きが難しくなります。
判断能力が不十分であるために、ご自身が不利になる契約を結んでしまったりします。それを防止するのが、成年後見人制度です。
成年後見人が選らばれると、裁判所が認めてくれたことに対して、後見人はご本人さまに代わってお手続きをすることが可能です。
不当な契約の解除や、銀行解約、不動産の売却などが主な例となります。
②裁判所が関与することによって不要な契約などが生まれない
成年後見人が、選任されるとその方の財産は、裁判所の管轄のもと成年後見人が管理することになります。
日常の雑貨であれば問題ありませんが、高額なお金が動く場合は、裁判所の許可を取らなければいけません。
なので、容易にご本人さまの財産が引き出せなくなるので、ご本人さまの財産が守ることにつながります。
これが成年後見人の最大のメリットとも言えます。
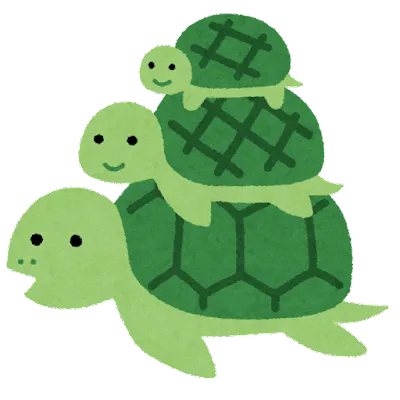
デメリット
では次に、成年後見人が選任された場合のデメリットをあげていきます。
①裁判所が関与するので、自由な契約等ができなくなる
先ほど、ご本人さまの財産を裁判所の管轄のもと、成年後見人が管理することをお話させていただきました。
つまりご本人さまの財産を、自由に引き出したりすることができなくなります。
簡単にいうと、高額のお金を引き出すときは、裁判所の手続きを踏まなければならないので、不便になります。
今までのように簡単に、ご本人様のキャッシュカードで、ATMからお金を引き出したりするのはNGです。
すべて高額なお金を引き出す際は、裁判所への手続きをしなければいけないので、時間もかかりますし、使用するお金は吟味されます。
さらに成年後見人が選任されないと公には、何もできなくなるので、とても不便になりますね。
この不便さというのが、成年後見人制度の1番のデメリットかもしれませんが、1番のメリットでもあるといえます。
②成年後見人には、弁護士、司法書士などの専門家が選ばれる
成年後見人になるために、資格はいりません。
そのため、ご親族がなることも原則可能です。
しかし、昨今、親族の横領事件が多かったため、裁判所は、弁護士、司法書士などの法律専門家を選ぶことが多いです。
そして、専門家が選ばれると、成年後見人に報酬がかかります。
年に1回、報酬を支払うこととなり、ご本人さまの財産の額に応じて報酬は変動しますが、大体の目安といたしましては、
ご本人さまの財産額が1,000万円未満の場合は、年24万円くらい。
5,000万円を超える場合は、年60万円くらいが目安となります。
決して安くない金額のため、この報酬もデメリットのひとつかなと思います。
③1度選任されてしまうとお亡くなりになるまで成年後見人が代理人となる
いちど成年後見人が選任されると、ご本人さまがお亡くなりになるまで、代理行為は続いきます。
そのため、ひとつの案件のみのお手続きではないということです。
当然お亡くなりになるまで、成年後見人の報酬はかかり続けます。
そういった面も、成年後見人のデメリットであると言えます。
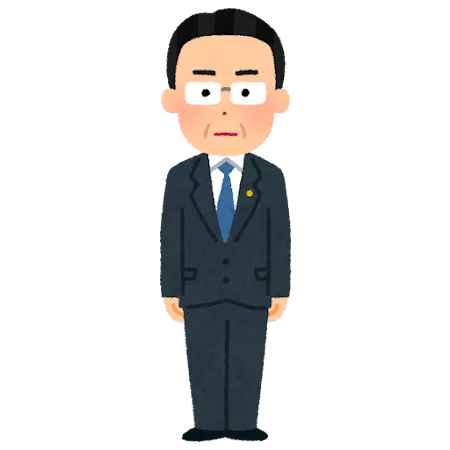
具体例
では、成年後見人を選任してよかった具体例を見ていきましょう。
ご本人さまが、認知症を発症し、成年後見人を選任してご自宅を売却した事例です。
今回のお客様のケースは、認知症のご相談ではありませんでした。
ご相談内容は、ご本人さまが高齢になってきたので、ご自宅を売却して、施設に入居させたいというものでした。
ご本人さまは病院に入院していて、認知症にかかっている。
この現状を鑑み、早速、成年後見制度のことをご説明しました。
ご依頼人の方には、ひととおり説明したあと、ご理解いただけたので、裁判所に成年後見人選任の申し立てを行いました。
その後、弁護士が成年後見人として選任され、無事に不動産売却まで終えることができました。
ご自宅の売却代金は、施設の入居代金に当てることができました。
そして、これからのご本人さまの生活代金として、成年後見人に管理してもらうという1番良い形でお手続きが終了しました。

でも、成年後見人って不便じゃない?
ここまで、成年後見人のメリット・デメリット、具体例をお話ししてきました。
私見も入っておりますが、はっきり申し上げて、自由が利かないので、成年後見人制度は不便だと思います。
しかしながら、ご本人さまの財産ということを、忘れてはいけません。
普段、司法書士の業務を行っていて、感じることがあります。
それは、お亡くなりになられた方の財産やご本人さまの財産を、自分の財産であるかのように考えているご相続人様が多いということです。
ご本人さまの財産なので、本来はご本人さま自身が、処分を決めるべきだと思います。
具体例のような、ご本人さまのためを考えて行う行為であれば、充分、有意義だと思います。
成年後見人を選任して、裁判所の管轄のもと、管理していくので、成年後見人制度をうまく活用できているでしょう。
不便だからという理由で、成年後見人制度を利用しないのではなく、あくまでのご本人さまの財産であるという観点から、成年後見人制度を考えてみてはどうでしょうか。
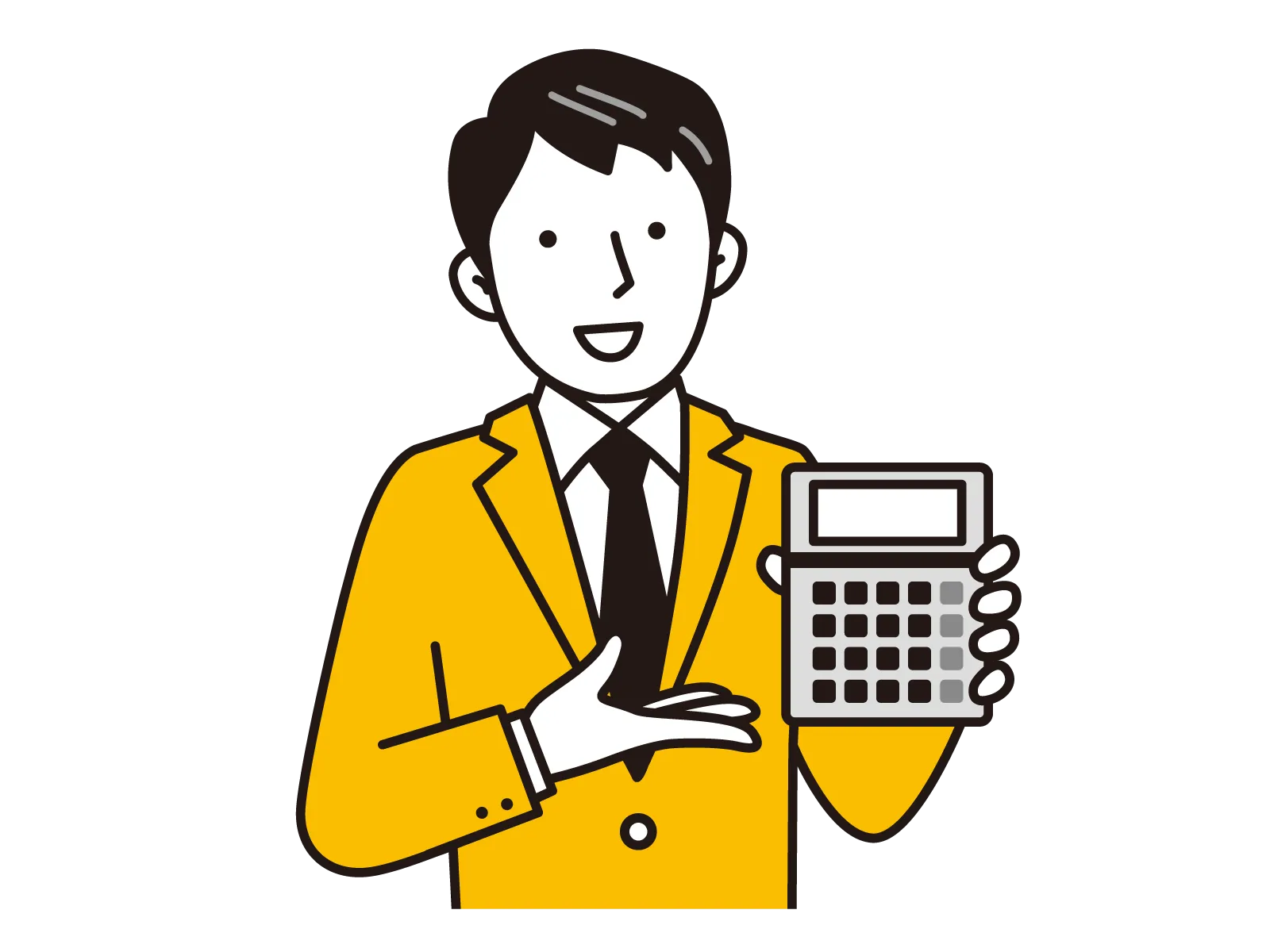
成年後見制度は価値のあるもの
本来、ご本人さまが認知症を発症したり、なんらかの理由で判断能力が不十分になるとご本人さまの財産を動かすことはできません。
重ねてお伝えしますが、ご本人さまの財産なので、本来はご本人さま自身が、処分を決めるべきものです。
ご本人さまがご存命のうちは、その財産をどう管理するかを決めるのは親族でもなく、本当はご本人だけのはずです。
いつかその遺産を相続するとしても、ご本人さまがお亡くなりになって、ご自身が相続人となり、相続してはじめてご自身の財産となります。
判断能力が不十分であるがゆえに、財産の処遇を決められない。
ましてや、それを他人が勝手に決めてしまっていいものではありません。
お亡くなりになるまで、何もできなかったことが、事情によっては、財産を動かすことができるという意味合いで、成年後見制度は、とても有意義な制度と言えるでしょう。
不便な制度だとは思います。
でも、判断能力が不十分な方にとっては、その方と一緒に財産や生き方を見守る、とても有意義な制度だと言えます。

蒲生相続相談センターのサービス
蒲生相続相談センターでは「代理人・家族を信じて託すプラン」を提供しています。
詳細はこちらからご確認ください。
代理人・家族を信じて託すプラン(後見・家族信託)
代理人・家族を信じて託すプラン は、
「ご家族が認知症になってしまった・・」
「まだ認知症になっていないけれど高齢になってきたから不安だ・・」
というお客様をサポートするプランです。
ご家族が認知症になりお困りの方、将来的に認知症になっても資産の売却や運用が出来るようにして、介護費用等にあてたいと思っている方にはこのプランが最適です。
相続では、事前対策がすごく重要になります。
後で動いて損をしてしまった方も多く見てきました。
損をしたくない方は、事前に対策することをお勧めします。
