めっきり朝晩寒くなってきましたね!
がもう相続相談センター ほんじょうです!
ほんじょうは、毎年ダウンを来て寒さをしのいでいますが、今年はスタジャンを来ています笑 案外あたたかくて重宝しています!
冷えは、健康の大敵!皆様も少しでも寒いと思ったら我慢せず、温かくしてくださいね。
さて、今回は生命保険を活用した相続対策のメリットとデメリットについてお話ししていこうと思います。
生命保険は、「万が一の時のため」にと思い、掛けている保険として、多くの人が利用していると思います。そんな生命保険ですが、実は相続税の負担を軽減することもできます。
生命保険は節税の手段として活用されることも多いです。ただ、具体的にどんな節税対策ができるのかというのはなかなか分からないものですよね。
そこで今回は生命保険を活用する際のメリットや注意点、そして活用方法などについてもご紹介したいと思います。

目次
◯生命保険の基本について
まずは生命保険の基本になりますが、生命保険というのは契約者から保険会社に保険料を支払い、被保険者が死亡した場合に、死亡保険金を受取人に支払うという仕組みになります。
そして生命保険には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
・定期保険
保険期間が定められていて、保険期間内に被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われる保険になります。掛け捨てタイプが多いので保険料自体も安価といった特徴があります。
・終身保険
保険期間が一生涯であり、被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われる保険になります。相続税の対策としては最も活用しやすい保険のタイプになります。
・養老保険
被保険者が一定の年齢に達したときに、死亡保険金もしくは生存保険金が支払われる保険になります。主に貯蓄や運用といった意味合いとして利用されることが多いです。
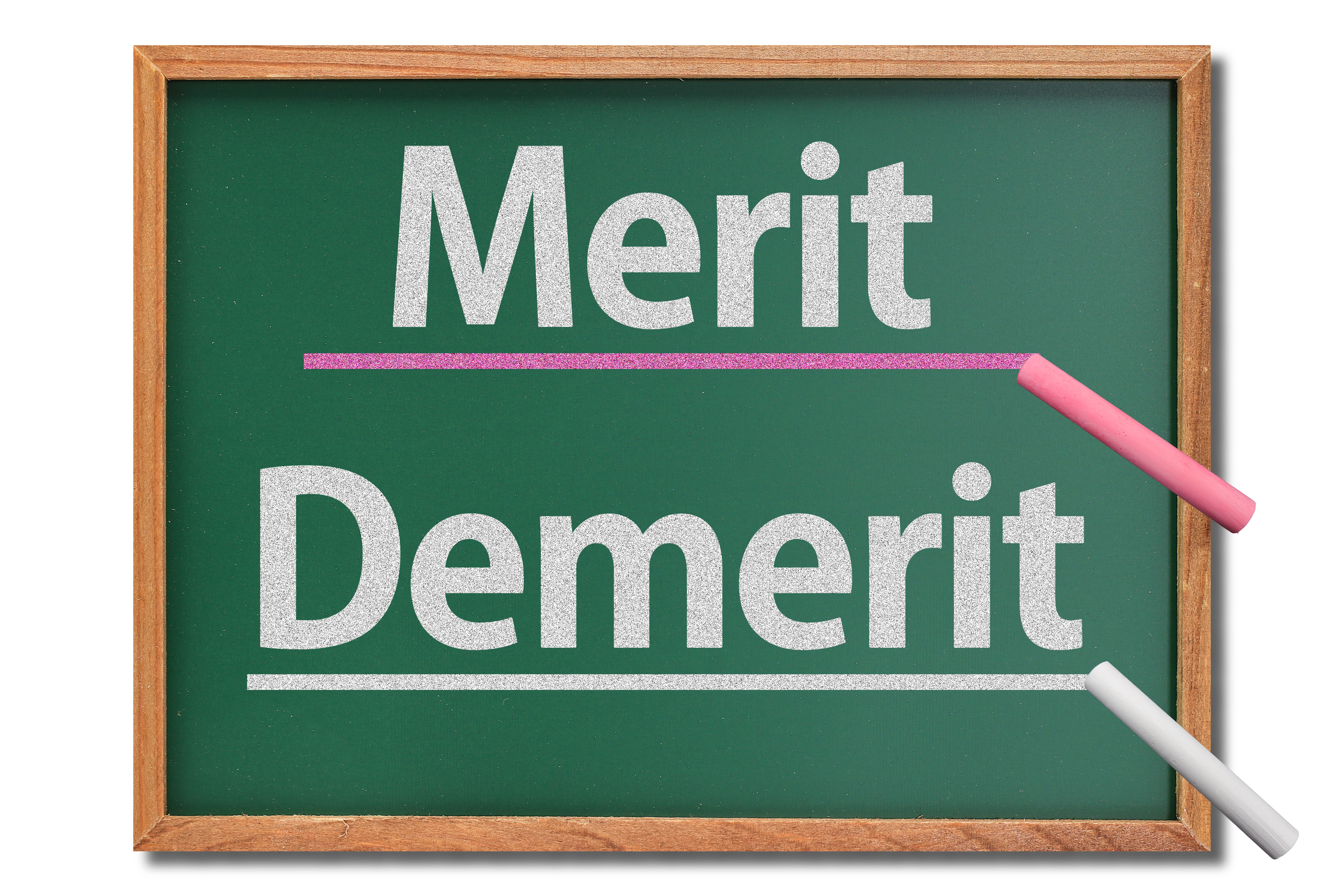
◯相続時の生命保険のメリットについて
相続時の生命保険には以下の様なメリットがあります。
・遺産分割の対象とならない
生命保険の死亡保険金は、遺産分割の対象とはなりません。そのため、相続人同士のトラブルを避けることもできます。
・法定相続人は相続税の非課税枠が適用される
生命保険の死亡保険金は、一定の条件を満たす場合、相続税の非課税枠が適用されます。そのため、相続税の負担を軽減することができます。
非課税枠は、法定相続人の人数によって異なります。
- 法定相続人が1人の場合:500万円
- 法定相続人が2人以上の場合:500万円×法定相続人の数
・納税資金の確保に役立つ
相続税の納税に必要な資金が不足する場合、死亡保険金を納税資金に充てることができます。
・特定の人に財産を相続させることができる
死亡保険金の受取人を特定の人に指定することで、特定の人に財産を相続させることができます。
上記をまとめると、
・遺産分割のトラブルを避けられる
・相続税の負担を軽減できる
・納税資金を確保できる
・特定の人に財産を相続させられる
などのメリットがあります。
◯相続時の生命保険のデメリットについて
・保険料が高い場合払えなくなるリスクもある
相続税対策として活用しやすい終身保険は一生涯保証が約束される保険でもあります。契約者が解約を行わない限りは保険会社は死亡保険金を支払う必要があります。
そのため終身保険は高額になる傾向があり、設定する保険の金額によっては月々の支払う保険料も高くなり、保険料金が負担となった場合には解約をしなくてはいけなくなる状況も考えられます。
・元本割れのリスク
生命保険は一つの金融商品でもあるので、内容によっては元本割れのリスクも伴ってきます。
仮に相続対策として生命保険に加入した場合でも元本割れしてしまった場合は相続財産が目減りしてしまう結果になることもあります。
生命保険の契約時には契約内容をしっかりと確認してご自身に合った保険・保証内容になっているのかを確認しておく必要があります。
・遺産分割ができないことでトラブルになることも
先述したように生命保険は受取人を指定できるため、場合によっては遺産分割の対象にならないということもあります。
そのため相続人同士や相続人以外で生命保険の受取人になっている場合、不平不満が出てきてしまいトラブルに発展してしまう可能性も0ではありません。
◯相続税対策としての生命保険の活用法
ここまでで生命保険は、相続対策として有効な手段ということがわかりました。では次に生命保険を相続対策に活用する方法についてもご紹介したいと思います。
生命保険を相続税対策に活用する場合には具体的に以下の様な方法があります。
・相続税の納税に充てることが可能
相続税の納税に必要な資金が不足する場合は、死亡保険金を相続税の納税に充てることができます。死亡保険金は、相続税の非課税枠が適用されるため、相続税の負担を軽減することができます。
例えば、相続税の納税額が1,000万円の場合、法定相続人が2人以上であれば、死亡保険金の非課税枠は500万円×2人=1,000万円となります。そのため、死亡保険金を1,000万円以上準備しておけば、相続税の納税に充てることができます。
・受取人に相続財産を分けることができる
相続財産を平等に分割したい場合、死亡保険金を受取人に分けて相続させることができます。死亡保険金は、遺産分割の対象とはならないため、受取人が自由に使うことができます。
例えば、相続財産が1000万円で、法定相続人が3人の場合、相続財産は333万円ずつ相続されます。この場合、死亡保険金を333万円ずつ受取人に分けて相続させることで、相続財産を平等に分割することができます。
・遺言の代用とすることが可能
遺言を作成せずに、死亡保険金を特定の人に相続させる場合は、遺言の代用として死亡保険金を活用することができます。死亡保険金は、受取人が自由に使えるため、遺言を作成せずに、特定の人に財産を相続させることができます。
例えば、遺言を作成せずに、死亡保険金を孫に相続させたい場合、死亡保険金の受取人を孫に指定することで、遺言の代用として死亡保険金を活用することができます。
ただ生命保険は、相続対策として有効な手段ですが、単独で相続税対策を完結させることはできませんので注意は必要となります。
◯まとめ
今回は生命保険を活用した相続対策のメリットとデメリットについてご紹介しました。
生命保険は活用次第で節税対策にもつながります。相続税対策は早く行うことでその効果も高くなりますので出来るだけ早く相続対策を行い、財産を多く残せる様に努めたいですね。
がもう相続相談センターのサービス
がもう相続相談センターでは、
「まるごと任せたいプラン」
を提供しています。
詳細はこちらからご確認ください。
まるごと任せたいプラン(相続手続き)
相続のお手続きは、手間がかかるものが多いといえます。
また、「知らなかった」、「誰も教えてくれなかった」と仰って、問題がおきてから、ご相談にいらっしゃる方もいますが、相続税対策などは早めに取り組む必要があります。
タイミングを逃したり、時間を無駄にしたりしたくない方は、ぜひ、専門家にご相談ください。
何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。
面倒くさいと思って放置してしまうと、さらに時間がかかってしまうことがあります。
大ごとになる前に、ぜひ専門家にご相談、そして、がもう相続相談センターをご利用ください。
専門家があなたを支えます。
