
みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
前回の記事で、基礎控除と特例控除についてお話しさせていただきました。
まだ、前回の記事をご覧になられていない方であれば、ご閲覧ください。
こちらです!!
今回も特例控除の続きをお話しさせていただきます。

目次
結論
特例控除の続きを挙げていきたいと思います。
そして、お客様にはあまり馴染みのない相続税対策だと思いますので、この機会に知っていただければと思います。
①配偶者控除
お亡くなりになられた方の配偶者(夫・妻)が全てを相続する場合、お亡くなりになられた方の財産が1憶6,000万円までであれば、相続税はかかりません。
配偶者には手厚い保護があるので、この特例控除を使えば、一般のご家庭であれば相続税は、ほとんどかからない事になります。
ただし次のご相続の事を考えると、基礎控除以上に財産をお持ちの方であれば、次の事前対策を考えていく必要があると考えます。
②未成年控除
未成年控除は、相続した年齢が何歳だったかによって控除額が変わってきます。
(20歳-相続した年齢)×10万円=控除額
の計算になります。
例えば、未成年のお子様(15歳)が相続されたとします。
(20歳-15歳)×10万円=50万円
控除額は50万円になります。
未成年のお子様の相続税が、100万円だったとします。
そこから、50万円を引いた50万円が相続税となります。
③小規模宅地の特例控除
小規模宅地等の特例とは、相続人が被相続人とともに居住していた土地を相続する場合など、所定の要件を満たせば土地の相続評価額が減額される特例です。
一定の要件を満たした場合、お亡くなりになられた方の土地の面積を80%(上限330㎡)圧縮した価格として、相続財産に計上することが出来ます。
1.被相続人の配偶者が土地を相続
2.被相続人の同居人が土地を相続
相続税の不動産の算定方法ですが、
土地については路線価、
建物については固定資産税評価額となっています。
この「小規模宅地の特例控除」を用いると、土地の路線価格の㎡単価を面積にかけて、その合計額の80%を圧縮できるという事になります。
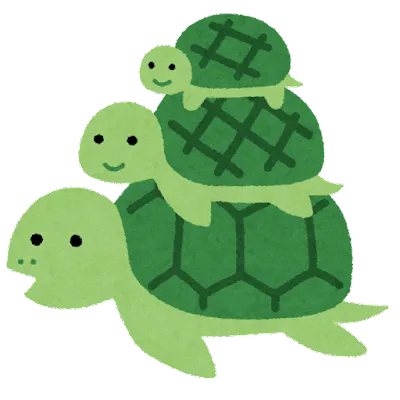
基礎控除
これはとても重要な事なので再度挙げさせていただきます。
相続税の基礎控除についてですが、
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)=基礎控除額
の計算になります。
相続税は、この基礎控除額以内であればかかりません。
基礎控除なので、必ず全ての相続税に適用出来ます。
例えば、相続人様が4名いるとします。
この基礎控除額は、
3,000万円+600万円×4名=5,400万円
となります。

特例控除
今、お話しさせていただきました基礎控除と合わせて、特例控除も挙げさせていただきます。
初めにお話しさせていただきました①~③が特例控除になります。
基礎控除は、必ず相続税申告で控除して、相続税を計算します。
仮に基礎控除を引かずに相続税申告した場合、税務署から基礎控除を引いた上で、相続税を計算してくださいと指摘されます。
お客様にとっては、「得」をすることになります。
特例控除は、仮に特例控除を引かずに相続税申告した場合、税務署から指摘はされません。
申告した通りに受付されるので、
お客様にとっては、「損」をする事になります。

相続税
相続税の申告についても、お話しさせていただきます。
原則、お亡くなりになられた方に財産がない場合や基礎控除を用いて、相続税を計算して相続税がかからない場合は、相続税の申告が必要ありません。
しかし、特例控除を用いた場合で、「配偶者控除」「小規模宅地の特例控除」を用いた場合、相続税がかからなくても、相続税の申告が必要になります。
「配偶者控除」「小規模宅地の特例控除」 については、次回の記事にてお話しさせていただきます。
なので、お客様がご自身で相続税申告をお考えの場合、こういう事実を知った上で、お手続きをするか、専門家にお任せすることをおすすめします。
では、特例控除を活用した相続税の事前対策をご説明させていただきます。

活用方法
これは以前、相続税の事前対策で実際にお客様にお話しさせていただいて、お客様に活用していただいた事例です。
配偶者控除の非課税枠の活用方法
では、活用方法をご説明させていただきます。
【前提情報】
現金7,000万円所有
ご自宅(固定資産税評価額は7,000万円)相続人は配偶者+お子様4名の5人
このままであれば、基礎控除3,000万円+600万円×5=6,000万円となり、
単純計算でも8,000万円がオーバーとなり、相続税がかかります。
なので、配偶者控除の1億6,000万円の非課税枠を活用して、配偶者の方が全額相続していただき、相続税はかかりませんが、相続税申告を行います。
しかしこのままでは、配偶者様がお亡くなりになられた際に、お子様4名がご相続された時に高額な相続税がかかる可能性があるので、配偶者様に相続税の事前対策を行っていただき、相続税の圧縮を図ります。
具体的には、 生命保険の非課税枠 を用いて、生命保険加入や収益不動産購入などの事前対策を考えていきます。
そうすることにより、相続税が圧縮出来ます。

再度結論
財産がお持ちの方であれば、相続税の事前対策をご検討は必要だと思います。
現在のご自身の財産が把握出来、現財産での相続税もわかります。
その上で、相続税の事前対策を検討していくので、専門家にご相談するのは、「損」を回避することに繋がると思います。
是非、皆様には「損」を回避していただきたいと思います。
蒲生相続相談センターでは、相続税に事前対策をサポートさせていただいてます。

蒲生相続センターのサービス
蒲生相続相談センターでは「亡くなる前に事前対策プラン」を提供しています。
詳細はこちらからご確認ください。
亡くなる前に事前対策プラン(相続・税務)
亡くなる前に事前対策プランは、お亡くなりになる前に相続税対策をするサービスです。
・事前に相続税対策をしておきたい
・相続税が支払えるか心配
・損をしたくない
という方は当プランがマッチします。
対処を後回しにし、亡くなられた後のご家族が困っているのをたくさん見てきました。
ご家族が後で困らないように、お早めにご相談ください。
