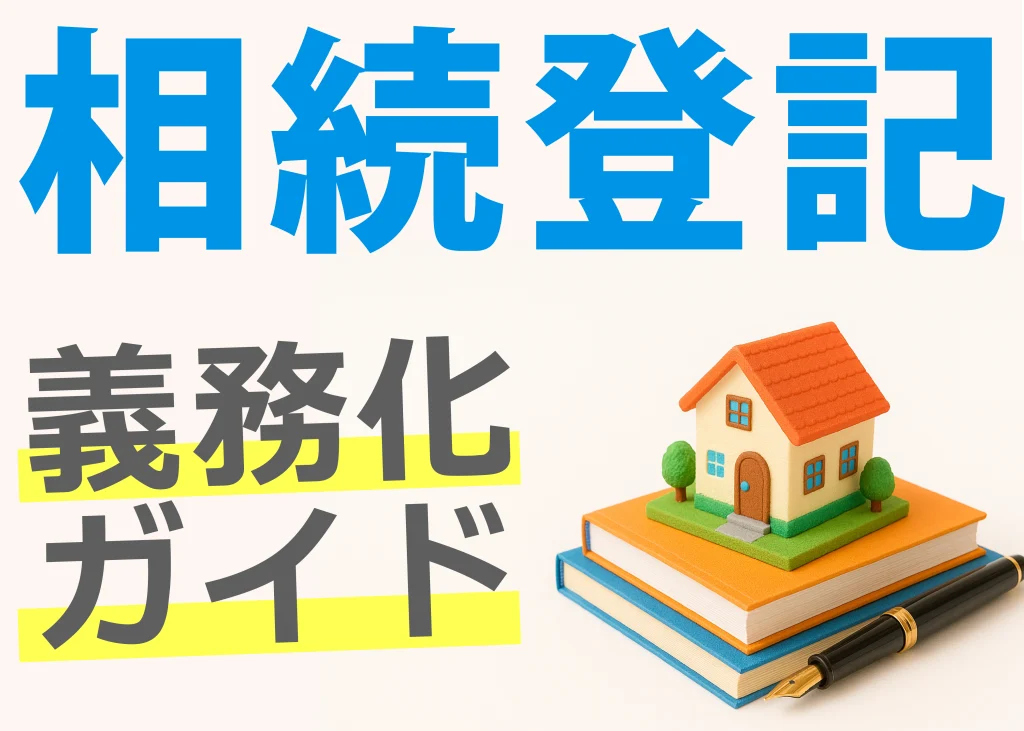
昔のままにしていた土地、今は放置できません
親の名義のままになっている土地や建物。
「いつか手続きしよう」と思いながら、ずっとそのままになっていませんか。
2024年4月から、相続登記(名義変更)が法律上の義務になりました。
これまでは手続きをしなくても特に制限はありませんでしたが、
今後は放置すると過料の対象になる場合があります。
しかも今回の改正は、過去の相続までさかのぼって適用されます。
つまり、何年も前に親や祖父母が亡くなった場合でも、
まだ登記していなければ義務違反となる可能性があるのです。
この記事では、相続登記義務化の内容と期限、
そして過去の相続をどう扱うかを、2025年時点のルールに基づいてわかりやすく解説します。
こちらの記事も読まれています。
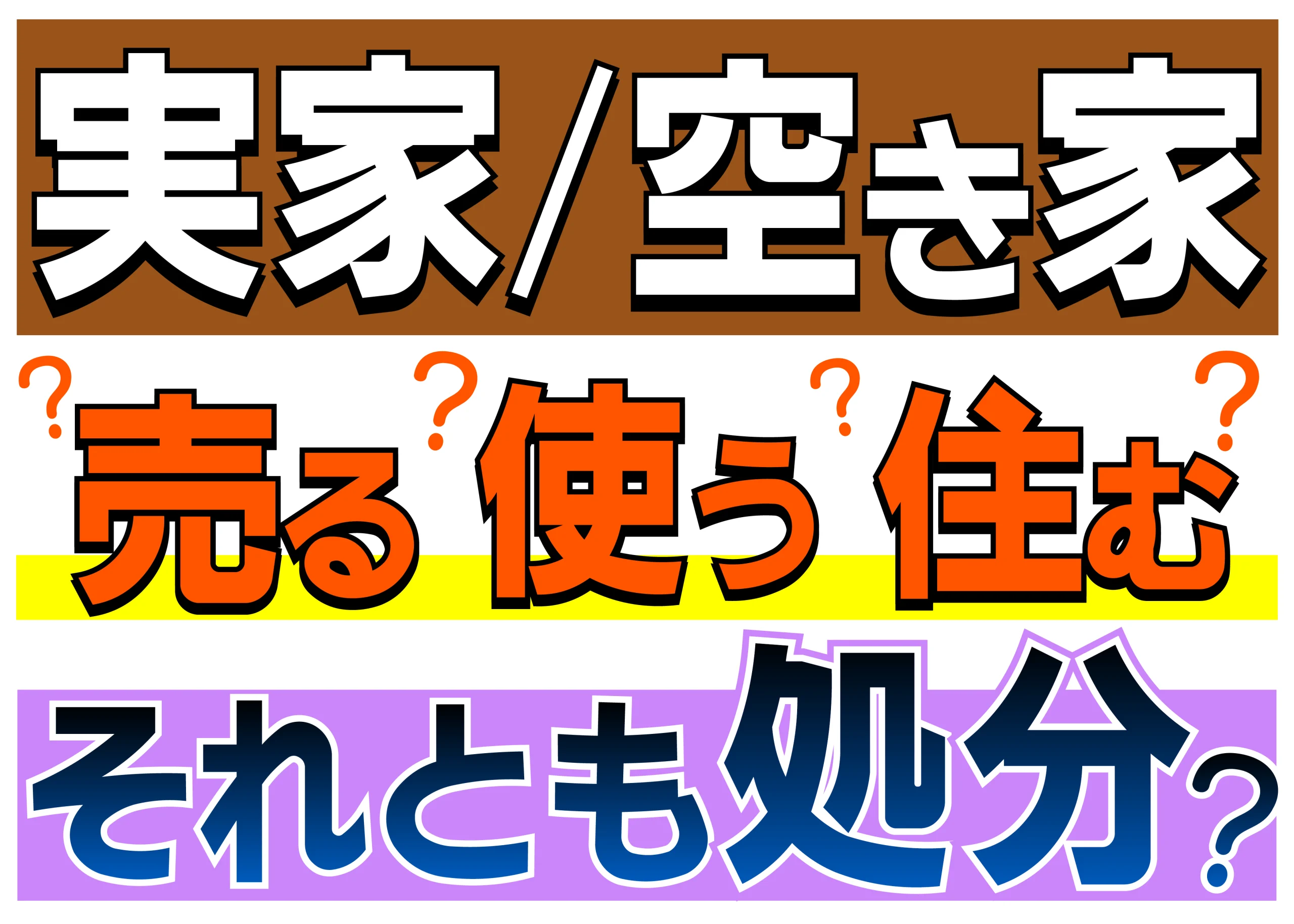
1. 相続登記義務化とは何か

相続登記とは、亡くなった人の名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、父親が亡くなり自宅を相続した場合、
登記簿上の名義を父から自分へ変更する必要があります。
これまで登記は任意でしたが、
登記を放置した土地が全国で増えた結果、所有者がわからない土地が問題になりました。
そのため、2024年4月1日から改正不動産登記法が施行され、登記が義務となりました。
2. 義務化の内容と期限
相続登記の義務化は2024年4月1日から始まっています。
この日以降に相続で不動産を取得した人は、
相続があったことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
【新しいルールの概要】
・対象:相続や遺贈で不動産を取得した人
・期限:相続があったことを知った日から3年以内
・過料:正当な理由なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料の可能性あり
登記を行わないままにしておくと、法律上の義務を果たしていない状態になります。
期限を過ぎても正当な理由があれば免除されますが、原則として期限内の手続きが求められます。
3. 過去の相続も対象になる
2024年4月1日より前に起こった相続も対象に含まれます。
例えば、
・10年前に親が亡くなって登記をしていない
・祖父母名義の土地をそのままにしている
・登記簿上の所有者がすでに亡くなっている
これらはいずれも義務化の対象です。
ただし、過去の相続については経過措置があり、
施行日から3年間、すなわち2027年3月31日までは猶予期間が設けられています。
【期限のまとめ】
| 相続の時期 | 登記の期限 |
| 2024年4月1日以降の相続 | 相続を知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前の相続 | 2027年3月31日までに登記 |
4. 義務化の背景

相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の増加があります。
登記をせずに放置したまま相続が続くと、
相続人の数が増えて所有者が誰か分からなくなり、
公共事業や再開発、災害復旧が進まない問題が起きていました。
国土交通省による調査では、所有者が不明な土地の総面積が
九州地方の面積を上回る規模に達しているとされています。
こうした社会的課題を解消するために、義務化が導入されました。
5. 放置した場合のリスク

登記を行わずに放置しておくと、次のようなリスクが生じます。
・不動産を売却したり担保に入れたりできない
・相続人の一人が亡くなると相続関係が複雑化する
・固定資産税だけが発生し続ける
・将来的に過料の対象になる可能性がある
このように、放置すればするほど手間と費用が増えてしまいます。
早めに登記を行うことが、結果的に家族の負担を軽くします。
6. 登記義務化への対応ステップ
まずは名義を確認
登記簿謄本を確認し、名義が故人のままになっていないかを調べましょう。
法務局やオンラインの登記情報提供サービスで簡単に確認できます。
こちらの記事も読まれています。
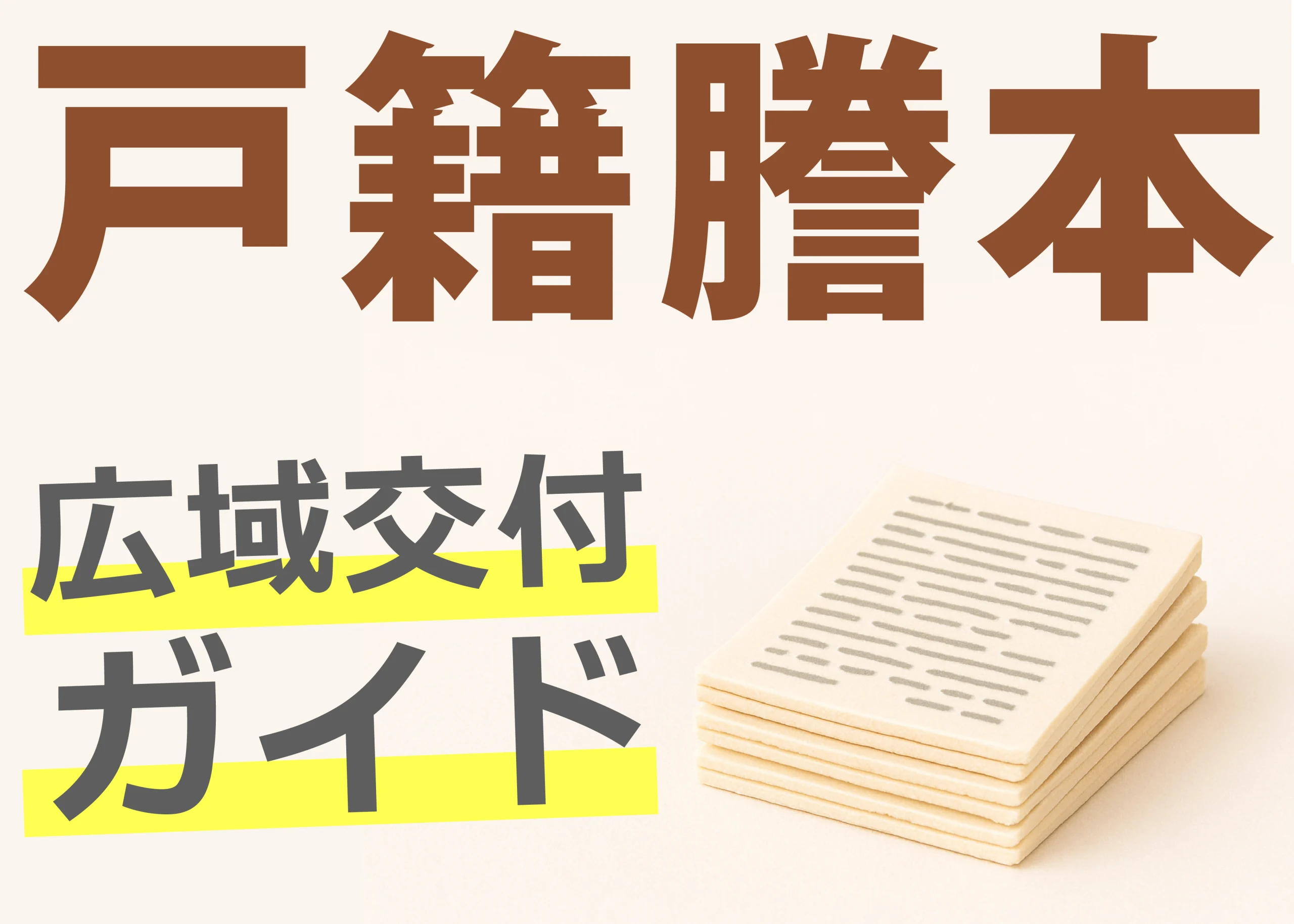
相続人を確定する
戸籍をさかのぼって、誰が法定相続人かを確認します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、関係を整理します。
遺産分割協議を行う
相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を相続するのかを決めます。
内容を文書化した「遺産分割協議書」を作成し、全員の署名押印を行います。
相続登記を申請する
必要書類をそろえて法務局に申請します。
司法書士に依頼すれば、書類作成から申請までを一括で任せることができます。
7. 新しい制度:相続人申告登記
【相続人申告登記】
「3年以内に手続きが間に合わない」「遺産分割がまとまらない」という場合には、
相続人申告登記という制度が利用できます。
これは、自分が相続人であることを法務局に申告しておくことで、
登記義務を果たしたとみなされる仕組みです。
この申告をしておけば過料の対象外となり、
後から正式な名義変更を行うことができます。
時間を稼ぎながら法的な義務を果たせる救済制度といえます。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 義務化前に親が亡くなった場合も対象ですか?
はい。2024年4月より前の相続も対象になります。
ただし、2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。
Q2. 登記をしないまま次の相続が起こるとどうなりますか?
相続関係が複雑化し、登記に必要な書類や人数が倍増します。
結果的に手続きが難航し、費用も増えてしまいます。
Q3. 登記費用はいくらかかりますか?
登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%です。
司法書士に依頼する場合は、別途報酬が必要になります。
9. がもう相続相談センターのサポート
がもう相続相談センターでは、
相続登記義務化に対応した無料相談を実施しています。
・名義確認のサポート
・相続人の特定と戸籍取得代行
・遺産分割協議書の作成支援
・司法書士による登記手続きの代行
登記を後回しにしていると、いずれ法的な負担が発生します。
「自分の家も対象かわからない」という段階でもかまいません。
早めに相談し、今のうちに状況を整理しておきましょう。

10. まとめ
相続登記義務化は、これからの相続だけでなく過去の相続にも適用されます。
・2024年4月1日以降の相続は、3年以内に登記が必要
・2024年3月31日以前の相続は、2027年3月31日までに登記が必要
期限を過ぎると過料の対象になる可能性があり、
将来的には売却や相続が難しくなるリスクもあります。
放置している土地や建物がある場合は、
まず登記簿の名義を確認し、専門家に相談してみましょう。
名義を整えることが、家族を守る最初の一歩です。

