
「兄弟のひとりが何年も音信不通で、相続の話し合いができない」
「相続人が全員そろわないとダメと聞いたけど、どうすればいいの?」
──こうしたお悩みは、実はとても多いです。
相続では、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)という話し合いで、
誰がどの財産を相続するかを全員で決める必要があります。
では、相続人に行方不明者がいる場合、
どんな手続きをとれば相続を進められるのでしょうか?

1. 相続人が行方不明だと、なぜ相続手続きができないのか
遺産分割協議で作成する合意書には、全員の署名と実印、印鑑証明書が求められます。
行方不明の相続人が1人でもいると、印鑑がそろわず、
手続きが「完全にストップ」してしまいます。
2. 相続人が行方不明のときの基本的な対応手順
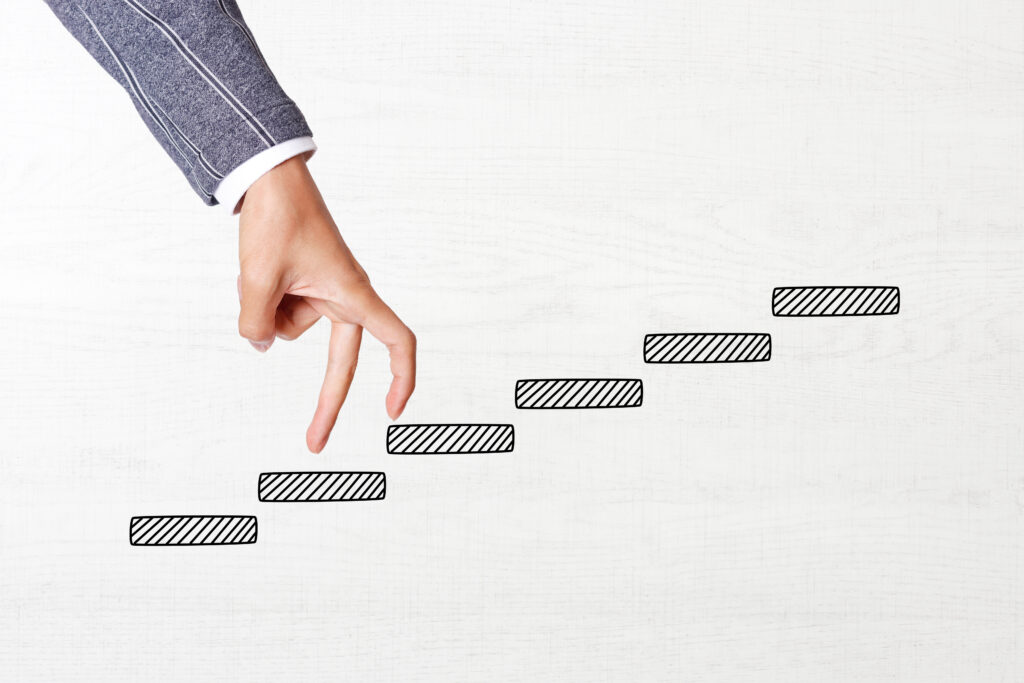
行方不明の相続人がいる場合、すぐに裁判や難しい手続きに進むわけではありません。
まずは「どこまで本人を探したか」という過程を踏むことが大切です。
ここでは、現実的な手順を3ステップで整理します。
【ステップ①】行方不明者を探す(所在確認の努力)
最初にすべきことは、「本当に行方不明なのか」を確認することです。
- 戸籍附票を取り寄せ、最後に住んでいた住所を確認する
- 市役所で住民票の除票や転出先を調べる
- 電話・手紙・SNSなどで連絡を試みる
- 親族・知人・勤務先などに情報を聞く
この段階で見つかるケースも少なくありません。
もし所在が判明した場合は、通常の遺産分割協議に戻ります。
【ステップ②】不在者財産管理人の選任を申し立てる
どうしても連絡がつかない場合、次にとるのが
「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」の選任です。
これは家庭裁判所に申し立てを行い、
行方不明者に代わって財産を管理・処分できる人を選ぶ制度です。
申し立てできる人は、
・他の相続人
・利害関係人(不動産共有者など)
です。
不在者財産管理人の主な役割
- 不在者の財産を保全する
- 相続に関する手続きを代わりに行う(裁判所の許可が必要)
この手続きを経れば、行方不明者の同意が得られない状態でも、
裁判所の判断のもとで相続を進められるようになります。
【ステップ③】家庭裁判所の許可を得て遺産分割を実施
不在者財産管理人が選任された後、
その管理人が家庭裁判所に「遺産分割協議を行う許可」を申請します。
裁判所が「相当である」と認めれば、
行方不明者の代理として協議を進めることが可能です。
その際、管理人は行方不明者の利益を守る立場として、
不利な内容では合意できません。
公平な内容であることが求められます。
協議が整えば、遺産分割協議書を作成し、
その署名欄には「不在者財産管理人 ○○(氏名)」として記載されます。
3. 長期間行方不明の場合は「失踪宣告」で解決する方法も
行方不明が長期にわたる場合、
より根本的な解決策として「失踪宣告」を申し立てる方法があります。
これは、家庭裁判所が「死亡したものとみなす」判断をする制度です。
【失踪宣告が認められる条件】
- 普通失踪:7年間行方不明の場合
- 特別失踪:災害や事故など危険な状況で1年以上消息不明の場合
失踪宣告が確定すると、その行方不明者は法律上“死亡した”扱いとなり、
相続人ではなくなります。
その結果、残された家族だけで遺産分割を進めることができます。
ただし、万が一後から本人が生存していたことが分かった場合は、
財産の返還義務が発生する点には注意が必要です。
4. 不在者財産管理人と失踪宣告、どちらを選ぶべき?

どちらも家庭裁判所に申し立てる手続きですが、
目的と使いどころが違います。
| 比較項目 | 不在者財産管理人 | 失踪宣告 |
| 対応できる期間 | 行方不明から短期〜中期 | 7年以上または特別失踪1年以上 |
| 効果 | 行方不明者の代理人が手続きを行う | 法的に死亡とみなされる |
| 手続きの速さ | 数ヶ月で可能 | 最短でも半年〜1年程度 |
| 戻ってきた場合 | 管理人解任で終了 | 失踪宣告は取り消し可能だが複雑 |
| 主なメリット | 早期に遺産分割が進められる | 法的に相続人から除外できる |
つまり、「すぐに手続きを進めたい場合」は不在者財産管理人、
「長年行方不明で戻る見込みがない場合」は失踪宣告が適しています。
5. 行方不明の相続人がいるときにやってはいけないこと
焦って次のような行動を取ると、後でトラブルになります。
- 行方不明者を無視して勝手に遺産分割協議書を作る
- 署名欄を代筆する、印鑑を代わりに押す
- 「もういないものとして」登記や解約を進める
これらは無効行為となり、
のちに行方不明者が現れた場合に、全てやり直しになる可能性があります。
正しい手続きを踏んでおくことが、トラブルを防ぐ唯一の方法です。
6. 手続きをスムーズに進めるための専門家の活用
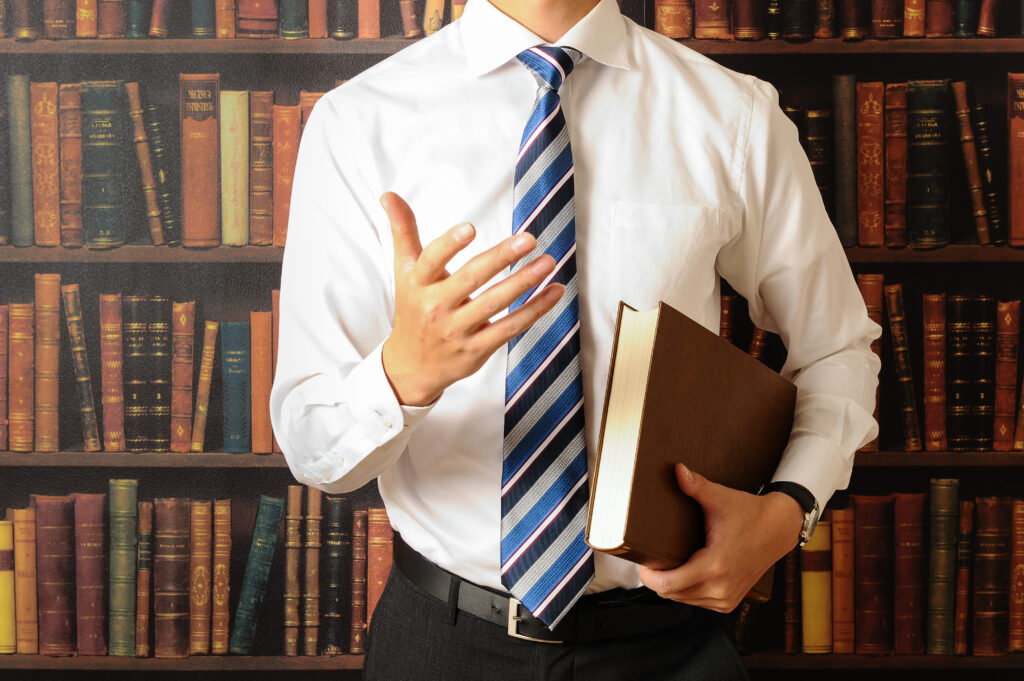
行方不明者がいる相続は、通常よりも複雑です。
家庭裁判所に提出する書類や添付資料も多く、一般の方が一人で進めるのは難しいのが現実です。
司法書士・弁護士に依頼することで、
- 戸籍の収集や相続人調査
- 家庭裁判所への申立書作成
- 管理人選任後の書類作成や登記対応
などを代行してもらえます。
特に、相続登記 (不動産の名義変更) を最終目的とする場合は、
司法書士が中心となり、弁護士・税理士と連携して進めるのが一般的です。
7. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、
司法書士を中心に、家庭裁判所への申し立て手続きや書類作成をサポートしています。
- 行方不明者がいる相続の全体整理
- 不在者財産管理人の申立て代行
- 失踪宣告の申立て支援
- その後の相続登記まで一括対応
相談は何度でも無料。
「行方不明者がいるからもう相続できない」と思わず、
まずはご相談ください。
8. よくある質問
Q1. 不在者財産管理人の選任にはどれくらい時間がかかりますか?
申し立てからおおむね1〜3か月程度で選任されることが多いです。
ただし、裁判所の混雑状況や、行方不明者を探すための証拠提出(戸籍附票・通知の記録など)が不十分な場合は、時間が延びることもあります。
専門家が書類を整えることで、スムーズに進むケースがほとんどです。
Q2. 弁護士と司法書士、どちらに相談すればいいですか?
どちらにも役割があります。
・司法書士:登記や戸籍の整理、申立書の作成など手続き面のサポート
・弁護士:行方不明者との利害対立や争いの可能性がある場合
相続の全体像を整理したい場合は、ワンストップ対応の窓口で相談するのが効率的です。
9. まとめ
相続人に行方不明者がいる場合でも、
正しい手順を踏めば相続を進めることは可能です。
- まずは本人を探す(所在確認)
- 見つからない場合は「不在者財産管理人」を選任
- 長期不明なら「失踪宣告」を検討
- 勝手な手続きはNG、専門家に相談を
行方不明の相続人を抱えたまま放置すると、
不動産登記や遺産分割が何年も止まってしまいます。
早めに正しい方法で動くことが、家族全員にとって最善の選択です。
弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。
ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

