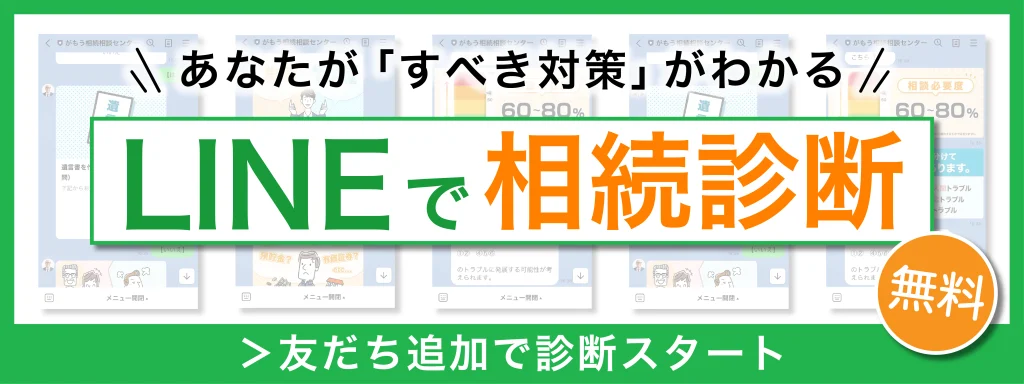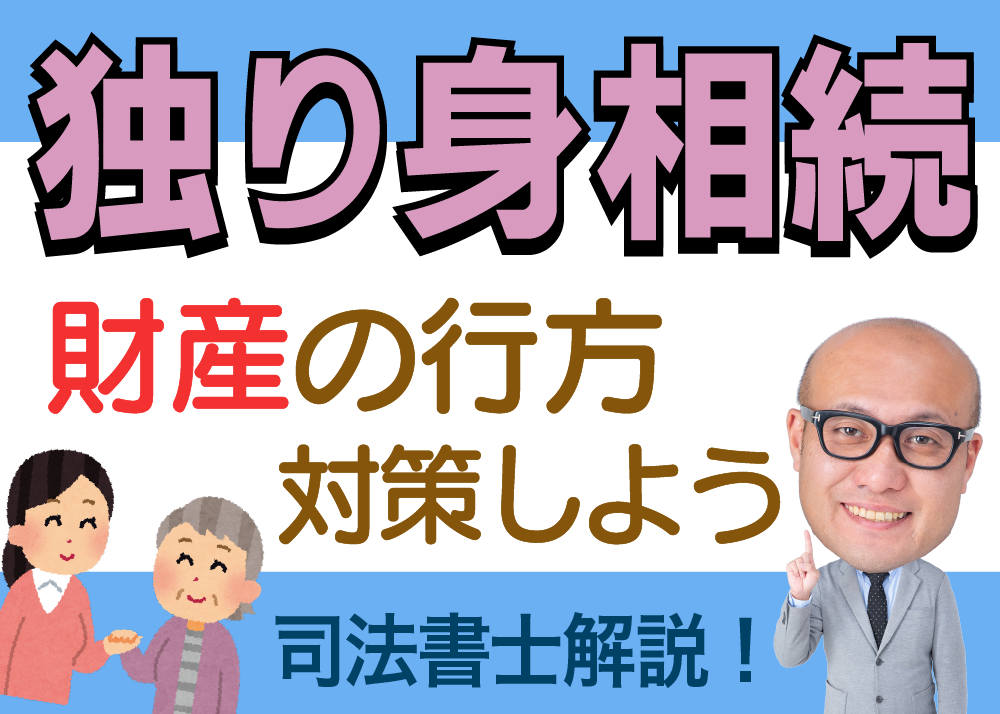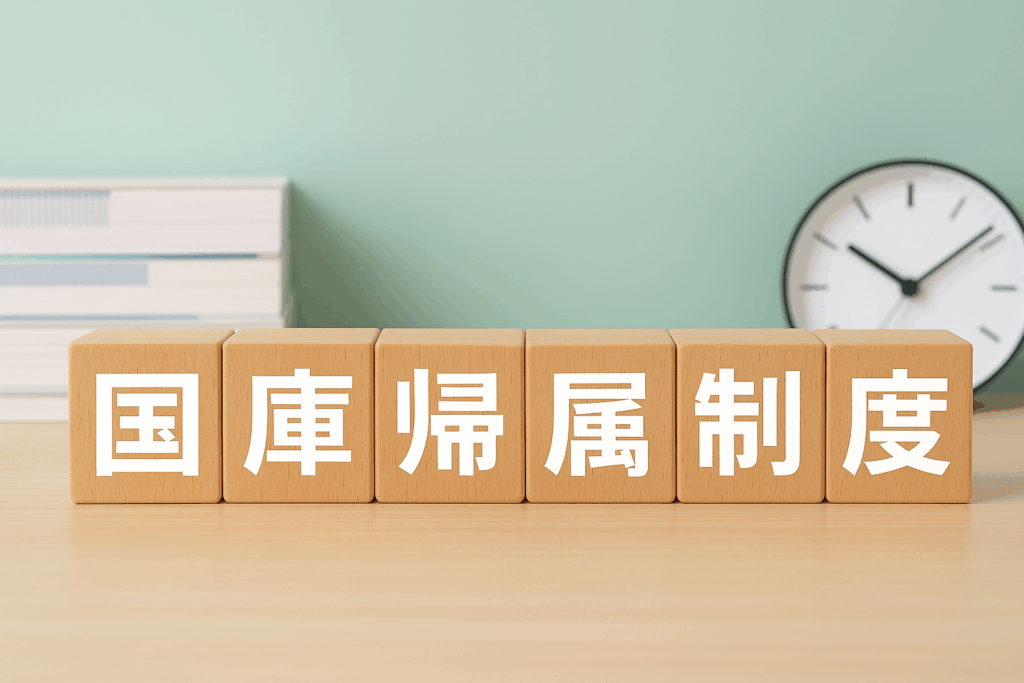
「自分には相続人がいないけれど、亡くなった後の財産はどうなるのか…」と不安に思う方は少なくありません。
独身の方、子どもがいない方、兄弟姉妹がすでに亡くなっている方などは「相続人がいない場合」に当てはまります。
放置されることはなく、財産は必ず法律に従って整理されます。ただし、準備をしていないと「望まない形で国に渡ってしまった」と後悔することもあります。
ここでは、相続人がいない場合の流れと国庫帰属の仕組み、そしてよくある疑問や備え方を、わかりやすく解説します。
こちらもあわせて読まれています。
1.相続人がいない場合の流れ

相続人がいない方が亡くなった場合、家庭裁判所が「財産を清算する人」を決めます(この人を相続財産管理人と呼びます)。
この管理人が、銀行口座や不動産を整理し、借金があれば支払いを行います。その後、公告(新聞や官報などで広く知らせること)を行い、「本当に相続人がいないか」を一定期間確認します。
誰も名乗り出なければ「相続人がいない」と確定し、次のステップに進みます。
家庭裁判所が管理人を選任
2.相続人がいない場合に財産は誰がもらう?
多くの人が気になるのは「相続人がいないと、財産は誰のものになるのか」という点です。
流れは次のようになります。
- 家庭裁判所が相続財産管理人を決める
- 縁故者(特別に関わりのあった人)が申し立てれば、認められる場合がある
- 誰もいなければ財産は国庫に帰属
3.相続人がいない場合の不動産はどうなる?
不動産がある場合も同じ流れです。
- 管理人が名義や処分を担当する
- 縁故者が認められれば、裁判所の判断でその人に渡る場合がある
- 誰もいなければ売却され、売却代金が国庫に帰属
不動産が放置されて空き家になると、様々な問題を引き起こします。
不動産は管理責任が重いため、事前の対策がとても大切です。
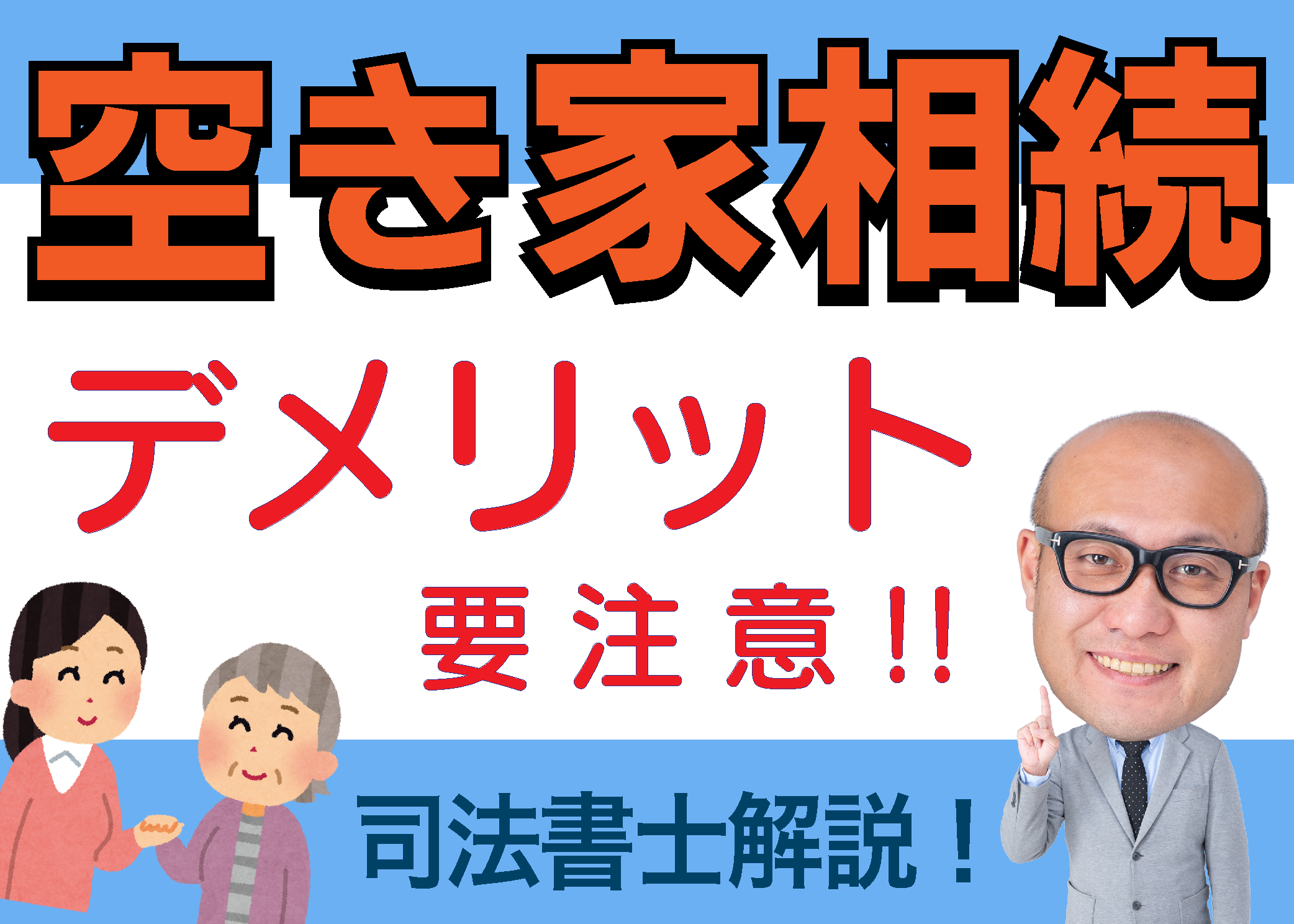
4.具体的な事例
縁故者が認められた事例
東京で独身男性が亡くなり、相続人がいませんでした。
長年同居していた女性(血縁関係なし)が「生活費を半分以上負担していた」「介護記録や同居証明がある」として家庭裁判所に申し立てました。
証拠が十分だったため、男性の預金の半分がその女性に分与されました。
縁故者が認められなかった事例
別のケースでは、亡くなった男性の友人が「昔から付き合いがあった」と主張しましたが、同居実績や介護の記録はありませんでした。
裁判所は「一時的な交際や友人関係は特別縁故には当たらない」と判断し、申し立ては却下。最終的に財産は国庫に帰属しました。
→ この違いから分かるように、「縁故者として認められるには継続的で密接な生活関係の証拠が不可欠」です。
5.相続人がいない場合に残った財産は国庫に帰属する
縁故者がいない場合や、分配しても残った財産はすべて国に渡ります。
実際には毎年1000億円以上が「相続人がいない財産」として国庫に帰属しています。
「自分が築いた財産を国に渡したくない」と考えるなら、遺言書で意思を残すことが欠かせません。
6.相続人がいない場合のよくある疑問(Q&A)

Q1.相続人がいない場合、借金はどうなる?
→ 財産と同じく清算されます。返済できない部分は消滅するため、親族に借金が引き継がれることはありません。
Q2.相続人がいない場合、ペットはどうなる?
→ 法律上ペットは「物」とされるため、管理人が引き取り先を探すことになります。事前に遺言や信託で託す方法を考えておくのがおすすめです。
Q3.相続人がいない場合の銀行口座は?
→ 口座は凍結され、管理人が清算します。放置すると使えないままになります。
7.後悔しないための準備
- 遺言を作る
信頼できる人や団体に遺贈して意思を残すことができます。
>遺言書の入門はコチラ! - 不要な土地は国に引き渡す制度を検討する
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、条件を満たす土地を国に引き渡せます。 - 身近な人への感謝を形にする
介護や支援を受けた人に残したい場合は、遺言に明記しておきましょう。
まとめ
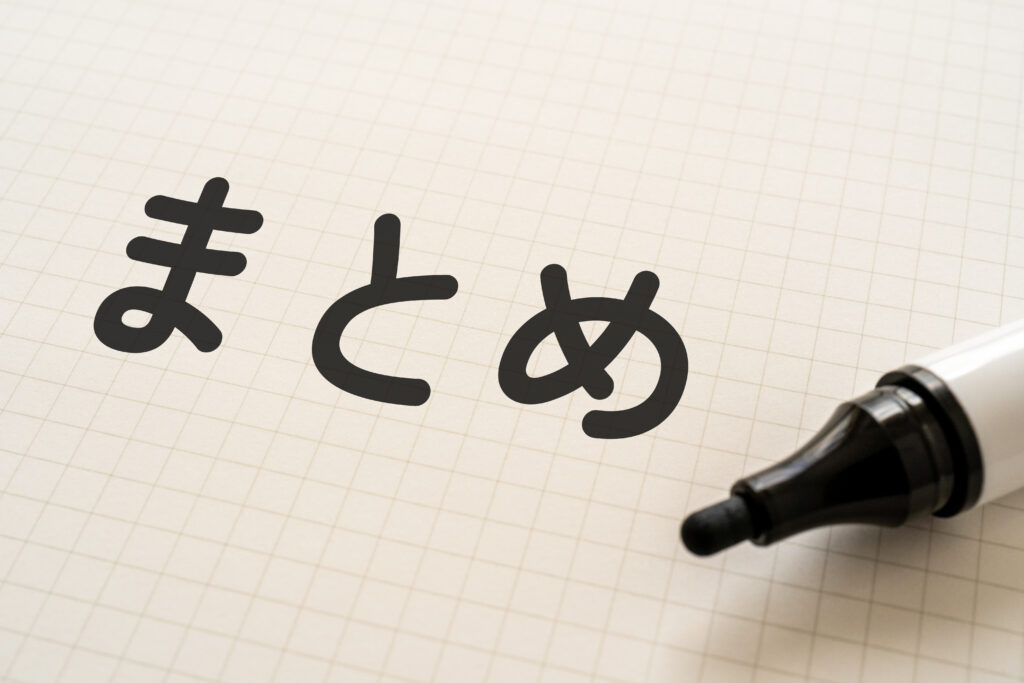
相続人がいない場合、財産は以下の流れで処理されます。
- 裁判所が管理人を選任
- 公告で相続人や縁故者を確認
- 縁故者に渡る場合がある
- 誰もいなければ国庫に帰属
不動産やペット、借金なども含め、放置されることはありません。
大切なのは「自分の意思を残しておくこと」です。遺言を準備し、縁故者や財産の扱いを事前に整理することで、亡くなった後も自分らしい形で財産を活かせます。
さらに詳しく対策方法を知りたい方は、ぜひ弊社の無料相談にお申し込みください!
あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。
\ この機会に是非ご登録ください! /