
親が亡くなり、いざ遺産を分ける段階になったとき、

相続人が多くて、話がまとまらない

誰がどれだけもらえるのか決まらない
そんな悩みに直面する方は少なくありません。
兄弟姉妹が多い家庭や、再婚家庭など家族関係が複雑なケースでは、遺産分割が思うように進まず、
親族間の関係が悪化してしまうこともあります。
・どうすれば揉めずに進められるのか?
・どんな順序で話し合えばいいのか?
ここでは、相続人が多い場合の遺産分割で起こりやすいトラブルと、
それを防ぐための具体的な進め方を紹介します。
1. 相続人が多いときに起こりやすいトラブル

相続人が多くなると、単純に話し合う人数が増えるだけでなく、
「考え方」「生活環境」「経済状況」「感情」の違いが表面化しやすくなります。
● 意見が合わず話が進まない
相続人が5人、6人と増えるほど、全員の意見を一致させるのが難しくなります。
「長男が実家を継ぎたい」
「次男は現金でほしい」
「長女は平等に分けたい」など、
価値観がぶつかる場面が増えるものです。
遺産分割協議は全員の合意が必要です。
一人でも反対すれば協議は成立せず、預金も不動産も動かせません。
● 代表者まかせで後から不満が出る
「兄が代表で話を進めてくれたから任せていた」という場合、
後になって「そんな内容聞いていない!」と揉めるケースもあります。
相続は“全員の意思確認”が前提。
手続き中に意見の食い違いが発覚し、相続が停滞してしまうこともあります。
● 感情のもつれによる長期化
相続の話し合いでは、お金の問題よりも感情の問題が大きく影響します。
「昔から親の面倒を見てきたのは自分だ」
「あの人は何もしてこなかった」など、
過去のわだかまりが再燃することも多いものです。
一度こじれると、法律よりも感情が優先され、解決まで数年かかるケースも珍しくありません。
2. 揉めないための第一歩|情報をそろえてスタートする
相続人が多い場合ほど、“話し合いの土台となる情報”をそろえることが重要です。
最初にやるべきは、「誰が相続人なのか」「財産は何があるのか」を正確に把握することです。
● 相続人を確定する
まずは亡くなった方(被相続人)の戸籍を出生から死亡まですべて集めます。
これによって、法的に相続権を持つ人全員を確定できます。
たとえば、再婚して前妻との間に子がいる場合、その子も相続人になります。
「知らなかった相続人」が後から現れると、すでに決めた内容が無効になるおそれがあります。
● 財産の全体像をつかむ
次に、遺産の全体像を明らかにします。
- 預貯金・株式・投資信託
- 不動産(土地・建物)
- 生命保険・死亡退職金
- 借入金やローンなどの負債
どの財産がどこにあり、どれくらいの価値があるのかを全員が共有できるように整理しましょう。
この段階をあいまいにすると、後で「そんな財産があったのか」と疑心暗鬼を生みます。
3. トラブルを防ぐ3つの話し合いのコツ

1. 「感情」と「数字」を分けて話す
相続の話し合いでは、感情と数字を混同するとまとまりません。
「親の面倒を見たから多くもらいたい」といった気持ちは理解できますが、
それは“寄与分”という法的な仕組みで整理すべきことです。
まずは冷静に財産の総額と相続分を共有し、
「気持ちの部分はあとで別に考えよう」と線引きするのが大切です。
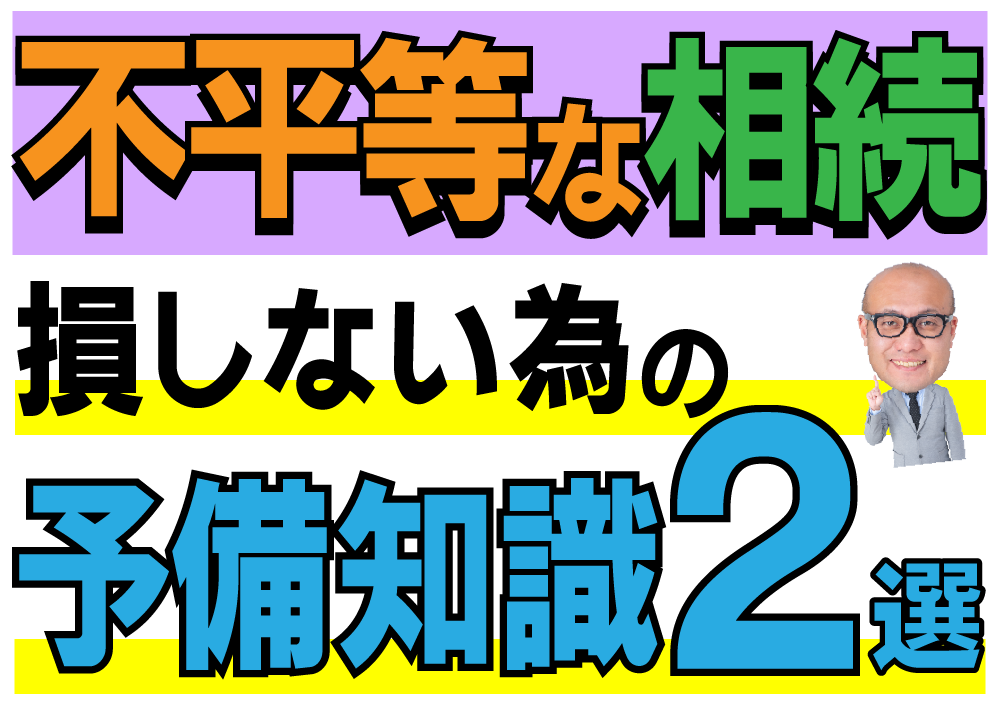
2. 書面に残す
口約束では、後になって言った・言わないの争いになります。
話し合いの内容はメモでも構いませんので、必ず記録を残しましょう。
また、最終的に決まった内容は「遺産分割協議書」にまとめ、
全員が署名・押印しておくこと。これが後日の証明になります。
3. 期限を意識して動く
相続税の申告期限は10か月以内です。
遺産分割が決まらないと、財産の評価もできず、税金の申告も遅れてしまいます。
長期化しそうな場合は、一旦「仮分割」や「法定相続分での申告」をしておき、
後から正式に分け直す方法も検討しましょう。
4. 揉めないための実践策|おすすめの進め方5選

1. 代表者を決めて情報を集約する
人数が多いほど、全員が自由に発言すると話が脱線します。
まずは兄弟姉妹の中から信頼できる1人を“代表”として決め、
窓口や専門家との連絡を一元化するのがおすすめです。
ただし代表者に任せきりにせず、定期的に共有すること。
情報が偏ると「知らされていない」と不信感を生みます。
2. 話し合いは「全員で一度に」ではなく「段階的」に
相続人が多い場合、初回から全員で集まると混乱しやすいです。
最初は代表者+専門家で大枠を整理し、次に全員へ説明する形のほうがスムーズ。
ポイントは、“全員が同じ資料を見る”こと。
一部の人だけが情報を持っている状態は、必ずトラブルになります。
3. 不動産は「分け方」を慎重に
遺産の中で最も揉めやすいのが不動産です。
売却して現金化するのか、誰かが引き継ぐのか──。
不動産を共有名義にすると、将来の売却や登記で手続きが煩雑になります。
できる限り単独名義にまとめるか、売却して分配するのが安全です。
もし「親の家を誰かが住み続けたい」という希望があるなら、
その人が他の相続人に対して代償金を支払う形を検討します。

4. 専門家を“第三者”として立てる
兄弟だけで話しても感情的になりやすいものです。
司法書士や弁護士、税理士などの専門家が間に入ることで、話し合いが冷静になります。
専門家は「相続人のどちらの味方でもない中立の立場」で進行します。
法律的に正しい道筋を示し、書類の整備までサポートしてくれます。
特に相続人が5人以上いる場合は、最初から専門家を交える方が結果的に早く解決します。
5. 遺言書がある場合は内容を慎重に確認
遺言書があっても、相続人全員が納得できるとは限りません。
たとえば「長男にすべて相続させる」と書かれていても、
他の相続人には遺留分(法律で保証された取り分)があります。
遺言書が法的に有効かどうか、内容に問題がないかは、
家庭裁判所の「検認」や専門家の確認を経てから進めることが重要です。
5. よくある質問と注意点
Q1. 相続人が多いときは、必ず全員の署名が必要ですか?
はい。遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印が必要です。
1人でも欠けると無効になります。印鑑証明書も必ず添付しましょう。
Q2. 代表者だけで手続きを進めてもいいですか?
財産の調査や専門家への相談など、“準備段階”なら代表者でも構いません。
ただし分割の決定や署名・押印は、全員の合意が前提です。
Q3. 連絡が取れない相続人がいる場合は?
連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議は進みません。
この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。
ただし時間がかかるため、早めの対応が必要です。
Q4. 話し合いが完全に行き詰まったら?
家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用します。
調停委員が間に入り、中立の立場で話し合いを進めます。
合意に至れば「調停調書」が作成され、法的効力を持ちます。
6. まとめ|人数が多い相続ほど「準備」と「冷静さ」が鍵
相続人が多いときの遺産分割では、
- 意見の食い違い
- 感情のもつれ
- 情報の偏り
この3つが大きなリスクになります。
解決のコツは、
- 全員の情報を共有し、
- 感情と数字を分けて考え、
- 専門家の力を借りること。
法律的な正解だけでなく、家族の関係を壊さずに進めることが何より大切です。
一人で抱え込まず、司法書士や弁護士などの専門家に早めに相談することで、
円満な解決への道が開けます。
相続は「争族」とも言われるように、話し合い方ひとつで家族の未来が変わります。
冷静な準備と第三者のサポートを取り入れて、“揉めない遺産分割”を実現しましょう。
がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、
名義預金や贈与の整理をはじめ、相続税のリスクを未然に防ぐサポートを行っています。
- 名義預金の有無を確認する口座整理サポート
- 贈与契約書の作成・税理士との連携支援
- 相続税の試算と申告サポート
- 相続開始後の税務調査対応アドバイス
弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。
ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

