
親が亡くなり、実家を相続した。
けれど誰も住む予定がない──。
そんな「空き家の相続」は、いま日本中で増えています。
相続した直後は、悲しみや整理の忙しさで後回しになりがちですが、放置すると税金・管理・売却のどれもが複雑になっていきます。
ここでは、空き家を相続したあとにやるべき手続きや判断の流れを、できるだけわかりやすく整理しました。
固定資産税の扱い、活用の選択肢、売却の注意点まで、今のうちに全体像をつかんでおきましょう。
※空き家を持つことのデメリットやリスクを詳しく知りたい方は、別記事「空き家所有のデメリット大全。固定資産税・火災保険・リスク一覧」もあわせてご覧ください。

1. まず確認すべきは「名義」と「登記」

空き家を相続したとき、最初に行うべきは名義の確認と登記手続きです。
1-1 不動産の名義は自動で変わらない
相続が発生しても、登記簿上の名義は自動で書き換わりません。
たとえば「父名義のまま」という状態では、売却も解体も、誰も正式に決定できません。
2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まり、相続を知ってから3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料の対象になります。
つまり「とりあえず放置」では済まない時代になったということです。
1-2 相続人が複数いる場合の注意点
兄弟姉妹など相続人が複数いる場合、まずは誰がその空き家を引き継ぐのかを決めなければなりません。
共有名義のまま放置してしまうと、後の売却や管理で話がまとまらず、手続きが長期化する原因になります。
話し合い(遺産分割協議)を行い、全員が署名押印した「遺産分割協議書」を作成しておくことが基本です。
これがあって初めて、法務局で登記ができます。
【オススメ】
相続登記についての詳細は下記ブログ記事がオススメです。
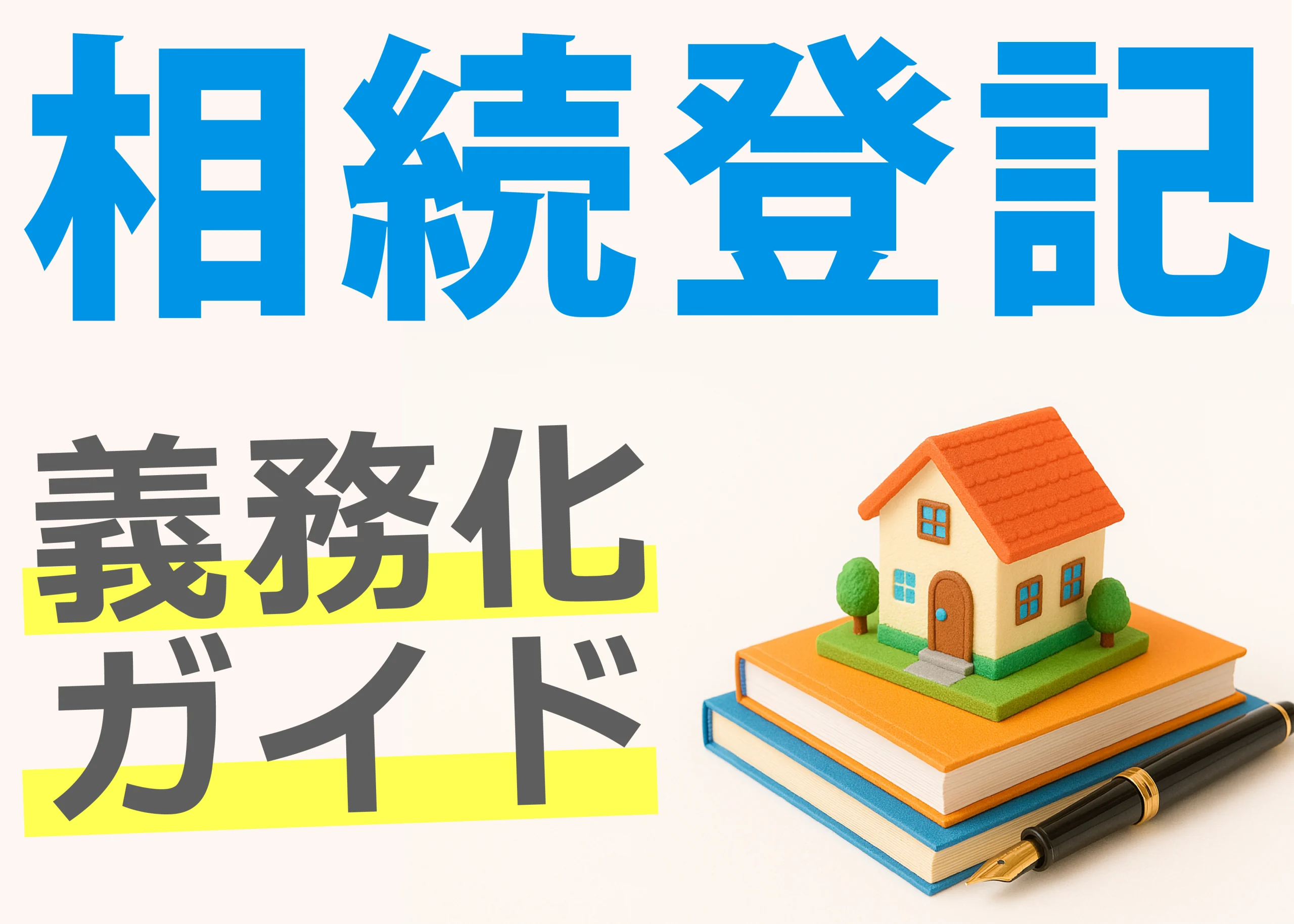
2. 固定資産税の負担を見逃さない

空き家を相続した瞬間から、固定資産税の支払い義務もあなたに移ります。
2-1 税金の通知書は翌年に届く
たとえば2025年3月に親が亡くなった場合でも、2025年度分の納税通知書は5月ごろ、被相続人(亡くなった親)あてに届きます。
この時点ではまだ名義変更が済んでいないため、相続人が代表して支払う必要があります。
「亡くなった親名義だから」と放置すると、延滞金が発生することがあります。
2-2 「住宅用地の特例」が外れないように注意
人が住まなくなった家は、長期間放置すると「管理不全空家等」や「特定空家等」に指定される場合があります。
そうなると、住宅用地に適用されていた固定資産税の軽減措置が外れるおそれがあります。
結果として税額が最大6倍になるケースもあるため、雑草の除去や建物の点検など「最低限の管理」を続けることが大切です。
2-3 解体した場合は税金が上がることも
「古い家だから壊して更地にすればいい」と考える人も多いですが、建物を解体すると住宅用地特例の対象外になります。
つまり、建物を残している方が税額が安い場合もあるということです。
税金だけで判断せず、売却予定や土地活用の計画も含めて考えるようにしましょう。
3. 管理と維持をどうするか決める
空き家をそのままにしておくと、建物はあっという間に劣化します。
湿気やカビ、害虫、雨漏りが進むと、将来の売却価格にも影響します。
3-1 最低限の管理を継続する
人が住まない家でも、次のような管理を続けることが理想です。
- 2〜3か月に一度は通風・通水を行う
- 雑草や庭木を定期的に整える
- 郵便物を処分し、外観を清潔に保つ
- 雨漏りや破損を点検し、必要なら修理する
遠方に住んでいて通えない場合は、空き家管理サービスを利用する方法もあります。
3-2 火災保険の見直しを忘れずに
相続した家が「空き家」になったときは、火災保険をそのままにしてはいけません。
人が住まない建物は「住宅用」として契約できない場合があり、空き家専用の保険への切り替えが必要です。
また、親名義のままの保険契約では補償を受けられないため、相続人名義への変更も必須です。
火災・風災・水害に備えるうえで、加入条件を一度確認しましょう。
4. 活用方法を検討する
空き家を持ち続けるなら、「どう活かすか」を決めておくことが重要です。
放置ではなく、運用する方向へ動くことで負担を軽くできます。
4-1 賃貸・シェアハウスとして活用する
リフォーム費用がかかりますが、貸家として賃料収入を得る方法があります。
近年は「リノベーションして貸す」ほか、「シェアハウス」「民泊」などの形で活用する例も増えています。
ただし、老朽化が進んでいる場合や耐震基準を満たさない場合は、改修に多額の費用が必要です。
空き家の状態を建築士などに調べてもらい、採算が取れるかを判断しましょう。
4-2 駐車場や資材置き場に転用する
建物を取り壊し、土地を月極駐車場や資材置き場として使う方法もあります。
固定資産税は上がる場合がありますが、安定した収入が得られ、管理も比較的簡単です。
ただし、土地の形状や立地によっては収益化が難しいケースもあります。
事業者に相談し、収支シミュレーションを立ててから決断しましょう。
4-3 地域貢献型の活用も
近年は、自治体やNPOと連携して「子ども食堂」「地域サロン」「学童保育」などに空き家を提供する動きも増えています。
直接の収益はなくても、地域貢献として評価されるケースや、解体補助金を受けられる自治体もあります。
5. 売却を検討する場合のポイント
空き家を維持するのが難しい場合、売却は現実的な選択肢です。
ただし、「古い家」「共有名義」「相続未登記」などの事情によって、手続きは複雑になります。
5-1 相続登記が完了していないと売れない
売却には、登記名義があなたになっていることが前提です。
まだ親名義のままなら、まず相続登記を済ませなければなりません。
登記をしないまま不動産会社へ相談しても、正式な契約はできません。
5-2 共有名義はトラブルのもと
兄弟姉妹との共有状態では、売却にも全員の同意が必要です。
一人でも反対すると、契約が進められません。また、誰かが亡くなればその人の相続人が加わり、さらに権利関係が複雑になります。
早めに「誰が所有するか」を決めて単独名義にしておくことが、のちのトラブル回避につながります。
5-3 「相続空き家の3,000万円特別控除」を確認
相続した家を売却する場合、一定の条件を満たせば最大3,000万円の譲渡所得控除が受けられます。
これは、被相続人が亡くなる直前まで居住していた家を、相続開始から3年10か月以内に売却した場合などに適用されます。
対象になるかどうかは、
- 被相続人が一人暮らしだった
- 空き家を更地にして売る、または耐震改修をして売る
といった条件で決まります。
税務署や税理士に確認しておくと安心です。
6. まとめ:空き家を「負債」にしないために
空き家の相続は、単に家を引き継ぐだけではありません。
固定資産税、火災保険、管理、活用、売却──すべての判断に「タイミング」と「行動」が必要です。
放置すれば税金が上がり、家は傷み、売りにくくなります。
一方で、早めに登記と管理を整え、活用や売却の方向性を決めておけば、無駄な負担を最小限にできます。
相続した空き家をどうするか迷っている方は、まず「登記」「税金」「管理」の3つを最優先に確認してください。
それだけで、後の選択肢がぐっと広がります。
弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。
ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

