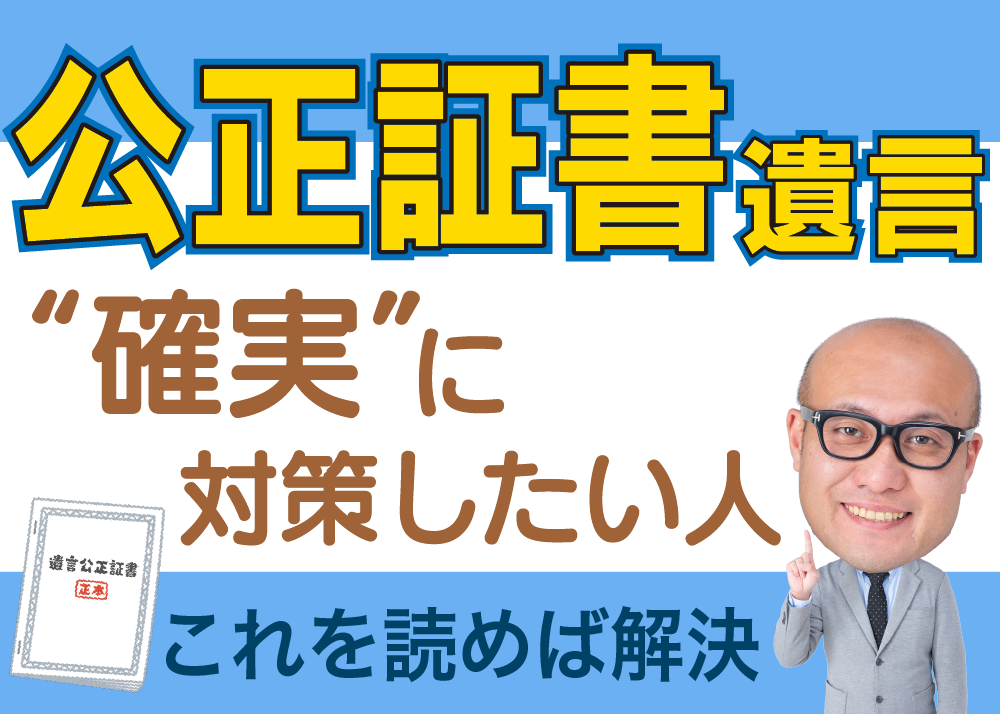せっかく書いた遺言書、「無効」にならない自信はありますか?
「自分の財産は、きちんと家族に託したい」
そう考えて遺言書を用意する人は年々増えています。
しかし実は、せっかく作成した遺言書が“無効”になるケースが少なくありません。
文字の書き方や日付の記載ミス、封印の不備など、
ほんの小さなミスでも「法的に認められない」と判断されることがあります。
こうしたトラブルを防ぐために2020年から始まったのが、
「自筆証書遺言書保管制度」です。
この制度を利用すれば、
「正しく保管」「確実に発見」「改ざん防止」がすべて公的に保証されます。
この記事では、2025年現在も活用できる最新の「遺言書保管制度」の仕組みと、
利用することで得られる5つの安心メリットをわかりやすく解説します。
1. 遺言書保管制度とは?
遺言書保管制度とは、
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で安全に保管してもらえる仕組みのことです。
これまでは、自筆の遺言書を自宅で保管する人が多く、「紛失」「改ざん」「発見されない」といったリスクがありました。
しかしこの制度では、
国(法務局)が正式に遺言書を受け取り、
専用の保管システムで厳重に管理してくれます。
つまり、家庭内トラブルや紛失の心配を一掃できる制度です。
対象となる遺言書は?
対象となるのは、
「本人が自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)」です。
ワープロやパソコンで作ったもの、公正証書遺言は対象外ですが、
財産目録だけはパソコンや印刷物でも認められています。
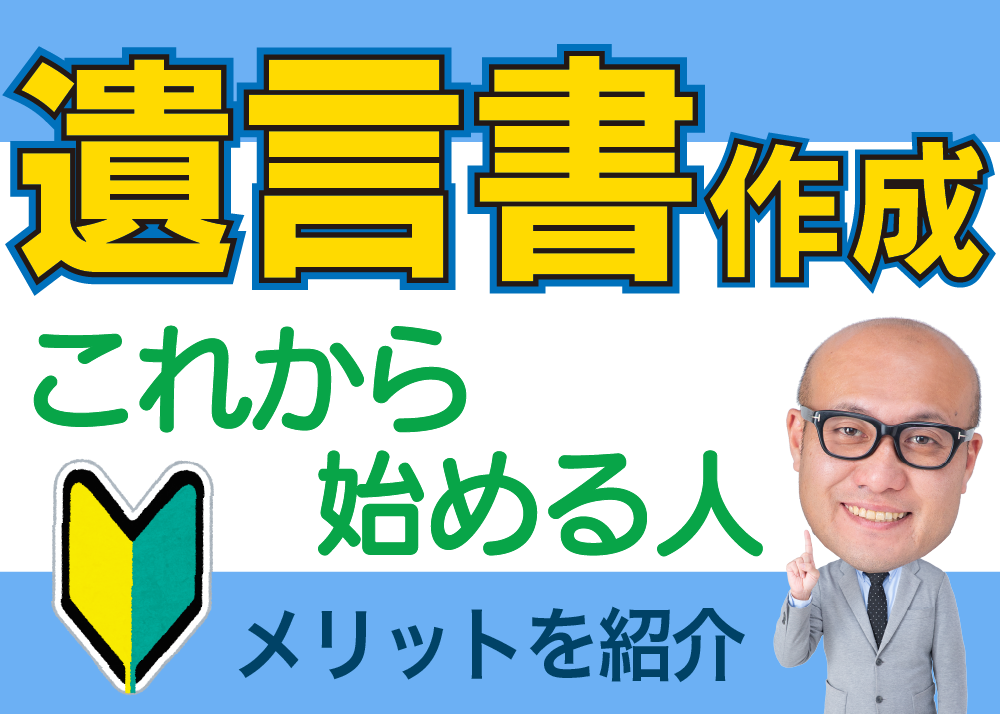
保管できる場所
遺言者の住所地、本籍地、または不動産所在地を管轄する法務局で申請します。
全国どこでも予約制で受け付けており、
事前に電話またはオンラインで手続きを進めることが可能です。
2. 遺言書保管制度を利用する5つのメリット

それでは本題です。
この制度を利用することで、どんな安心が得られるのでしょうか。
① 紛失・改ざんのリスクがゼロになる
自宅で保管していると、
「どこに置いたかわからない」「家族に勝手に開けられた」などのトラブルが起こりがちです。
法務局で保管すれば、
遺言書の原本は厳重な金庫で保管され、本人以外は閲覧不可。
万が一火災や災害が起きても、データとしてもバックアップされています。
つまり、「せっかく書いたのに見つからなかった」という最悪の事態を防げます。
② 家族が“勝手に開封してトラブルになる”心配がない
自宅保管の遺言書は、亡くなった後に家族が勝手に開封してしまうケースが多く、
その場合「家庭裁判所での検認(けんにん)」という手続きが必要になります。
しかし、遺言書保管制度を利用していれば、
裁判所での検認が不要。
法務局に保管された時点で「真正(本物)」が公的に確認されているためです。
そのため、相続手続きをすぐに進めることができ、
家族間の不要な疑念やトラブルを防ぐことができます。
③ 遺言書の存在が確実に見つかる
「親が遺言書を残したかどうかわからない」──
この不安は、相続の現場で非常に多い悩みです。
遺言書保管制度を利用していれば、
亡くなった後、法務局で検索・確認が可能。
全国の法務局ネットワークで一括管理されているため、
別の地域に引っ越しても安心です。
家族は「遺言情報証明書」を取り寄せることで、
確実に遺言の存在を確認できる仕組みになっています。
④ 手数料が安く、誰でも利用しやすい
この制度の利用料は、わずか3,900円(1通あたり)。
公正証書遺言のように数万円かかることはありません。
費用を抑えながらも、「国家機関が預かる安心感」が得られるのが魅力です。
予約して法務局に行けば、
担当官がその場で内容や形式を確認してくれるため、
形式ミスのまま提出されることもほぼありません。
⑤ 家族が相続手続きをスムーズに進められる
遺言書保管制度を利用していると、
亡くなったあと家族が法務局で「保管証明書」を発行してもらうだけで、
すぐに相続手続きに入れます。
つまり、
・検認の時間と費用を省ける
・相続人全員が内容を同時に確認できる
・争いを最小限にできる
というメリットがあります。
「遺言書がある=家族が安心して動ける」という仕組みを、
国の制度として整えたのがこの制度の最大の意義です。
3. 制度を利用するための手続きの流れ

(1)まずは遺言書を作成
遺言書保管制度で預ける前に、
本人の自筆で遺言書を作成します。
手書きで以下を明記しましょう。
• 日付
• 氏名
• 押印
財産の内容や分け方を、できるだけ具体的に書くのがポイントです。
(2)法務局に事前予約
保管申請は予約制です。
法務局のホームページまたは電話で、
「遺言書保管申請をしたい」と伝えましょう。
(3)当日の持ち物
• 遺言書(封筒に入れずそのまま)
• 本人確認書類(運転免許証など)
• 手数料(3,900円)
申請時、職員が形式上の不備をチェックしてくれます。
※内容そのものの確認や助言は行いません。
(4)保管証の発行
手続き完了後、「遺言書保管証」が交付されます。
この書類が、正式に法務局で保管された証明です。
(5)内容の確認・変更も可能
後日、「やっぱり書き直したい」という場合は、
いつでも遺言書を撤回・再提出できます。
※その際は再度手数料がかかります。
4. よくある質問(FAQ)
Q1. 保管制度を使えば、内容に間違いがあっても直してもらえる?
→ いいえ。法務局は形式を確認するだけで、内容のアドバイスは行いません。
内容の妥当性や文面の表現は、司法書士など専門家に相談しましょう。
Q2. 遺言書を預けた後、家族に知られたくない場合は?
→ 家族に通知されることはありません。
遺言者本人が亡くなって初めて、相続人が照会できる仕組みです。
Q3. 公正証書遺言とどちらがいいの?
→ どちらにもメリットがあります。
確実性と法的効力を重視するなら公正証書遺言、
費用と手軽さを重視するなら保管制度がおすすめです。
5. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、
遺言書保管制度を利用したい方のために、
遺言書の作成・文面チェック・法務局申請サポートを一括で行っています。
• 遺言書の書き方アドバイス
• 保管制度の申請同行サービス
• 内容チェック(法的有効性の確認)
• 将来的な遺言更新のサポート
司法書士法人として、法務局制度に精通しているため、
「ミスのない遺言書」「安心できる保管」を実現します。
6. まとめ
遺言書保管制度は、
「自分の思いを確実に残したい」と考える人にとって、
今後の相続準備に欠かせない制度です。
• 紛失・改ざんの心配がない
• 検認不要で家族がスムーズに手続きできる
• 費用が安く誰でも使える
この3点だけでも、大きな安心をもたらします。
さらに、司法書士など専門家のアドバイスを受けながら活用すれば、
「意思を残すだけでなく、家族を守るための遺言」に変わります。
遺言書を作ったまましまい込んでいませんか?
その1枚に「確実な保管」という安心をプラスするだけで、
あなたの想いは、確実に次の世代へつながります。
弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。
ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。