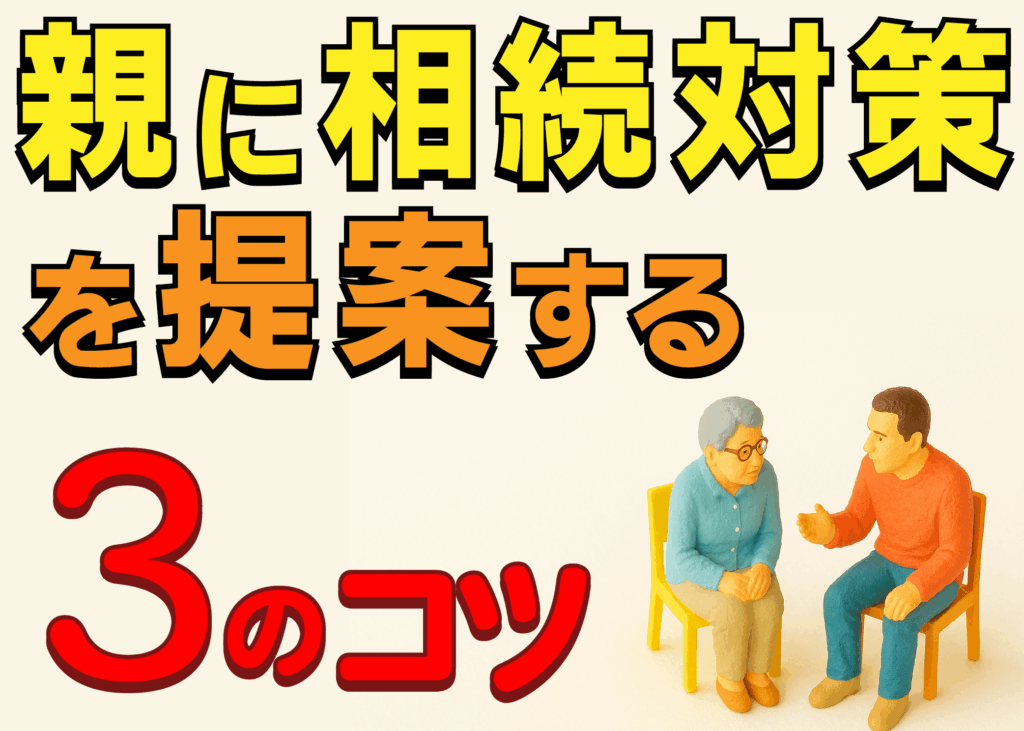
親に「相続の話」をするのは、なぜこんなに難しいのか
「そろそろ相続のことも考えなきゃと思うけど、話を切り出しづらい」
「まだ元気なのに、そんな話をしたら気分を悪くしそう」
──そう感じて、つい先延ばしにしていませんか?
相続の話題は、どうしても“死”を連想させてしまうため、
親にとっても、子にとっても気まずいテーマです。
しかし、相続の準備は“亡くなってから”ではもう間に合わないのが現実です。
遺言書の作成や財産の整理、生前贈与の判断などは、
親が判断力のあるうちにしか進められません。
この記事では、
「高齢の親に相続の話を切り出すベストなタイミング」と、
「親を傷つけず、前向きに話を進めるコツ」
を、やさしい言葉で解説します。
1. なぜ“今”が相続の話をするタイミングなのか

多くの家庭では、親の健康状態や年齢をきっかけに
「そろそろ考えた方がいいかも」と意識し始めます。
ただ、実際に話を始めるきっかけが見つからないまま、
時間だけが過ぎてしまうケースが非常に多いです。
判断力があるうちでないと、法的な手続きができない
相続の準備とは、遺言書・生前贈与・財産整理などのことです。
これらは、本人(親)が自分の意思で判断できるうちにしかできません。
たとえば、認知症が進んでからでは、
「遺言書が無効になる」「贈与契約ができない」
といった問題が起こります。
そのため、
「まだ元気だから大丈夫」と思える“今この瞬間”こそ、
最も良いタイミングなのです。
話を先送りすると、家族の関係が悪化するリスクも
相続の話を避けたまま親が亡くなると、
残された家族が初めて財産や遺言を知ることになります。
すると──
「どうして自分だけ知らされてなかったの?」
「生前に話しておいてくれたら…」
といった不信感が生まれ、兄弟間の関係が壊れることもあります。
話を避けることが“優しさ”になるとは限りません。
早めに話すことこそ、家族にとっての思いやりです。
>兄弟間でなぜ揉める…?トラブル原因5選
制度改正で“事前準備がある人”が得をする時代に
2024年以降、相続登記の義務化や不動産の共有制度改正など、
相続に関する法律は大きく変わりました。
生前のうちに、
・不動産の名義を整理する
・財産目録(ざいさんもくろく)を作っておく
・遺言書を公正証書で残す
といった準備をしておくことで、
相続後のトラブルをほぼゼロに近づけることができます。
2. 高齢の親に相続の話を切り出す3つのタイミング

では、実際にどんなタイミングで話を切り出せばよいのでしょうか?
ここでは、自然に会話に入りやすい3つのきっかけを紹介します。
(1)身近な人の相続をきっかけに話す
「○○さんの家で相続の話があったらしい」
「ニュースで相続トラブルの特集を見たよ」
──こうした“第三者の話題”を入口にすると、
親も構えずに話を聞いてくれることが多いです。
「うちもそういうこと、ちゃんと決めておいた方が安心だね」
と、自然に相続の話へつなげられます。
(2)介護や入院など“将来の生活”を話す流れで
介護や医療の話をするとき、
「もしもの時はどうしたい?」という話題から入るのも効果的です。
そこから、
・誰にどんな財産を託したいか
・自宅は残したいか売りたいか
・延命治療を望むかどうか
といったテーマに発展させやすくなります。
相続の話というよりも、
「生き方」「暮らし方」の延長線で話すのがポイントです。
(3)親自身が“整理したい”と感じているとき
高齢になると、多くの人が
「物やお金を整理しておきたい」「迷惑をかけたくない」
という気持ちを持ち始めます。
その時期を感じたら、
「私たちも安心したいから、一緒に整理しよう」と
“支える立場”で声をかけるとスムーズです。
このとき、「相続」や「死後」といった言葉を避け、
「もしものときに困らないように」「手続きがスムーズになるように」と
前向きな表現を使うと効果的です。
3. 親が話したがらないときの対応法

「話を切り出したけど、拒絶された」
そんなときも、焦らず段階を踏むことが大切です。
“押しつけ”ではなく、“一緒に考える姿勢”を示す
相続の話を嫌がる親の多くは、
「自分の人生を決められる」と感じて防御反応を起こしています。
まずは、
「お父さんの考えを知っておきたいだけなんだ」
「何かあったときに、家族で困らないようにしたいだけ」
と伝えましょう。
“話し合い”ではなく、“相談”という姿勢を取ることで、
心を開いてくれることが多いです。
専門家を交えて“第三者の提案”に変える
親子だけで話すと、感情が先に立ちやすくなります。
そんなときは、司法書士や税理士など専門家を交えて話すのがおすすめです。
「法律の観点から話を聞くだけでも違うよ」
と伝えれば、親も“学びの機会”として受け止めてくれます。
専門家が入ると、
・遺言書を作ると何が変わるか
・税金面でどんな違いがあるか
を客観的に説明してもらえるので、
親の不安が薄れ、前向きな話し合いにつながります。
繰り返し話題にして「慣れ」を作る
一度で進めようとせず、
時間をかけて少しずつ“相続の話題”に慣れてもらいましょう。
最初は軽い話題からで構いません。
「通帳どこにある?」「不動産の名義、最近変えてる?」
といった会話から少しずつ具体的な話へ広げていきます。
相続の話は“1回勝負”ではなく、“長期戦”が基本です。

4. 話をスムーズに進める3つのコツ

心理的なハードルを下げながら話を進めるには、
次の3つのコツが役立ちます。
(1)「ありがとう」で始め、「安心」で終わる
相続の話は、どうしても重くなりがちです。
だからこそ最初に「今まで育ててくれてありがとう」と伝えるだけで、
会話の空気がやわらかくなります。
最後に「これで安心したね」と締めくくることで、
親に「話してよかった」と感じてもらえる流れを作れます。
(2)専門用語を使わず、生活に置き換える
たとえば「遺言書を作った方がいい」ではなく、
「お父さんの考えをそのまま残しておく紙があると安心だよ」と伝えるなど、
“わかる言葉”に言い換えることが大切です。
専門用語を多用すると、親は身構えてしまいます。
日常の言葉で説明することが、信頼を生むコツです。
(3)書面よりもまず「気持ち」を聞く
「何を残すか」よりも先に、
「どうしたいか」「どんな思いで暮らしてきたか」を聞くことが大切です。
感情の整理ができたあとに、
「それを形にする方法として、遺言書や生前贈与があるよ」
と伝えると、自然に実務の話へと移行できます。
5. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、
「親にどう話したらいいかわからない」という段階からご相談を受け付けています。
- 家族での話し合いの進め方のアドバイス
- 遺言書作成や生前贈与のサポート
- 不動産・預貯金の整理方法の提案
- 司法書士・税理士・行政書士との連携によるワンストップ対応
ご相談は何度でも無料です!
相続の話を“争いの種”ではなく、“安心のきっかけ”に変えるお手伝いをいたします。
6. まとめ
親に相続の話を切り出すタイミングは、「まだ元気なうち」です。
話しづらいからと先延ばしにすると、
・判断力が落ちて手続きができなくなる
・家族がもめる
・資産が正しく引き継がれない
といったリスクが高まります。
自然に話を始めたいときは、
- 身近な人の相続をきっかけに話す
- 介護や老後の話の流れで切り出す
- 親自身の“整理したい気持ち”に寄り添う
この3つのタイミングを意識するのがポイントです。
相続の話は、“不安を減らす会話”です。
勇気を出して一言、「一緒に考えよう」と声をかけてみましょう。
よくある質問
Q1. 親が話したがらない場合、無理に切り出してもいいですか?
無理に迫るのは逆効果です。
一度拒まれたら「今度専門家に一緒に話を聞いてみようか」など、
第三者を介して少しずつ距離を縮めるのが効果的です。
Q2. 相続の話を始める年齢の目安はありますか?
一般的には70代前半が最も多いです。
判断力がしっかりしていて、生活の整理を意識し始める時期だからです。
ただし、健康状態や家族構成によって前後するため、
「思い立った今」が最良のタイミングといえます。
Q3. 相続の話はどの専門家に相談すればいいですか?
内容によって異なります。
・財産の名義や登記 → 司法書士
・税金や贈与 → 税理士
・家族間のトラブル → 弁護士
がそれぞれ担当分野です。
がもう相続相談センターでは、これらすべてをワンストップで相談可能です。
弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。
ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

