
相続税の制度は複雑で、「どうすれば税金を減らせるのか」と悩む方は少なくありません。
その中で昔から注目されている方法のひとつが「養子縁組」です。
養子縁組は本来、家族関係を築くための制度ですが、相続税の計算方法に大きく関わります。
実際に国税庁の計算式に「養子」という言葉が明記されていることからも、制度として正しく活用すれば効果があることがわかります。
ここでは、養子縁組と相続税の関係をできるだけ分かりやすく解説し、メリットと注意点を整理します。
こちらの記事も合わせて読まれています
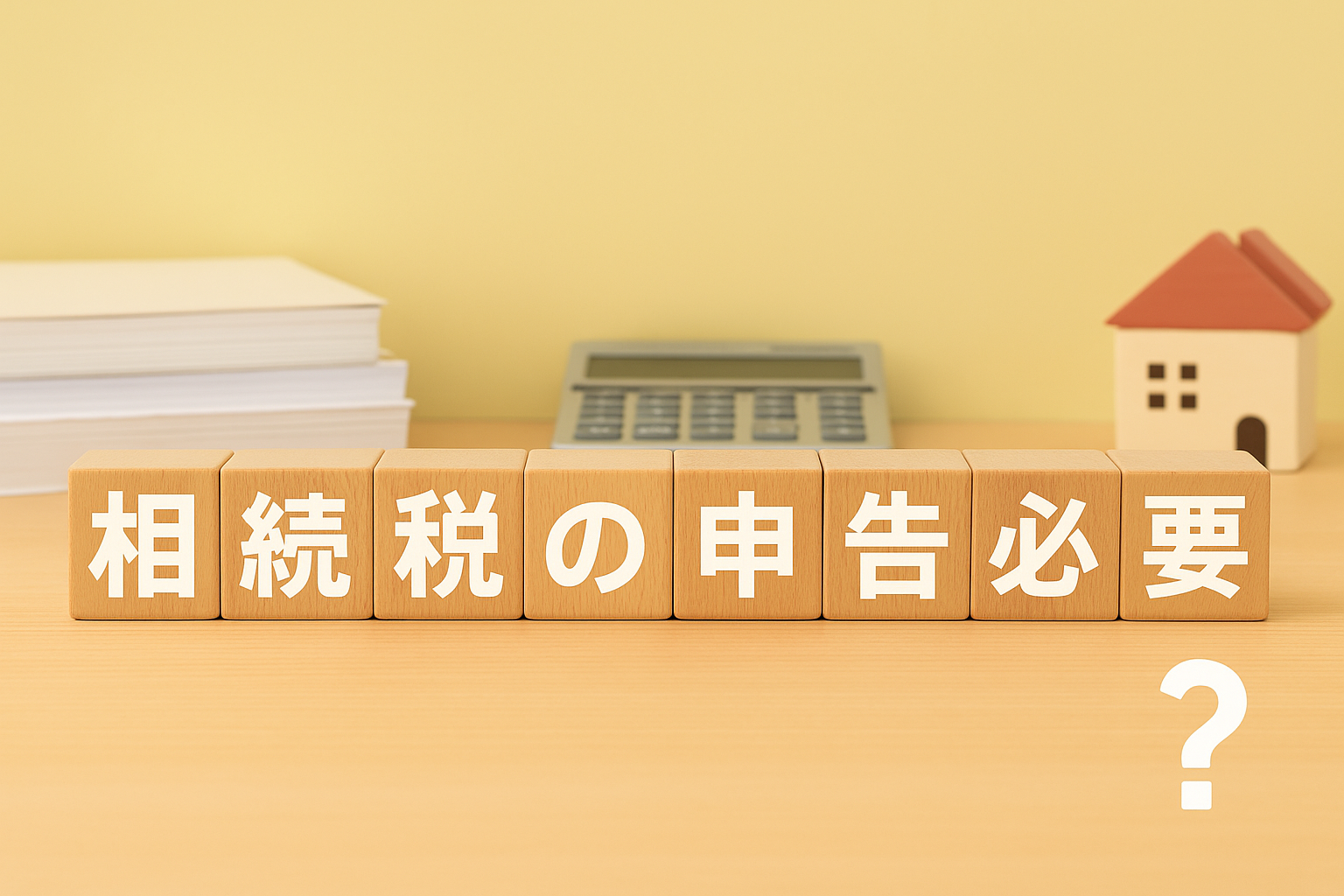
1.相続税と基礎控除の仕組み

相続税の計算では、遺産の総額から「基礎控除」という金額を引いた残りに税率をかけます。
国税庁が定めている基礎控除の公式は次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人とは、配偶者や子どもなど、民法で定められた「相続できる人」のことです。ここに養子も含まれます。
計算例
- 配偶者と子1人の場合
相続人は2人 → 基礎控除額=3,000万円+600万円×2=4,200万円 - 配偶者と子1人+孫を養子にした場合
相続人は3人 → 基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円 - 子がいない夫婦が養子を2人迎えた場合
相続人は2人 → 基礎控除額=3,000万円+600万円×2=4,200万円
このように、養子縁組によって相続人の数が増えると、控除額も増加します。
2.養子縁組が相続税対策になる仕組み
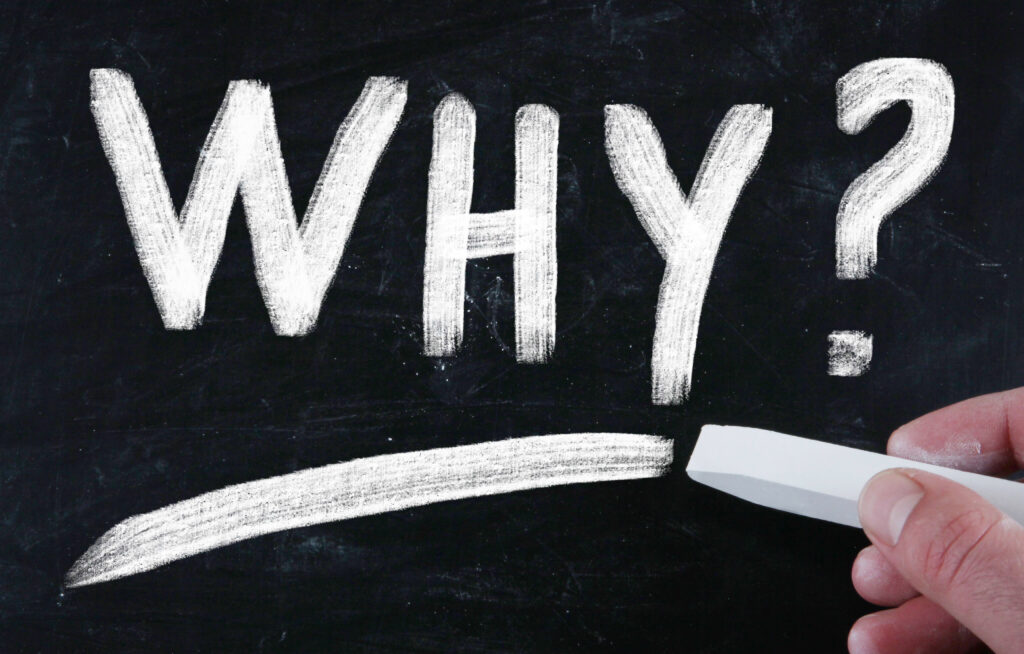
養子縁組が有効とされる理由はシンプルです。
「相続人が増える=基礎控除が増える」ため、課税対象となる遺産額を小さくできるからです。
特に土地や不動産を持っている家庭では、評価額が高いために基礎控除を超えやすくなります。
現金が少なくても「土地の値段」で相続税が発生することがあるため、基礎控除を増やす工夫は大きな意味を持ちます。
3.人数制限と孫養子加算

国税庁は養子縁組の人数について次のような制限を設けています。
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
また、孫を養子にした場合は「一代飛ばして相続する」扱いになり、相続税額が加算されるルールもあります(孫養子加算)。
これは「相続税を一世代分飛ばして減らす」ことを防ぐための制度です。
4.メリット
- 相続税の軽減
基礎控除額が増え、相続税の負担を減らせる可能性があります。 - 後継者を確保できる
子どもがいない夫婦が養子を迎えれば、財産を承継する人を確保できます。 - 家族関係の安定
血縁に限らず、信頼できる人や孫と親子関係を築けます。
5.注意点とトラブル事例
- 形式的な縁組は認められない
「節税目的だけ」と判断されると無効になる可能性があります。過去の裁判例でも「真実の親子関係」が重視されました。 - 相続人が増えることで不満が出る
「養子を入れたことで自分の取り分が減った」と兄弟姉妹が不満を抱くケースがあります。実際に遺産分割協議が長期化した事例もあります。 - 扶養義務が発生する
養子は法律上の子どもです。生活を助ける義務も生じるため、親族関係の責任は重くなります。 - 孫養子加算の存在
孫を養子にした場合、相続税の加算対象になるため「控除が増える=必ず得する」とは限りません。
6.FAQ

Q.普通養子縁組と特別養子縁組の違いは?
普通養子縁組は実親との関係を残したまま新しい親子関係を結びます。特別養子縁組は実親との関係を完全に断ち切る制度で、通常は未成年を対象にしています。相続税対策で使われるのは普通養子縁組です。
Q.いつまでに養子縁組すれば効果がありますか?
相続開始(被相続人が亡くなった時点)までに縁組が成立している必要があります。直前の縁組でも法的には有効ですが、実態が伴わない場合は否認される可能性があります。
Q.養子にすると必ず相続税は安くなりますか?
基礎控除は増えますが、遺産の規模や孫養子加算の有無によって結果は異なります。実際の計算は税理士に確認するのが安心です。
7.まとめ
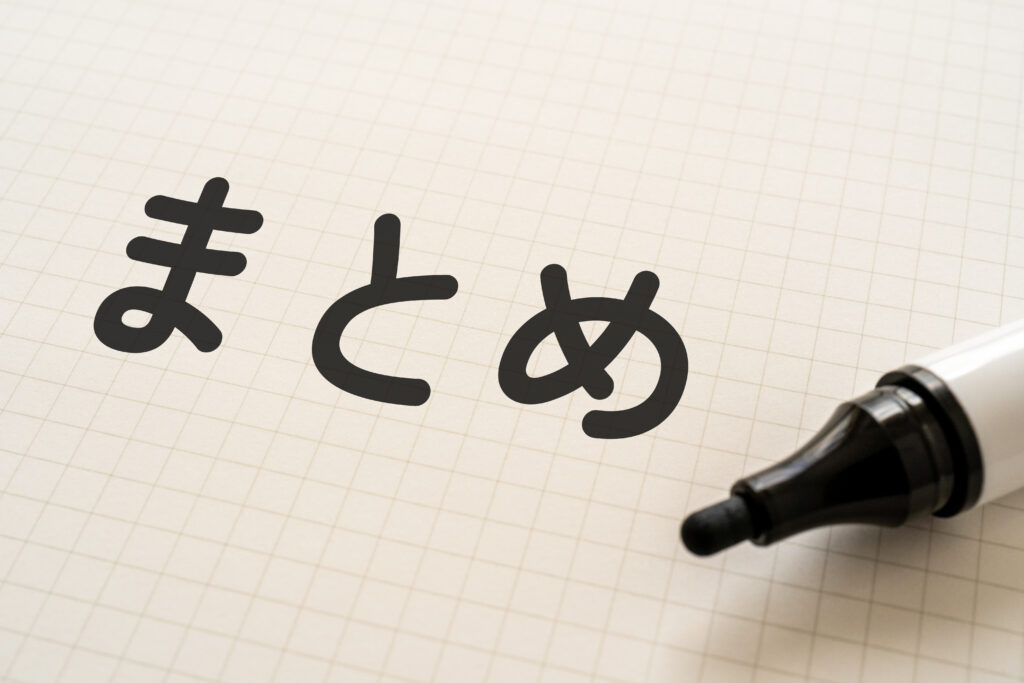
- 養子縁組は、相続税対策として「基礎控除を増やせる」制度として一般的に知られている
- 国税庁の公式式に基づき、法定相続人にカウントされるため効果がある
- ただし人数には制限があり、孫養子の場合は加算税もある
- メリットと同時に、家庭内トラブルや扶養義務といったリスクも存在する
- 制度を利用する際は「節税目的だけ」にせず、家族関係を含めた長期的視点が必要
養子縁組は相続税対策の一つとして有効な手段ですが、誰にでも適しているわけではありません。税制のルールや家庭の事情を踏まえたうえで、専門家に相談しながら検討することが大切です。
弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。
ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

