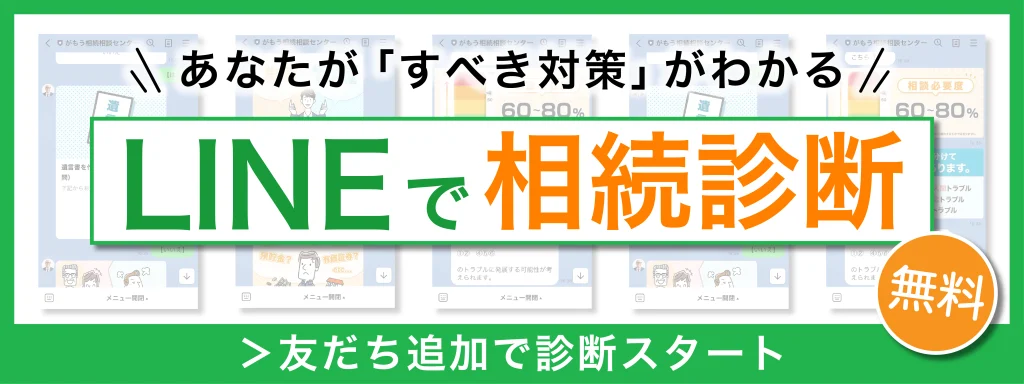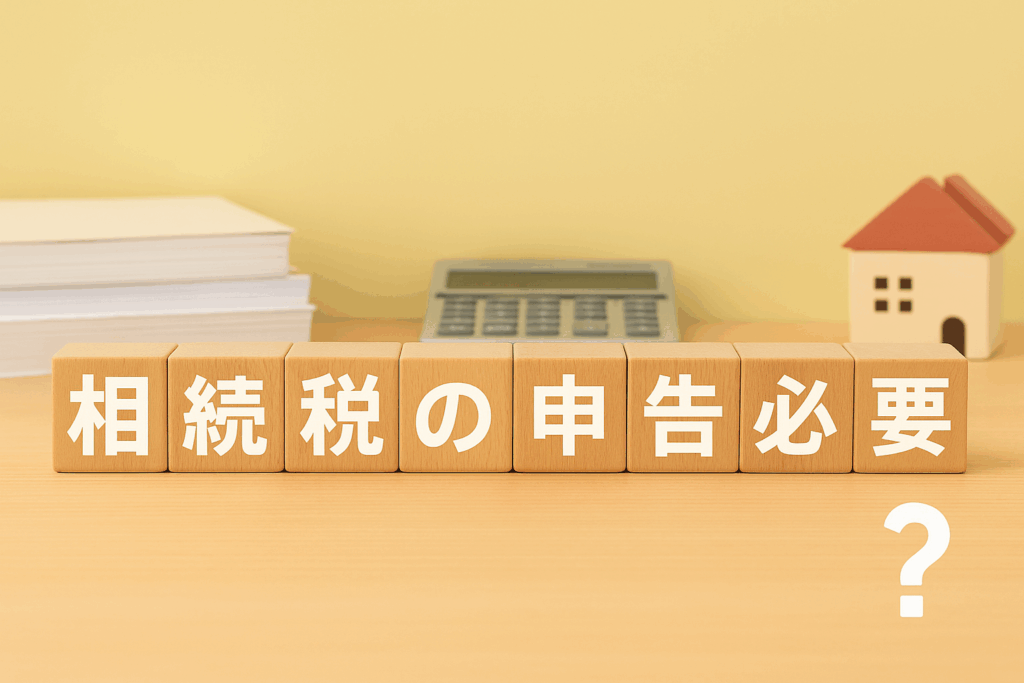
親が亡くなったとき、多くの人が悩むのが「相続税がかかるのかどうか」です。
「資産家じゃないから大丈夫」と思っていても、実際に申告が必要だったというケースは少なくありません。
この記事では、相続税の申告が必要な人と不要な人の違いを、最新の法律に基づきわかりやすく解説します。
具体的な例や事例も紹介するので、自分の家庭にあてはめて考えてみてください。
1.相続税の申告が必要な人とは?基礎控除額で判断する
相続税がかかるかどうかを判断する基準は「基礎控除額」です。
基礎控除の計算式
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:相続人が2人なら
3000万円+600万円×2=4200万円
→ 遺産総額が4200万円を超えれば相続税の申告が必要になります。
2.相続税の申告が不要な人とは?具体例で理解しよう
基礎控除以下で、特例を使わない場合は申告不要です。
具体的なケース
- 相続人1人、遺産総額3000万円 → 控除3600万円以下なので不要
- 相続人2人、遺産総額4000万円 → 控除4200万円以下なので不要
- 相続人3人、遺産総額4700万円 → 控除4800万円以下なので不要
このように、遺産総額が基礎控除に収まっていれば相続税の申告は不要です。
ただし「不要」でも不動産登記や預金の解約といった相続手続きは必須なので注意しましょう。
3.相続税が必要かどうかを判断する流れ
「自分は相続税がかかるのか?」を確認する流れをまとめました。
相続税 必要/不要の判断フローチャート
(預金・不動産・有価証券などを合計)
(3000万円+600万円×相続人の数)
遺産総額 ≤ 控除額 → 原則不要
→ 迷ったら放置せず、税理士に早めに確認することが大切です。
4.相続税が必要になった/不要だった事例
事例1:控除以下でも申告が必要だったケース
大阪のAさんは、遺産総額が4000万円で相続人は2人。控除額4200万円以下なので「不要」と思っていました。
しかし、自宅の土地に「小規模宅地の特例」を使いたい場合、たとえ税額がゼロでも申告が必要。
結果的に申告期限ギリギリに税理士へ駆け込みました。
事例2:不動産評価で課税対象になったケース
東京都内で30坪ほどの土地を所有していたBさん。市場価格では4000万円程度と思っていたのに、税務評価額は6000万円。
相続人は2人で控除額4200万円を超えてしまい、申告が必要になりました。
事例3:不要だったケース
地方に住むCさんは、現金3000万円と小さな土地を残しました。相続人は1人で控除額3600万円。
基礎控除以下なので相続税は不要。申告はせず、不動産登記と預金の解約だけで済みました。
【その他トラブルにつながるケースはこちら】
5.相続税の申告期限と注意点
相続税の申告期限は 相続開始から10か月以内 です。
もし遅れると…
- 延滞税や加算税が課される
- 配偶者控除や特例が使えなくなる
- 本来ならゼロだった税額が課税されることもある
「不要かも」と思っても、申告が必要かどうか早めに確認することが一番の安心につながります。
6.相続税に関するよくある質問(FAQ)
Q1.相続税が必要かどうかは誰に相談すればいい?
→ 税理士が専門です。司法書士や弁護士は登記や争いごとに強いですが、税額の判断は税理士になります。
費用は財産規模によりますが、一般的に10〜50万円程度が目安です。
Q2.相続税の申告を忘れたらどうなる?
→ 延滞税・無申告加算税がかかります。申告期限から数ヶ月遅れるだけで数十万円単位のペナルティになることもあります。
Q3.相続税が不要でも登記や名義変更は必要?
→ はい。不動産の登記や銀行口座の解約は相続税の有無に関わらず必ず必要です。放置すると後々トラブルになります。
まとめ:相続税が必要な人・不要な人の違い
- 必要な人
基礎控除額を超える遺産を相続する人
控除以下でも特例を使う人 - 不要な人
基礎控除額以下で、特例を使わない人 - 大事なポイント
・基礎控除を計算して判断する
・特例を使うときはゼロでも申告が必要
・不動産評価で課税になるケースが多い
・申告期限は10か月以内、遅れるとペナルティ
さらに詳しく対策方法を知りたい方は、ぜひ弊社の無料相談にお申し込みください!
あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。
\ この機会に是非ご登録ください! /