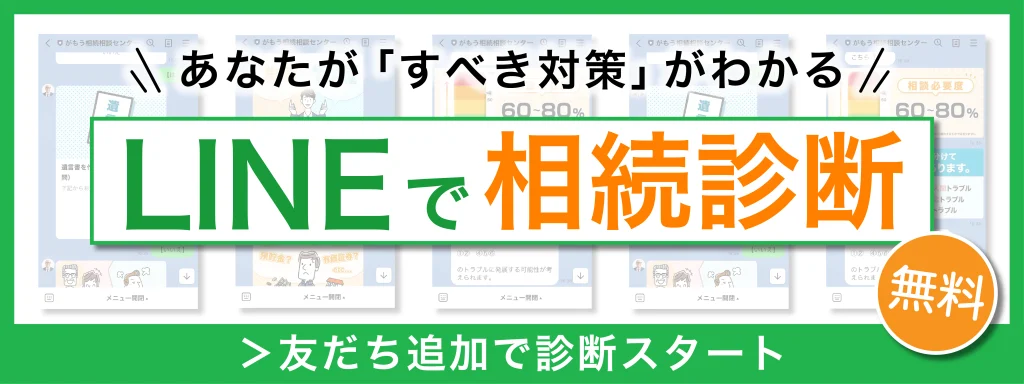相続が始まったとき「遺言書がない」と大きなトラブルに繋がります。
この記事では、遺言書がない場合に相続手続きでどのようなリスクが生じるのかを、わかりやすく解説します。
1.遺言書がないと「法定相続分」に従うことになる

遺言書がない場合、相続手続きは民法で定められた 法定相続分 に従って行われます。
例えば、配偶者と子どもが相続人であれば、配偶者が1/2、子どもが残り1/2を人数で等分するという形です。
一見公平に見えますが、実際には以下のような問題が起きやすくなります。
遺産の分け方が相続人の希望と合わない
法定相続分はあくまで法律上の一般ルールであり、家族の事情や本人の想いを一切考慮しません。
例えば、長男が親の介護を続けてきたとしても、その貢献度は考慮されず、兄弟姉妹で均等に分けられてしまいます。
「自分の尽力が報われない」という不満が出やすくなるのです。
特定の人に多く遺したい希望が反映されない
「配偶者の生活を守るために多めに遺したい」「障がいのある子に手厚く残したい」など、
被相続人の意志があっても、遺言書がなければ一切反映されません。
その結果、残された家族が困窮するケースも少なくありません。
相続人同士で意見が対立しやすい
法定相続分に基づく分け方は公平に見えますが、
不動産や事業資産のように分割しにくい財産がある場合、揉め事が生じやすい です。
「自宅に住み続けたい人」と「現金化して分けたい人」で意見が割れ、争いの火種になります。
2.遺産分割協議が必要になりトラブルが増える

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」をしなければ相続手続きが進みません。
ここで意見が食い違うと、以下のようなリスクが発生します。
話し合いがまとまらず長期化する
相続人が複数いるほど、利害関係が複雑化しやすい です。
不動産の扱い・現金の使途・預貯金の配分など、全員が納得する形を見つけるのは困難で
何年も決まらないケースもあります。
感情的な対立から家族関係が悪化する
財産をめぐる議論は単なる金銭問題にとどまらず、
「親の愛情の差」や「過去のわだかまり」 と結びつきます。
そのため些細な金額の差でも「不公平だ」と感じ、兄弟姉妹の関係が修復不可能になることもあります。
裁判沙汰になり時間と費用がかかる
協議がまとまらなければ家庭裁判所で「調停」や「審判」となります。
弁護士費用や裁判にかかる時間的コストが増大し、
相続財産そのものが目減りする リスクもあるのです。
3.相続手続きが進まず「不利益」が発生する

遺言書がないことで相続手続きが停滞すると、以下のような不利益が現実的に起こります。
銀行口座が凍結され生活資金が使えない
被相続人が亡くなると、銀行は口座を凍結します。
そのため、葬儀費用や入院費の支払いがあるのに引き出せない 状況に陥るのです。
不動産の名義変更ができず資産を動かせない
不動産は相続手続きで名義変更が必要ですが、協議がまとまらなければ手続き不能。
その間、売却も賃貸もできず「塩漬け資産」 となり、固定資産税だけがかかり続けます。

相続税の期限に間に合わずペナルティがかかる
相続税は「相続開始から10か月以内」に申告・納税しなければなりません。
しかし協議が長引くと期限に間に合わず、延滞税や加算税といった余計な負担 が発生します。
つまり、遺言書がないことで相続手続きがスムーズに進まず、金銭的・時間的な負担が大きくなってしまうのです。
4.遺言書を用意するとどうなる?

逆に、遺言書を準備しておけば相続手続きの多くのリスクを回避できます。
本人の意思が優先される
遺言書は「財産の分け方」を明確に記したものなので、法定相続分より優先されます。
これにより「誰にどの財産を遺すか」が一目瞭然となり、相続人同士の議論が不要になります。
協議の負担が減る
遺言書に基づいて相続手続きを進められるため、協議や争いを最小限に抑えられる のです。
速やかに相続手続きが進む
特に「公正証書遺言」であれば検認も不要なので、すぐに銀行解約や不動産名義変更に使える 実効性の高い書面になります。
特に「公正証書遺言」であれば無効になるリスクも低く、相続手続きに直結する確実な手段となります。
5.まとめ
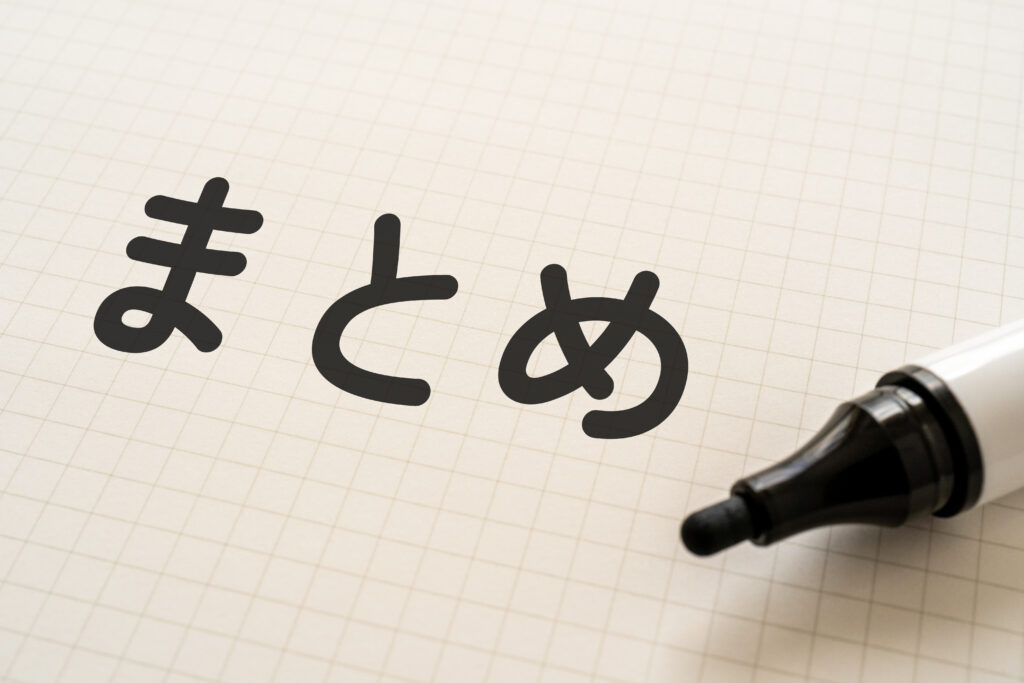
遺言書がないと、相続手続きは法定相続分に従い、協議や手続きが停滞して不利益を生みやすくなります。
特に「希望が反映されない」「家族関係が悪化する」「税金や生活費で困る」など、
人生に大きな影響を及ぼすリスクが現実的に起こり得ます。
一方で、遺言書を準備しておけば相続手続きの基準が明確になり、家族の争いを防ぎ、安心して将来を迎えることができます。
さらに詳しく対策方法を知りたい方は、ぜひ弊社の無料相談にお申し込みください!
あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。
\ この機会に是非ご登録ください! /