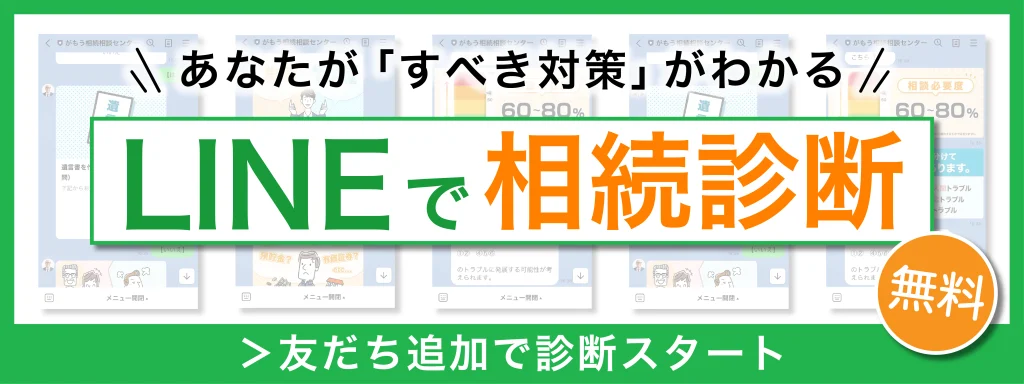親が借金を残して亡くなったら相続放棄すれば大丈夫です。
しかし、実はこの“相続放棄”、やり方を間違えると借金を背負うリスクがあります。
特に大切なのが、相続放棄の期限と手続きのルールを正しく理解しておくこと。
相続放棄の実例はコチラ!
1.相続放棄とは?

「プラスもマイナスも全部放棄」の制度
相続放棄とは、相続人が財産を一切引き継がないと家庭裁判所に申し出る手続きのことです。
放棄が認められると、最初から“相続人ではなかった”ことになるため、
- 借金や債務を引き継がずに済む
- 財産を一切受け取らない
- 他の相続人に権利と義務が移る
という扱いになります。
特に、借金が多い親の相続では、相続放棄をしないと多額の負債を抱えることになるリスクがあるため、相続放棄は必須です。
さらに詳しい解説はコチラ
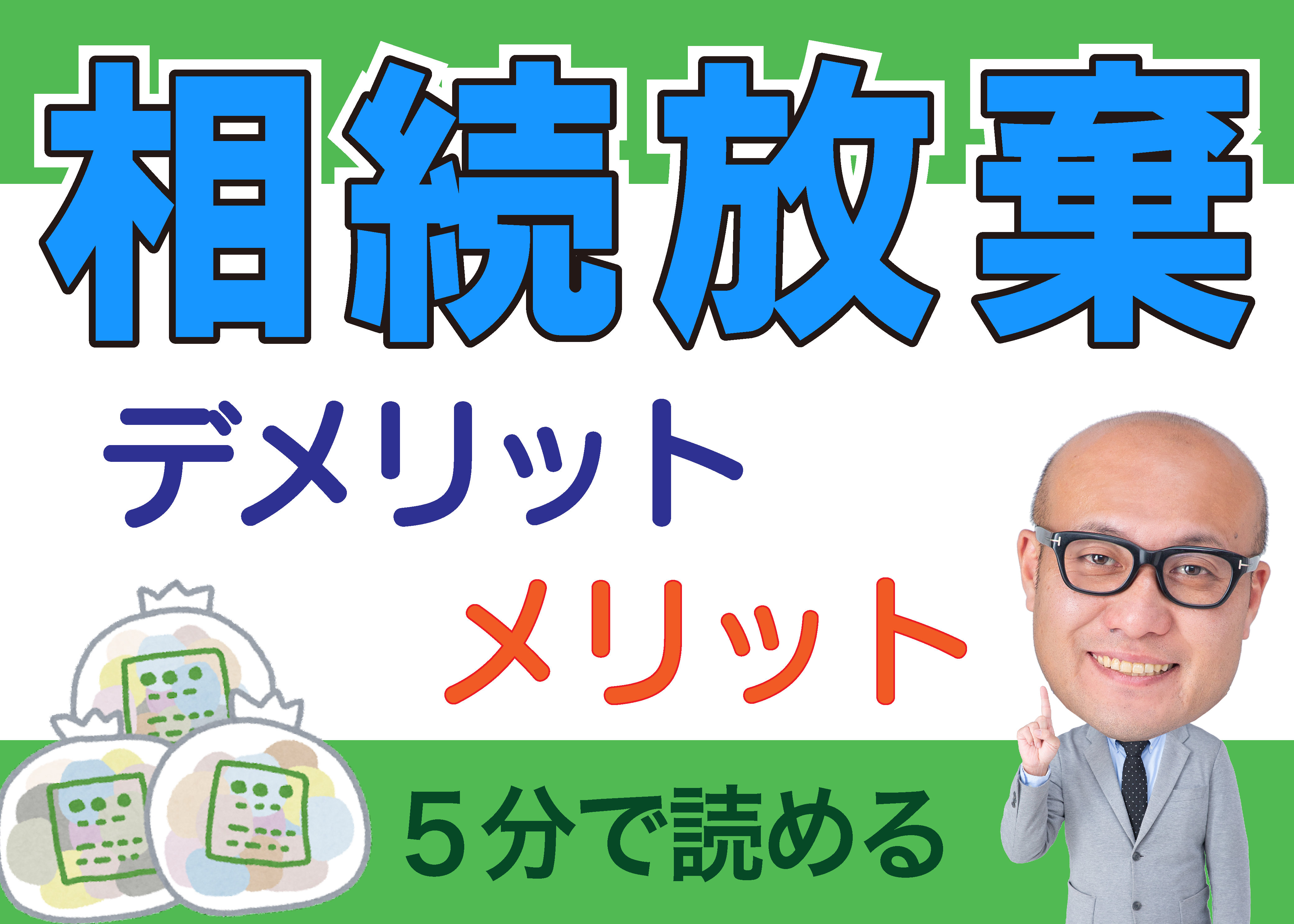
2.相続放棄の期限

注意:相続開始を知った日から3ヶ月以内
相続放棄の最大の落とし穴は、期限が非常に短いことです。
民法では、相続放棄の期限は「自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内」と定められています。
つまり、「あとで考えよう」と思っていると、3か月があっという間に過ぎてしまう可能性があります。
3.相続放棄の方法

家庭裁判所への申述が必要
相続放棄をするには、家庭裁判所への正式な申立てが必要です。
単に「いらないです」と親族に伝えるだけでは、法的に無効です。
相続放棄の基本的な流れ:
- 管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
- 必要書類(被相続人の戸籍・相続人の戸籍など)を添付
- 書類審査を経て、相続放棄が受理されると「受理通知書」が届く
👉 ポイントは「必ず3か月以内に申立てをする」こと。
不備があると受理されないため、専門家に相談して進めるのが安心です。
4.知らないと損する注意点

相続放棄は便利な制度ですが、次のような注意点があります。
● 注意点①
一部だけ放棄はできない
相続放棄をすると、すべての財産(プラスもマイナスも)を放棄したことになります。
「借金はいらないけど、預貯金だけほしい」は認められません。
● 注意点②
一度放棄すると撤回できない
相続放棄が受理されると、後から「やっぱり受け取りたい」はできません。
慎重に判断する必要があります。
● 注意点③
相続財産を使った時点で放棄不可になる場合も
相続財産を勝手に使ったり、売却したりすると「単純承認(=放棄できない)」とみなされることがあります。
● 注意点④
放棄すると、次の相続人に回る
自分が相続放棄をすると、その分の相続権は他の相続人(たとえば兄弟や甥姪)に移ります。
その結果、他の親族に迷惑をかけることもあるため、全体像を考慮したうえで判断することが大切です。
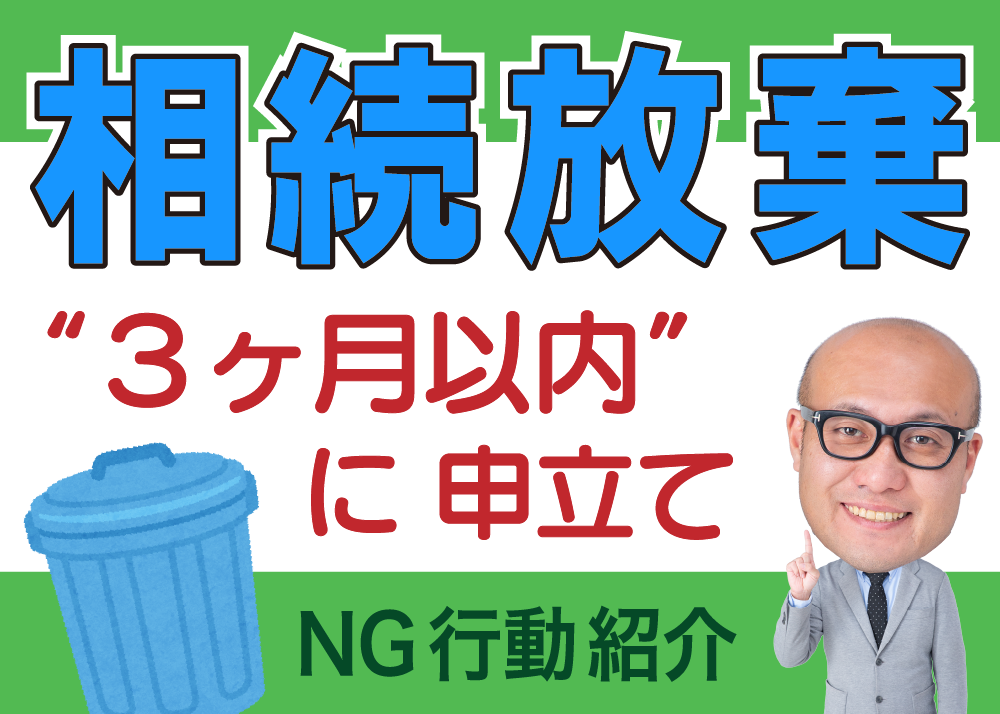
5.まとめ
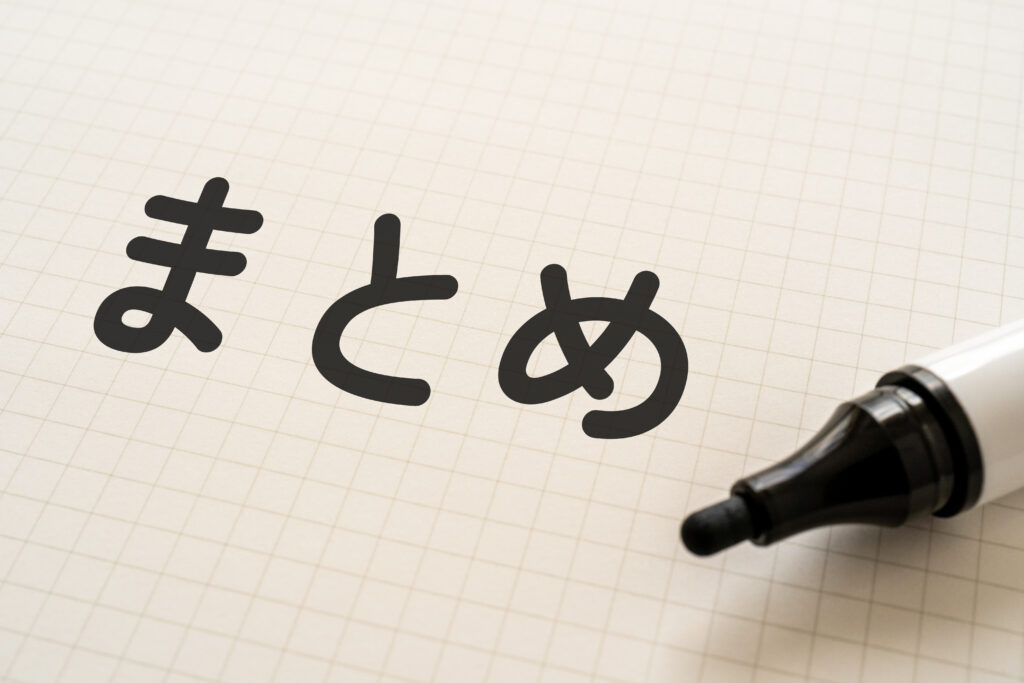
相続放棄は“期限と手続き”を守るのが最重要!
相続放棄は、相続税や借金リスクを回避する有効な手段ですが、
「期限」や「申立て方法」を誤ると、放棄できずに損をするケースもあります。
もう一度、ポイントをおさらいしましょう。
- 相続放棄の期限は「相続を知った日から3か月以内」
- 口頭では無効、家庭裁判所での申立てが必要
- 放棄後の撤回や一部のみの放棄は不可
- 相続財産の使用で放棄できなくなるケースもある
- 他の相続人への影響も考慮して判断を
迷ったら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
「相続放棄は期限が命」——知っているかどうかで、将来の安心が大きく変わります。
弊社では何回でも何時間でも無料でご相談いただけます。
また、相続放棄以外の相続まで幅広くカバーしております。
「何から手をつけたらいいのか…」とお考えの方に弊社の無料相談はピッタリです!
あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。
\ この機会に是非ご登録ください! /