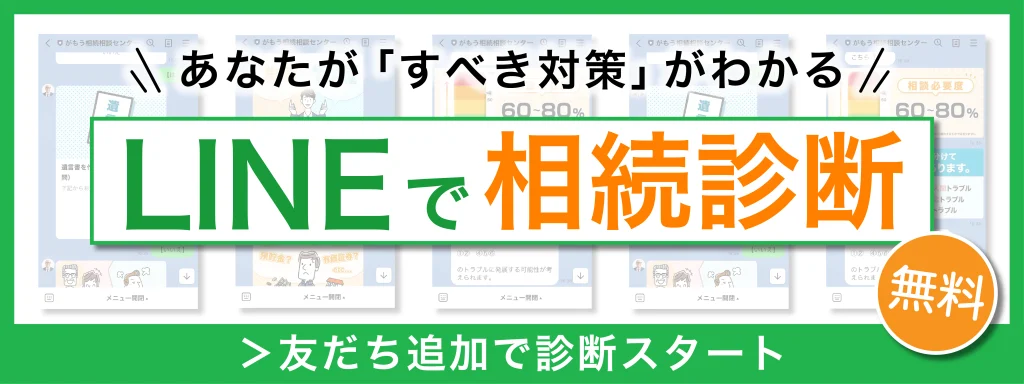「生前贈与をすれば、相続税が安くなる」と思っていませんか?
たしかに相続税対策として有効な手段ですが、使い方を間違えると、かえって相続税が高くなるケースがあるのです。
この記事では、
生前贈与がうまくいかない理由や、相続税が高くなる落とし穴についてわかりやすく解説します。
1.まず初めに生前贈与のおさらい

生前贈与は、生きているうちに財産を少しずつ渡すことで、将来の相続財産を減らし、相続税が高くなるのを防ぐためです。
とくに有名なのが、年間110万円の非課税枠。
この範囲内であれば贈与税がかからず、毎年コツコツと渡すことで節税になるという仕組みです。
しかし、この方法には見落とされがちな注意点があります。
2.生前贈与でも「相続税が高くなる」3つの落とし穴

落とし穴①:「相続開始前7年以内」の贈与は相続税の対象に
もっとも大きな誤解がこれです。
実は、亡くなる前の7年間に相続人に対して行われた贈与は、相続税の計算に戻されるルールがあります
せっかく贈与しても、相続税の課税対象に加算されてしまい、相続税が高くなる結果になるのです。
特に高齢になってから贈与を始めた場合、このルールに引っかかりやすくなります。
落とし穴②:「贈与したつもり」はアウト

生前贈与は、「あげたつもり」「もらったつもり」では成立しません。
たとえば以下の場合、贈与と認められません
- 贈与契約書を作っていない
- 親の口座から子の口座に移しただけで、子が管理していない
- 通帳や印鑑を親が持ったまま
このような場合、税務署に「名義預金」と判断され、生前贈与と認められません。
結果的に相続税が高くなることがあります。
生前贈与をする場合は正式な手続きが必要です。
落とし穴③:毎年110万円ずつ贈与しても「定期贈与」と判断されることも

毎年同じ金額を贈与していると、
税務署から、
「はじめから1,100万円を10年に分けて贈与しただけ」とみなされるリスクがあります。
これは「定期贈与」と呼ばれ、全額が一括で贈与されたと判断され、贈与税や相続税が高くなる可能性があります。
3.生前贈与で相続税対策を成功させるには?
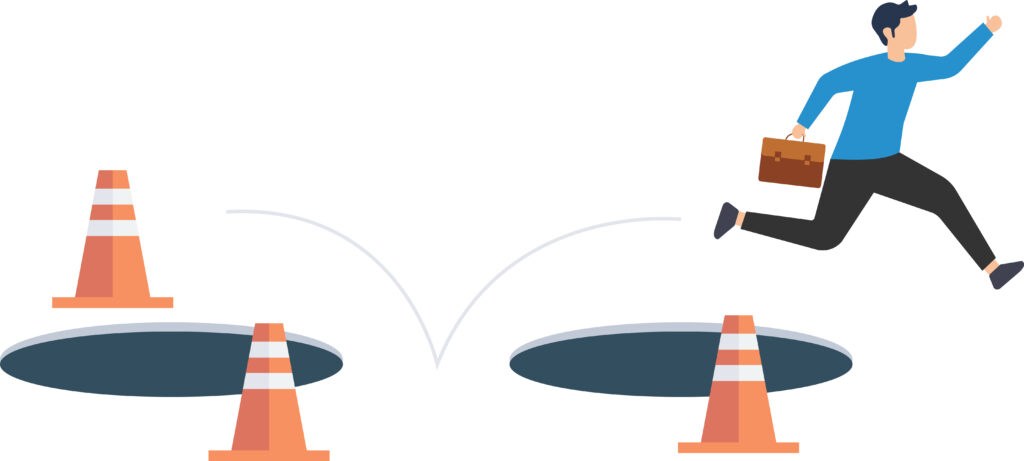
生前贈与をうまく活用して相続税を抑えるために
以下のポイントを押さえましょう!
- 贈与契約書を毎年作成する
- 通帳・印鑑は受贈者(もらう側)が管理する
- 金額や回数を変えて「定期贈与」とみなされない工夫をする
- 税務上のルールを正しく理解する
- 税理士など専門家に相談する
4.まとめ:生前贈与=節税になるとは限らない
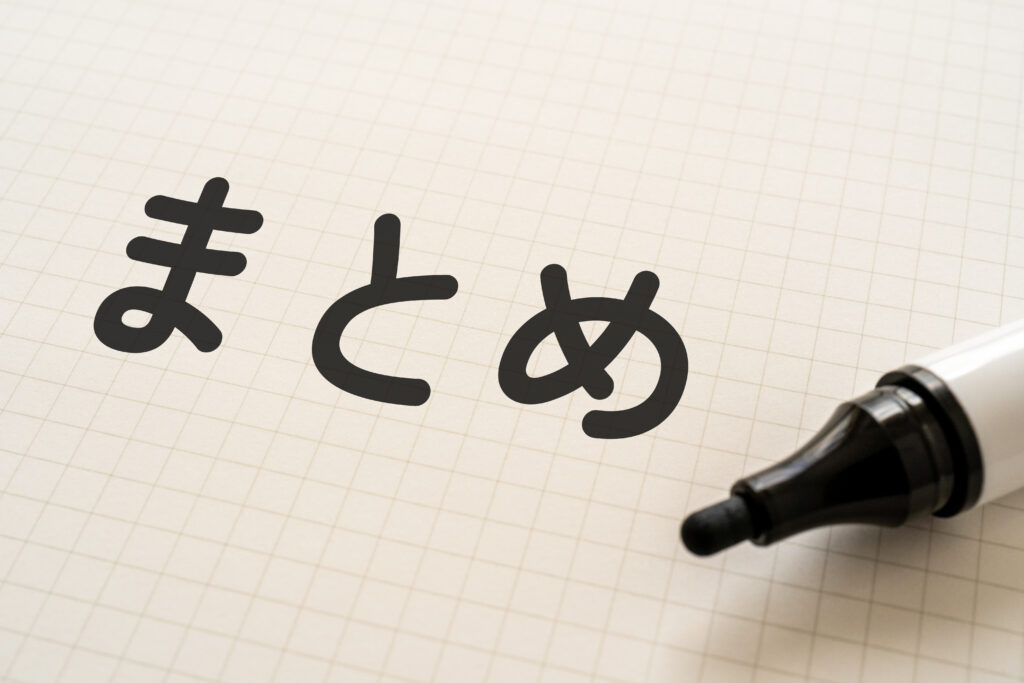
「生前贈与をすれば、相続税が安くなる」と考えるのは間違いではありません。
しかし、使い方を間違えると相続税が高くなる可能性もあります。
特に、
- 相続開始前7年以内の贈与
- 曖昧な贈与手続き
- 税務署に否認されるリスク
これらの落とし穴を理解したうえで、計画的に生前贈与を進めていくことが大切です。
相続税対策をしたい方は、自己判断せずに必ず専門家に相談しましょう。
高くつく相続税を防ぐには、「正しい知識」と「早めの行動」がカギです。
弊社では提携の税理士とご相談いただくことが可能です。
また、相続税対策以外の相続まで幅広くカバーしております。
「何から手をつけたらいいのか…」とお考えの方に弊社の無料相談はピッタリです!
あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。
\ この機会に是非ご登録ください! /