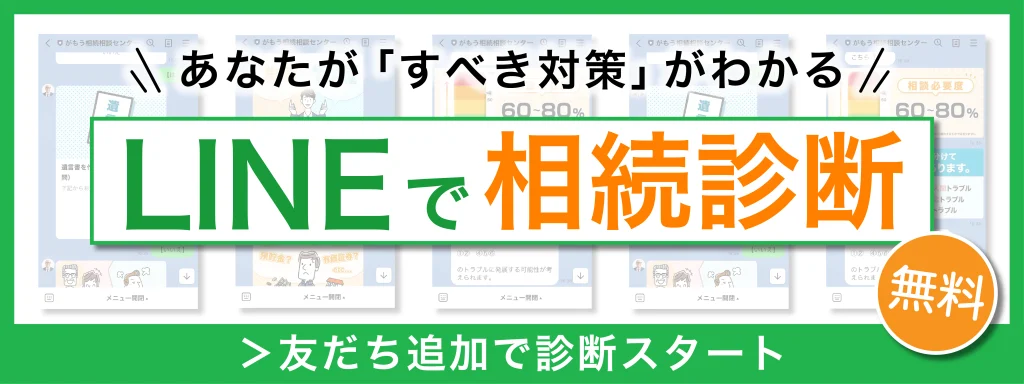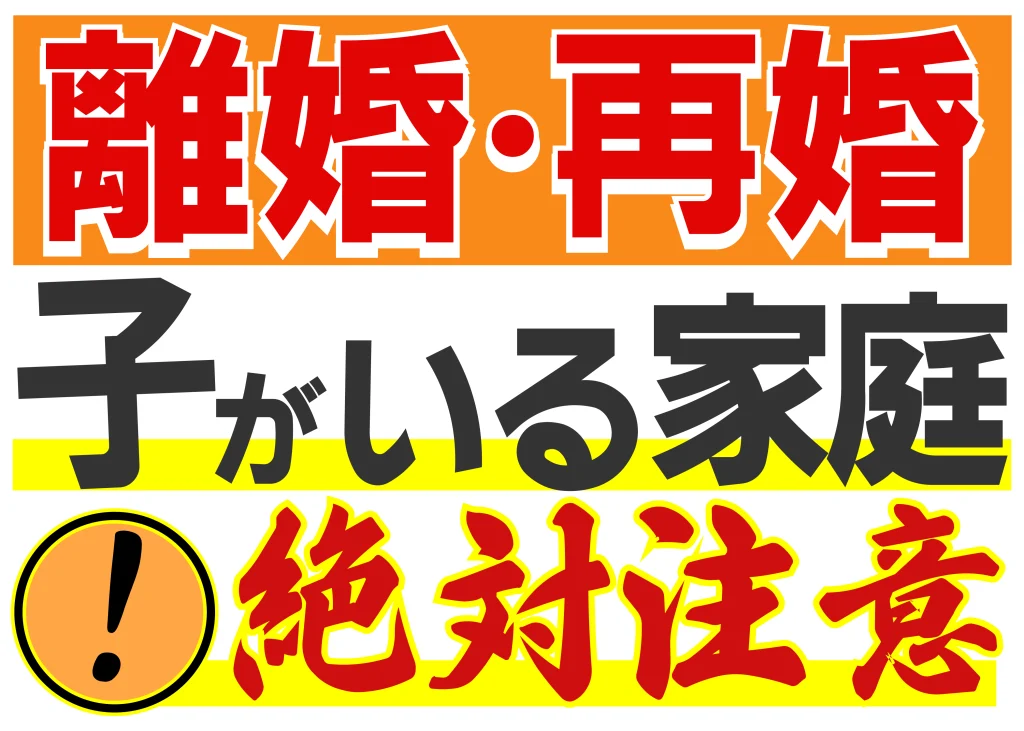
離婚や再婚が増える中で、「家族のかたち」はどんどん多様化しています。
しかし、相続の仕組みは昔のままです。
再婚家庭では「法律上の相続人」と「実際の家族関係」にズレが生じ、
予想外のトラブルに発展するケースが少なくありません。
この記事では、再婚家庭の相続で起こりやすい問題や、「実子・連れ子」との関係における注意点を、事例を交えてわかりやすく解説します。

1.相続人になるのは「誰」?
まず、相続では「誰が相続人になるのか」は、法律で厳密に決められています。
たとえば以下のようなケースで考えてみましょう。
例)Aさん
前妻との間に子が1人。
再婚相手との間にも子が1人。
この場合、Aさんが亡くなったときの相続人は誰でしょうか?
→ 答え:両方の子どもが相続人になります。
つまり、たとえ疎遠になっていた前妻の子であっても、法律上は実子として同じ取り分を持つのです。

2.連れ子は「法的に相続人ではない」
再婚後、夫婦と連れ子で長年一緒に暮らしてきた――
そんな関係であっても、法律上の「親子」になっていなければ、連れ子は相続権がないことをご存じでしょうか?
これは「戸籍上の親子関係」があるかどうかで判断されるのです。
なぜ相続人になれないのか?
民法では、相続人になれるのは原則として「配偶者」と「血縁者」に限られています。
そのため、たとえ再婚相手の連れ子であっても、
養子縁組をしていなければ血縁者ではない=相続人ではないという扱いになります。
つまり、いくら長年大切に育ててきた連れ子であっても、
- 法律的には他人
- 相続では「もらう権利」がない
という現実があるのです。
養子縁組をすれば法的な「子」に
この問題をクリアするために必要なのが、養子縁組です。
養子縁組をすれば、連れ子は正式に「法定相続人」となり、
実子と同じように財産を受け取れるようになります。

3.再婚家庭でよくある相続トラブルとは?
以下は、実際に再婚家庭で起きやすい相続トラブルの一例です。
前妻の子どもと再婚相手が揉める
→ 相続人として法定の取り分を主張され、再婚後の家族が「家を追い出される」事態に。
連れ子に相続させたいのにできない
→ 養子縁組も遺言書もないまま亡くなり、実子だけが財産を取得。
家族関係が複雑で「誰にいくら渡すか」が曖昧
→ 「誰がどれだけもらえるのか」をめぐって、家族間の対立が長期化する。
特に、不動産や自宅など「分けにくい財産」が絡むと、争いはさらに深刻になります。

4.再婚家庭こそ「遺言書」で備えるべき理由
再婚家庭では、「誰に何を遺すのかを予め決めておくこと」が極めて重要なテーマになります。
しかし実際には、そうした“想い”がうまく形にできず、遺産分割の段階で家族同士が対立するケースが非常に多く見られます。
その最大の原因が、「遺言書がないまま亡くなること」です。
想定外の“主張”が、家族の関係を壊す
前妻との子どもが「法定相続人」として突然現れたり、
再婚後の配偶者が「その家で住み続けられなくなる」など、
本人が生前に想像もしなかった状況が、相続の現場では起こります。
特に、遺言書がない場合には「民法のルール=法定相続分」に従って分けられるため、
感情面や生活実態が一切考慮されないというのが大きな問題点です。
遺言書があるだけで防げるトラブルがある
遺言書を作っておけば…
- 相続人ではない連れ子に「遺贈」という形で財産を遺すことができる
- 残された配偶者に「住み続ける権利(配偶者居住権)」を明記できる
- 「誰に、何を、どれだけ」渡すかをはっきりさせることで、揉める余地を減らせる
- 家族へのメッセージや気持ちを添えることで、想いが伝わる
遺言書はトラブルの抑止力であり、家族への配慮でもあるのです。
再婚家庭の「複雑さ」を整理するために必要
再婚家庭では、
- 実子・連れ子・前妻の子
- 今の配偶者・前の配偶者の血縁者
…といった立場の異なる人々が関係する可能性が高く、利害も複雑です。
この状況で、遺言書を用意せずに何も意思表示がされていない状態は、残された家族にとってあまりに過酷な現実です。
5.まとめ:家族のかたちは自由でも、相続はルールどおり
現代では、再婚やステップファミリーは特別なことではなくなりました。
しかし、相続のルールは「戸籍」と「法律」によって動くため、想いだけでは通じない部分があるのも事実です。
再婚家庭の方は、次の2つを意識してください。
- 誰が相続人になるのかを事前に確認する
- 想いを形にする手段(養子縁組・遺言)をきちんと整える
家族を守るためにこそ、冷静に、早めの対策を考えていきましょう。
さらに詳しく知りたい方は、ぜひ弊社の無料相談にお申し込みください!
あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。
\ この機会に是非ご登録ください! /