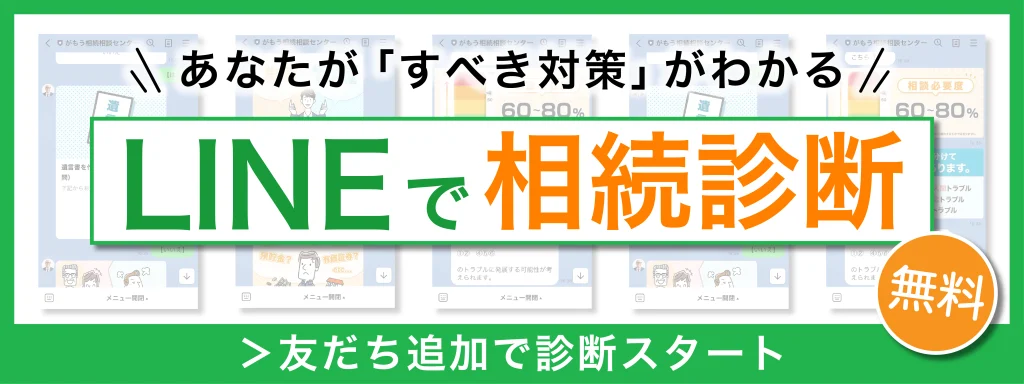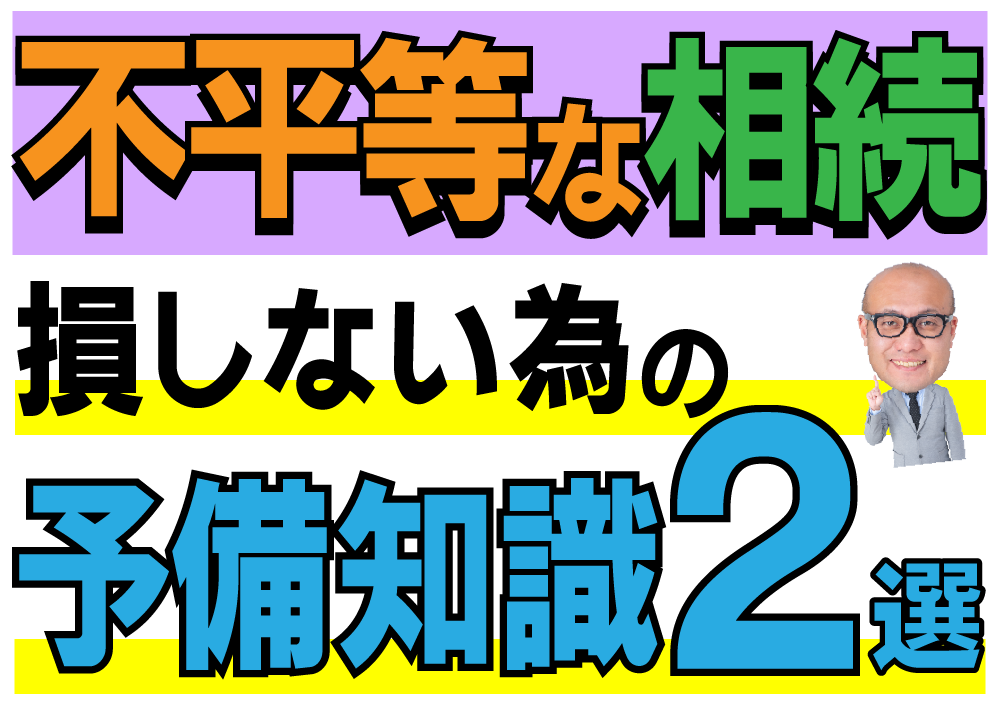
「相続人なのに、私だけ何ももらえないなんて、おかしくないですか?」
実際のご相談の中でも、こうした声は珍しくありません。
相続では、法律で「誰が相続人になるか」「どれだけの割合をもらえるか」が決まっています。
しかし、いざ遺産を分けると——
「兄弟なのに取り分が違う」「相続人なのにゼロ」といった事態が起こることがあります。
その背景にあるのが、相続制度の中でも特に理解が難しい
・寄与分(きよぶん)
・特別受益(とくべつじゅえき)
という2つのルールです。
この記事では、これらの制度がどのように相続人の“取り分”に影響を与えるのかを、
専門用語をなるべく使わずに、事例を交えて分かりやすく解説していきます。
執筆者:司法書士 ほんじょう たかし
若干18歳で単身ブラジルにサッカー留学に行き、帰国後、吉本NSCへ入学。お笑いの道では花咲かず、親戚の葬儀屋で働く中で司法書士と出会い、相続の仕事を志す。
司法書士の資格を取得し、経験を積んだのち「がもう相続相談センター」をオープン。現在では2000名以上のご相談を受け、城東区を中心に多くの相続問題を解決に導く。
1.そもそも相続人は「みんな平等」じゃないの?

「相続人はみんな平等に財産を受け取れる」と思っている方が多くいます。
たしかに、民法では法定相続分という「基本の取り分」が定められており、
たとえば子どもが2人いれば、それぞれ1/2ずつ相続できるとされています。
しかし、現実の遺産分割では、この“基本の取り分”がそのまま適用されないことがあるのです。
その理由が、「寄与分」と「特別受益」という制度の存在です。
- 寄与分 → 生前、親の介護や財産管理を手伝った人は“多くもらえる”可能性がある
- 特別受益 → 生前に多くの援助を受けた人は“取り分が減らされる”ことがある
2.寄与分とは?貢献した人が多くもらえる仕組み

「親の介護を10年以上してきたのに、他の兄弟と同じ取り分なんて納得できない」
そんなときに登場するのが「寄与分(きよぶん)」という制度です。
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人がいた場合に、
その人の相続分を“上乗せ”してあげようという仕組みです。
▷ どんな行為が「寄与」にあたる?
- 長年にわたって親の介護をしていた
- 親の事業や農業を手伝い、収益を支えた
- 親の借金を返済したり、建物の修繕費を肩代わりした
- 高齢の親の生活全般を支え、施設に入れずに済んだ
→ これらの行為は、他の相続人にはできなかった“特別な貢献とみなされることがあります。
▷ どうやって「寄与分」が決まるの?
寄与分は自動的に認められるものではなく、
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則です。
もし話がまとまらない場合は、家庭裁判所に「寄与分の調停・審判」を申し立てて判断を仰ぐことになります。
▷ 注意点:どんな介護でも寄与分になるわけではない
寄与分が認められるには、「無償で」「継続的に」「特別な貢献をしたこと」が条件とされます。
たとえば、たまに様子を見に行ったり、買い物を代行した程度では、寄与分として評価されにくいのが実情です。
寄与分という制度を理解し、正しく主張することが大切です。
3.特別受益とは?すでに多くもらっていた人は減らされる

「弟は親からマンション購入費を援助してもらっていたのに、相続でも同じ取り分って不公平じゃない?」
そんな不満の背景にあるのが「特別受益(とくべつじゅえき)」という制度です。
特別受益とは、生前に被相続人から特別な援助(贈与)を受けていた相続人の取り分を調整する仕組みです。
要するに「すでに多くもらっていた人は、その分だけ相続分を減らしましょう」という考え方です。
▷ どんな援助が「特別受益」とみなされる?
- 結婚資金や持参金
- マイホームの購入援助金
- 学費や留学費用
- 開業・独立資金
- 高額な生前贈与など
これらは、通常の生活費の範囲を超えていると判断されるものです。
▷ 特別受益のある人はどうなる?
たとえば、相続財産が3,000万円あり、長男が生前に1,000万円の住宅援助を受けていたとします。
この場合、相続分を計算する際には:
- 相続財産を“実質4,000万円”とみなし
- そこから長男の取り分(2,000万円)を計算
- すでに1,000万円受け取っているため、相続時には残りの1,000万円のみを受け取れる
というように、既にもらった分を差し引いた上で平等を図るのです。
▷ 特別受益も「言わなければそのまま」になる?
はい、その通りです。
特別受益は自動的に考慮されるわけではなく、相続人が主張しなければ反映されません。
そのため、把握していないと「他の兄弟だけ得していた」と気づかぬまま終わってしまうこともあります。
このように、相続では「生前にもらっていたかどうか」「どれだけ親に尽くしたか」が、
相続分に大きく影響を与える可能性があるのです。
4.自分が「寄与分」「特別受益」に当てはまるか調べる方法
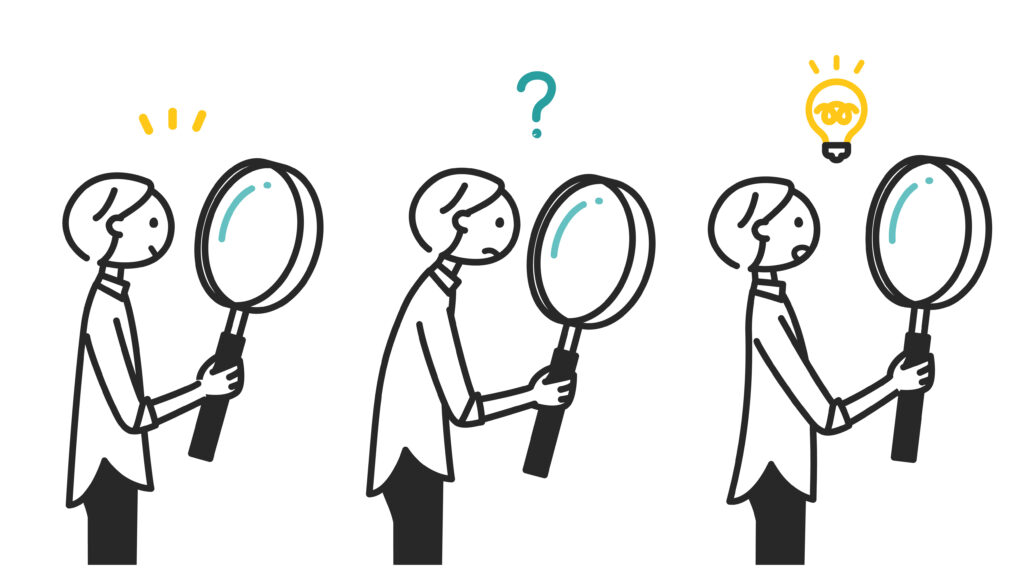
ここまで読んで、
「自分も寄与分が主張できるのでは?」
「あの兄弟は特別受益じゃないの?」
と思った方もいるかもしれません。
では実際に、自分や他の相続人がこれらの制度に当てはまるのかを確認するには、どうすればよいのでしょうか?
▷ 寄与分に当てはまる可能性がある人
以下のような経験がある場合、「寄与分」として相続分が増える可能性があります。
- 親の介護を無償で、長年続けていた
- 親の生活費を支えていた(年金では足りなかった)
- 親の事業を手伝って無給で働いていた
- 建物や土地の修繕費・借金の肩代わりなどで経済的に支えていた
→ ポイントは、他の兄弟にはできなかった「特別な貢献」であることです。
▷ 特別受益に当てはまる可能性がある人
以下のような援助を生前に親から受けていた人は、「特別受益」に該当する可能性があります。
- 親からマイホーム購入資金を援助された
- 結婚資金や持参金を受け取っていた
- 留学や私立の高額な学費を親が全額負担していた
- 事業資金を出してもらった
- 親名義の不動産を生前に無償で譲り受けていた
→ ポイントは、“他の兄弟にはない特別扱い”を受けていたかどうかです。
▷ 確信が持てない場合は、記録や会話を振り返ってみる
・介護の頻度や内容
・仕送りや贈与の記録(通帳・振込明細)
・当時の親とのやりとりや兄弟間の会話記録(LINE・メールなど)
これらの情報を整理することで、相続の取り分に影響しうる材料がないかを見極めやすくなります。
このように、自分や兄弟の行動・支援歴を振り返ってみることが、
「本来もらえるべき取り分」を確認する第一歩になります。
5.相続で損しないためにできること
相続でトラブルや不満を避けるためには、以下のような心がけが重要です。
- 事前に相続について家族で話し合い、「誰がどのように親を支えていたか」「どんな援助を受けたか」を共有しておく
- 他の相続人に寄与分や特別受益の主張があるかを把握する
- 制度に納得できない場合は、早めに専門家に相談する
6.まとめ:取り分が違うのは「仕組み」があるから
相続人の取り分に差が出るのは、「寄与分」や「特別受益」といった制度が存在するからです。
- 頑張った人には報いる「寄与分」
- すでに受け取っていた人は調整する「特別受益」
法律では「平等」が原則ですが、実際には“見えない不平等”を是正する仕組みがあるのです。
「自分だけもらえなかった」「取り分が少ない」と感じる前に、まずはその背景にある制度と理由を理解することが大切です。
もっと詳しく知りたい方は、ぜひ弊社の無料相談にお申し込みください!
あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。
\ この機会に是非ご登録ください! /