
仲の良い兄弟でも相続ではトラブルになります。
ふだんは穏やかで協力し合っていた兄弟姉妹でも、「お金」や「不動産」が関わると、思わぬすれ違いや感情のもつれが生まれることがあります。
たとえば、
「お兄ちゃんばかり得をしている気がする」
「昔から自分は損ばかりしてきた」
といった“過去の感情”がふと顔を出し、相続の話し合いがきっかけで関係がこじれてしまうことも少なくありません。
特に、親が遺言書を残していない場合は…
「誰が何をどれだけ受け取るか」を話し合いで決める必要があり、その過程で意見の食い違いや不信感が生まれやすくなります。さらに、相続には「不動産の分けにくさ」や「手続きの複雑さ」など、そもそも話し合いが難しくなる要因が多くあります。
このあと紹介する「よくある兄弟トラブルの事例」を知っておくことで、トラブル回避のヒントが得られます。
ケース1. 生前贈与の偏りで「不公平だ」と感じるケース

相続トラブルでよくあるのが、「生前に兄だけが車を買ってもらった」「妹は結婚時にまとまったお金を援助された」など、親からの支援に差があったことに対して他の兄弟姉妹が不満を抱くケースです。
こうした“見えない不公平感”は、普段は口に出されなくても、いざ相続の場面になると一気に噴き出します。
このような不満は、放置すると遺産分割協議が長引いたり、調停や訴訟にまで進んだりすることも。
トラブルを防ぐための対策
- 生前に贈与したことがあるなら、それを他の相続人にも共有しておく
- 親自身が元気なうちに遺言書を作成し、不動産や預貯金の分け方を明確にしておく
- 「感謝の気持ち」「お詫びの気持ち」など、言葉で伝えるだけでもトラブル予防につながる
“金額”よりも、“気持ちの整理”が重要なのが相続の特徴です。だからこそ、事前の配慮がカギになります。
弊社の実際の対策実例をご覧になりたい場合は

ケース2. 実家の不動産を誰が相続するかでもめるケース

相続の中でも特にトラブルが起こりやすいのが、「実家」の取り扱いです。
たとえば、兄が「親と同居して面倒を見てきたから、自分が相続すべきだ」と主張する一方で、
妹は「それなら代償金を払ってほしい」と反論する……というパターン。
不動産は現金のようにきっちり分けられないため、「誰が相続するか」「どうやって平等に分けるか」が非常に難しいのです。
よくある対立ポイント
- 「実家を売りたいvs住みたい」
- 「同居していた兄が全部もらうのはズルい」
- 「不動産の評価額や分け方に納得できない」
- 「固定資産税や維持費は誰が払うの?」
こうしたモヤモヤが積もると、感情的な対立に発展してしまいます。
実家の相続でやってはいけないことをピックアップした記事もございます
不動産をお持ちの方は必見です。

トラブルを防ぐための対策
- 遺言書や家族信託などで不動産の相続先を明確にしておく
- 不動産の評価額を事前に出して、他の相続人とのバランスを考える
- 売却して現金化し、平等に分ける方法も選択肢のひとつ
「実家」は思い出の詰まった大切な場所だからこそ、感情的になりやすい財産でもあります。
だからこそ、冷静に「どう分けるか」を話し合っておくことが重要です。
遺言書について詳しく知りたい方はコチラ
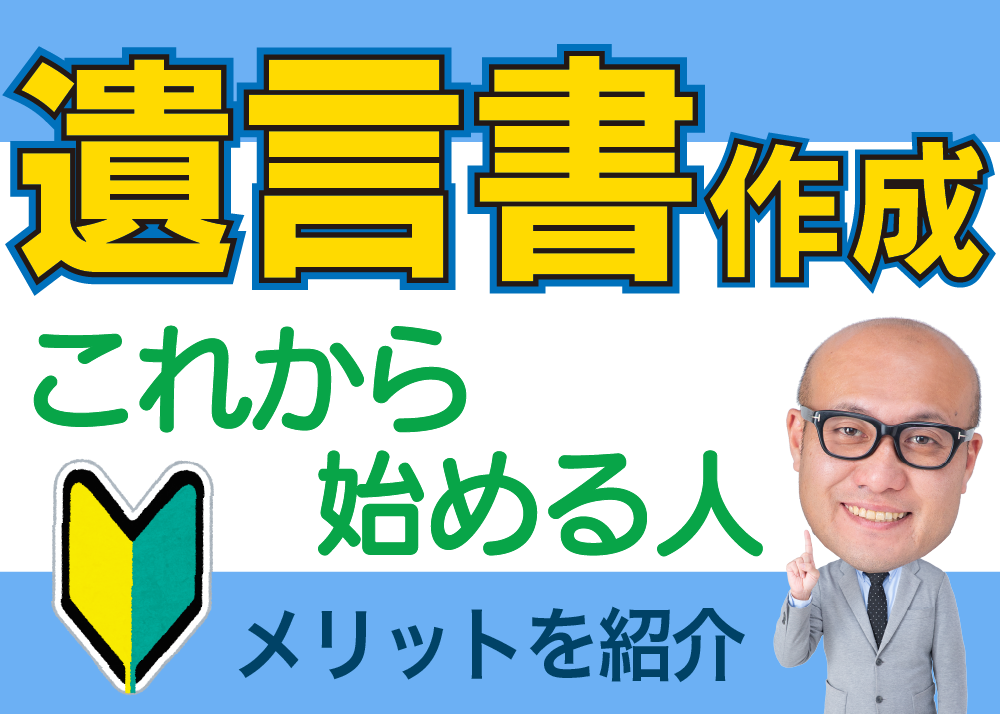
ケース3. 誰か一人が相続を進めたことで不信感が生まれるケース

相続手続きは複雑で手間がかかるため、兄弟姉妹のうち誰か一人が代表して動くこともよくあります。
しかし、「勝手に進められた」「私には何も相談がなかった」といった不満が後々トラブルに発展することも。
たとえ善意で動いていたとしても、他の相続人から見ると「自分に都合よく進めているのでは?」と疑念を抱かれやすいのです。
よくあるトラブルのきっかけ
- 財産内容や手続きの進捗を共有しなかった
- 書類にハンコを押すだけの状態になっていた
- 「なんで私には何の説明もないの?」という不満
こうした不信感は、小さなすれ違いからでも簡単に生まれてしまいます。
トラブルを防ぐための対策
- 相続手続きの段階ごとに、全員で情報を共有する
- 財産の内容は書面でまとめて全員に提示する
- 第三者である司法書士や専門家を間に入れることで、公平性を担保する
家族の間だからこそ、「ちゃんと話さなくてもわかってくれるはず」という思い込みが危険です。
少しの手間を惜しまないことが、兄弟関係を守る最大のポイントになります。
遺言執行者を利用すれば手続きする人を指定して、揉め事を回避することも可能です。
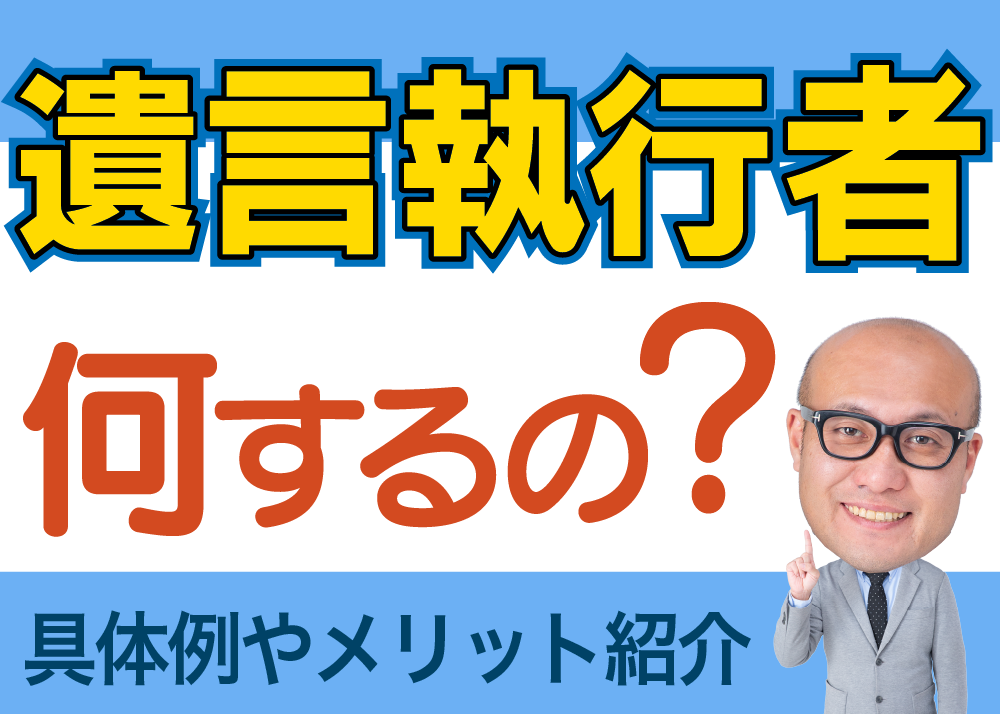
ケース4. 介護の負担に差があり、感情的な対立になるケース

相続トラブルの中でも、特に感情がもつれやすいのが「介護」に関する問題です。
例えば、実家の近くに住む妹が10年以上にわたって親の介護をしてきたのに、相続の場面で「法定相続分だから」と言って兄と折半にされた。そんな事例は決して珍しくありません。
介護には時間的・体力的・精神的な負担が伴います。にもかかわらず、
相続分にその「頑張り」が反映されないと、不満が爆発してしまいます。
よくあるトラブル例
- 「介護をしていない兄が、親の預貯金を当然のように半分要求してきた」
- 「私は病院の送迎や付き添いを続けてきたのに、兄は一度も顔を出さなかった」
- 「“親の面倒を見るのは当然”と言われて終わった」
感情的なトラブルを避けるための対策
- 介護の内容や期間、金銭的支出を記録しておく
- 相続人同士で事前に話し合い、「寄与分」の考え方を共有する
- 必要に応じて、専門家に相談する
介護はお金以上に「感謝されたい」「報われたい」という思いが強く出るテーマです。
だからこそ、「ちゃんと評価されなかった」と感じた瞬間に、兄弟関係が壊れてしまう可能性があります。
大切なのは、相続分を“単なる割合”ではなく、“家族の物語”として話し合うこと。
その一歩が、争族を防ぐ鍵になります。
専門家ごとに相談できる内容はことなってきます。下記記事にまとめております

ケース5. 相続人の一人が音信不通で手続きが進まないケース

相続手続きで意外と多いのが、「相続人の一人と連絡が取れない」というトラブルです。
例えば、兄弟の一人が昔から家族と疎遠で、今どこに住んでいるのかもわからない。
あるいは、連絡先はわかっているけれど、電話にも出ない、書類にも協力してくれない…。
実は、相続手続きは相続人全員の同意がなければ進められないものが多く、
1人でも同意してくれない、もしくは連絡がつかないと、全体がストップしてしまいます。
こうした状況では、他の相続人がイライラしたり、焦ったり、不公平に感じたりして、家族内の関係がますます悪化することも少なくありません。
ありがちな状況
- 「昔ケンカ別れした兄と20年近く連絡が取れていない」
- 「書類への署名をお願いしたのに、無視されてしまう」
- 「海外に住んでいて、手続きが大きく遅れている」
トラブルを回避するための対策
- 生前に親が「誰に何を遺すか」を明確にしておく(遺言書の作成など)
- 相続が発生したら早めに全員に連絡をとり、できる限り穏やかな話し合いを心がける
- どうしても進まない場合は、家庭裁判所での「不在者財産管理人」選任などの法的手続きも検討する
相続では「全員が揃わない=何も進まない」というケースも多いため、
「まさかうちは大丈夫」と思わず、早めに話し合いの土台を作っておくことが大切です。
まとめ|兄弟間の相続トラブルは「準備」で防げる
相続は、お金や不動産の問題だけでなく、「感情」や「家族関係」が深く関わってくるものです。
今回ご紹介したように、兄弟間で起こるトラブルには共通点があり、多くは「話し合い不足」や「準備不足」から始まっています。
特に以下のようなケースには注意が必要です。
- 生前贈与の偏りで「不公平だ」と感じる
- 実家の不動産を誰が相続するかで対立
- 相続手続きを誰か一人で進めたことで不信感が生まれる
- 介護の負担が偏っていて、感情的な衝突が起きる
- 音信不通の相続人がいて、手続きが進まない
しかし、これらのトラブルは「事前の準備」と「冷静な話し合い」で防げるものでもあります。
たとえば、遺言書を作っておく、家族で事前に相続について話し合っておく、
必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家に相談する――
そうした一歩が、後の大きな争いを避け、家族の絆を守ることにつながります。
「うちは大丈夫」と思っていても、相続は誰にでも起こる身近な問題です。
将来のために、今からできる準備を少しずつ始めていきましょう。
お気軽にLINEや電話でお問い合わせください
相続に関するご不安や疑問点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門家チームと連携しながら、最適な方法をご提案させていただきます。
 司法書士:本上
司法書士:本上お気軽にご相談ください!
自己紹介:本上崇(ほんじょう たかし)
皆様、はじめまして!
がもう相続相談センター代表の本上崇 ( ほんじょう たかし ) と申します。
簡単に自己紹介させていただきますと、 実は私、司法書士になる前は、プロサッカー選手を目指してブラジルに留学したり、お笑い芸人をしていたりと、少し変わった経歴の持ち主なんです。
「え、司法書士なのに?!」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。
でも、 これまでの経験を通して、どんな人とも “楽しく、わかりやすく” コミュニケーションをとることの大切さを学びました。
そして、その経験は、相続問題という複雑で、時にデリケートな問題を抱えたお客様と向き合う上で、大きな強みになっていると自負しています。
相続問題は、誰にとっても 不安や悩み がつきものです。「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが複雑そうで面倒だ」「費用がいくらかかるのか不安だ」…
そんな悩みを抱えたまま、一人で抱え込んでいませんか?
がもう相続相談センターは、「お客様に寄り添い、不安を解消し、笑顔になっていただく」ことを理念としています。
相続の専門家である司法書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて、わかりやすく丁寧 にご説明いたします。
- ・ご相談は何度でも無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- ・専門スタッフが親身になって対応いたしますのでご安心ください。
- ・「もっと早く相談すればよかった…」そう思っていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
がもう相続相談センターは、皆様の相続を、生涯にわたってサポートいたします。
まずはお気軽にご連絡ください!
代表司法書士 本上崇

