
相続は「不動産」が関わると一段と複雑になり、トラブルになる可能性も高くなります。
しかし、財産に不動産が含まれる以上、不動産の処理や対策は避けられません。
「なぜトラブルになるのか」「どう対策したらいいのか」を今の内に知っておくことで
未来のトラブルを回避しましょう
【今よく読まれています】認知症の対策をしたい方はこちらの記事がオススメです。
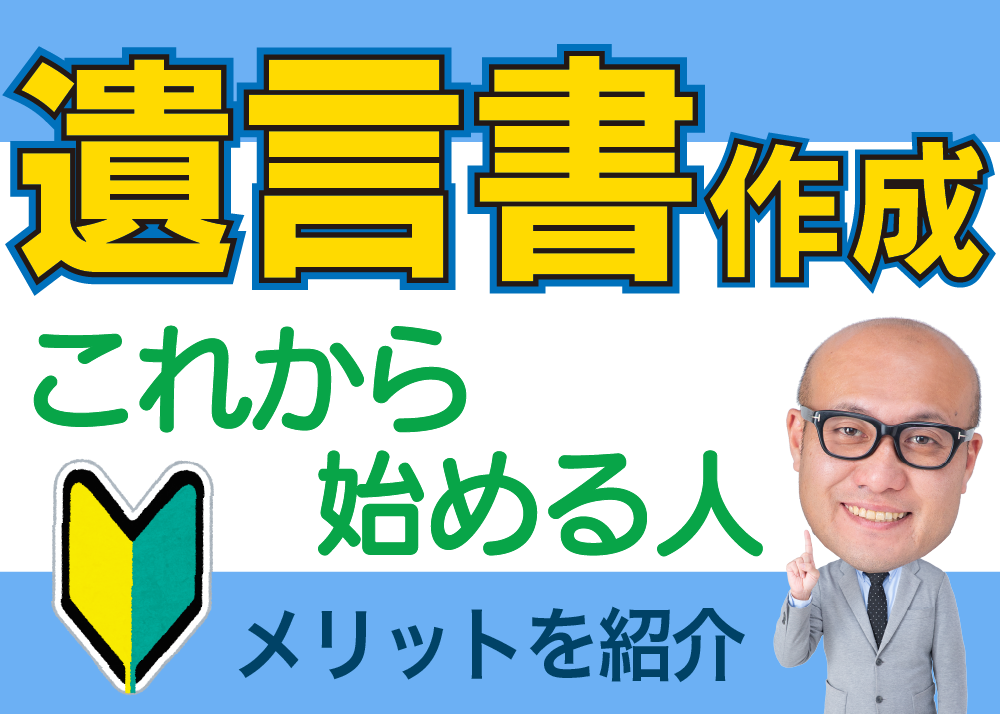
実家の相続はトラブルの火種になりやすい

不動産の相続は、分けにくい財産のため、トラブルの原因になりやすいものです。
兄弟間の不平等感や、相続手続きを後回しにすることで、思わぬトラブルが発生することもあります。
この記事では、実家の相続で「やってはいけない3つのこと」と、
その対策を解説します。
- 実家の相続で避けるべき失敗例
- 相続トラブルを防ぐ方法
- 早めの対策が重要な理由
① 不平等感を解消せずに実家を相続すること

相続で最も揉めやすいのが、兄弟間の「不公平感」です。
親が生前に特定の子に多く財産を与えていた場合、相続時にトラブルが起こりやすくなります。
特に、不動産のように簡単に分けられない財産が絡むと、感情的な対立に発展することが少なくありません。
よくあるケース
- 遺言書がないため、兄弟の間で相続割合について争いが発生する
親が「子どもたちが仲良く分ければいい」と考えていても、実際には意見が分かれ、争いに発展しがちです。
例えば、「長男が親と同居していたから実家は長男のもの」と考える人もいれば、「親の介護をしていたのは次男だから次男に相続させるべき」という主張が出ることもあります。 - 一部の相続人が生前に多くの財産を受け取っており、不満が募る
例えば、「長男だけが親から多額の援助を受けていた」「次女の結婚費用だけ親が負担していた」などの状況があると、他の兄弟姉妹から「不公平だ」と不満が出ることがあります。
こうしたケースでは、生前贈与された分を相続財産に加算して計算する「特別受益」のルールが適用されることがありますが、これが原因で話し合いが長引くこともあります。 - 実家の不動産価値が高く、現金化しないと公平に分けられない
実家の評価額が高いと、不動産を相続した人としなかった人の間で不公平感が生まれます。
たとえば、兄が実家を相続し、弟が現金を相続した場合、時間が経つにつれて不動産の価値が上がれば「兄だけが得をした」と考える人が出ることもあります。
また、不動産を相続しても維持費や固定資産税がかかるため、相続人が負担を感じることもあります。
①の対策
- 遺言書を作成し、不動産の処分方法を明確にする
遺言書があれば、親の意思が明確になるため、相続人同士の争いを防ぐことができます。
例えば、「長男に実家を相続させる代わりに、次男には預貯金を多めに分ける」「実家を売却し、得た現金を兄弟で均等に分配する」といった具体的な指示を書いておくことで、相続トラブルを回避できます。 - 実家を売却し、現金化して公平に分配する
不動産は簡単に分けられないため、売却して現金化することで、兄弟間の不平等感を減らせます。
例えば、1,500万円の価値がある実家を相続する代わりに、もう一方の相続人に750万円ずつ支払う「代償分割」を行う方法もあります。
また、「親の死後すぐに売却するのではなく、相続人全員が納得したタイミングで売却する」と決めておくのも有効な方法です。
遺言書作成についての詳しい情報は、下記よりご覧いただけます
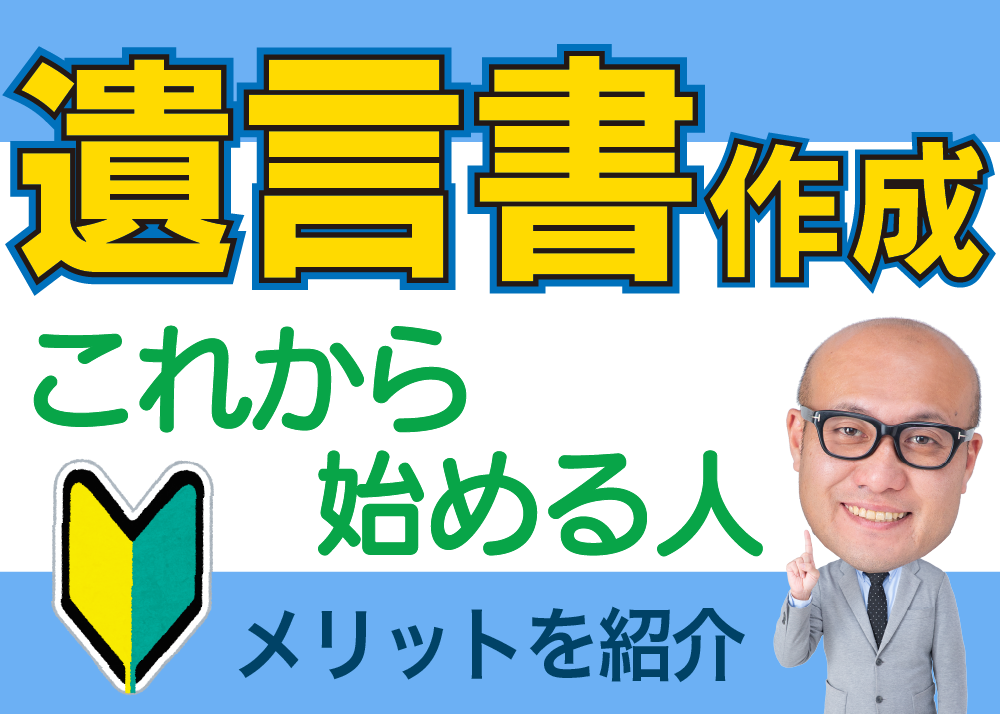
② 相続登記で共有名義にしてしまうこと

「兄弟で共有すれば円満に解決できる」と思いがちですが、共有名義にすると、
将来のトラブルの原因になりやすいため注意が必要です。
なぜ共有名義が危険なのか?
不動産を売却したり、賃貸に出したりする場合、共有者全員の同意が必要になります。
例えば、兄弟2人で共有している実家を売りたい場合、どちらか一方が反対すると売却ができません。
「今は売りたくない」「もっと高く売れるはずだ」といった意見の違いから、話し合いが進まず、長年塩漬け状態になることもあります。
兄弟が元気なうちはスムーズに話し合いができても、時間が経つにつれて関係が変わる可能性があります。
特に、結婚して配偶者の意見が入ると、「今すぐ売却して現金がほしい」「この家を貸し出して家賃収入を得たい」など、それぞれの事情が絡み、合意を取ることが難しくなります。
さらに、相続後に兄弟の関係が悪化すると、一切の話し合いができなくなるケースもあります。
例えば、兄弟2人で共有していた実家のうち、兄が亡くなった場合、兄の持ち分は兄の家族(配偶者や子ども)に相続されます。
こうなると、当初は兄弟2人の話し合いで済んでいたものが、兄の配偶者や子どもを含めた複数の相続人が関わることになり、意思決定がさらに困難になります。
最終的には、誰の判断もつかないまま放置され、売却も活用もできない負の遺産になってしまう可能性が高まります。
さらに詳しい共有名義のリスク解説は下記から!
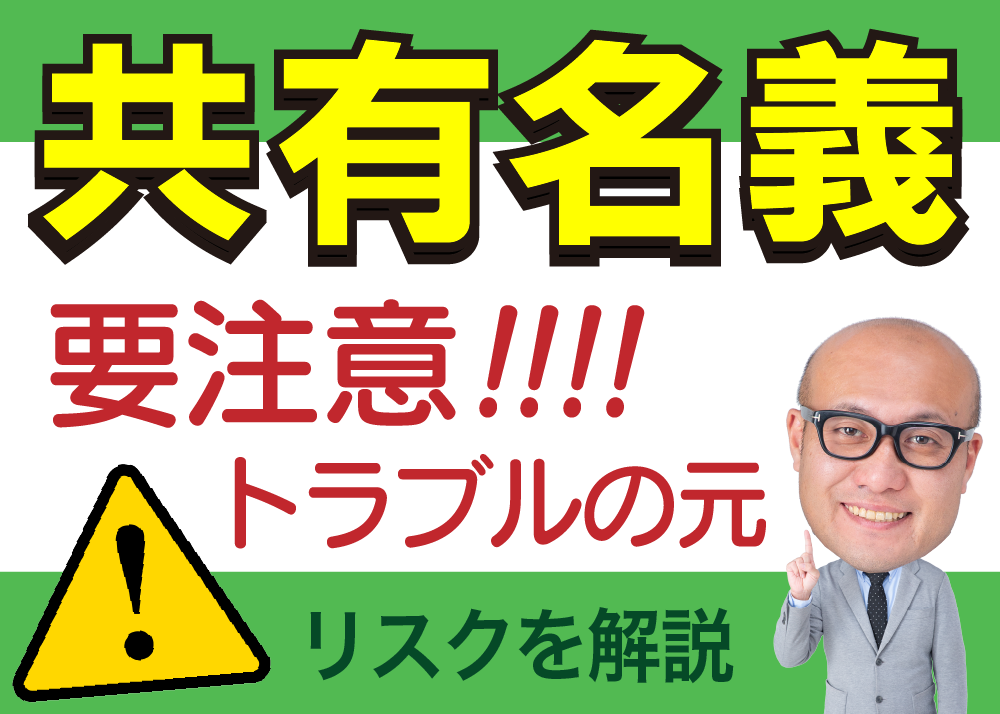
②の対策
共有名義にしないための対策として、以下の方法を検討しましょう。
- 兄弟のうち1人が単独で相続し、他の相続人に代償金を支払う(代償分割)
例えば、兄が実家を相続し、弟には相続分として現金を支払う方法です。
これにより、1人の意思で売却や活用ができるため、後々のトラブルを防げます。 - 実家を売却し、現金を公平に分ける(換価分割)
不動産は分けにくいため、売却してしまうことで兄弟間で公平に財産を分けることができます。
不動産の相続は専門的な知識が必要なため、自己判断せずに専門家に相談するのがベストです。
- 司法書士:相続登記の手続きや、共有名義を避けるためのサポート
- 税理士:相続税の計算や、売却する際の税務処理をアドバイス
- 不動産の専門家:売却の際の市場価値の査定、活用方法の提案
相続は一度決めると変更が難しいため、後悔しないためにも早めに専門家へ相談しましょう。
③ 処理を後回しにしてしまうこと

「特に急がなくても大丈夫」と考えて放置すると、後々大きな問題になる可能性があります。
相続は時間とともに手続きが複雑になり、知らないうちに経済的な負担が増えることも少なくありません。
放置することで発生するリスク
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
これにより、相続が発生してから3年以内に登記をしないと、最大10万円の過料が科される可能性があります。
また、登記がされていないまま時間が経つと、以下のような問題が発生することがあります。
- 共有者が増えて、権利関係が複雑になる
- いざ売却しようとしても、登記手続きに時間がかかる
- 行政から固定資産税の支払いを求められ、放置すると延滞金が発生する
相続登記の義務化に関してさらに詳しい情報については、下記ブログからご覧いただけます
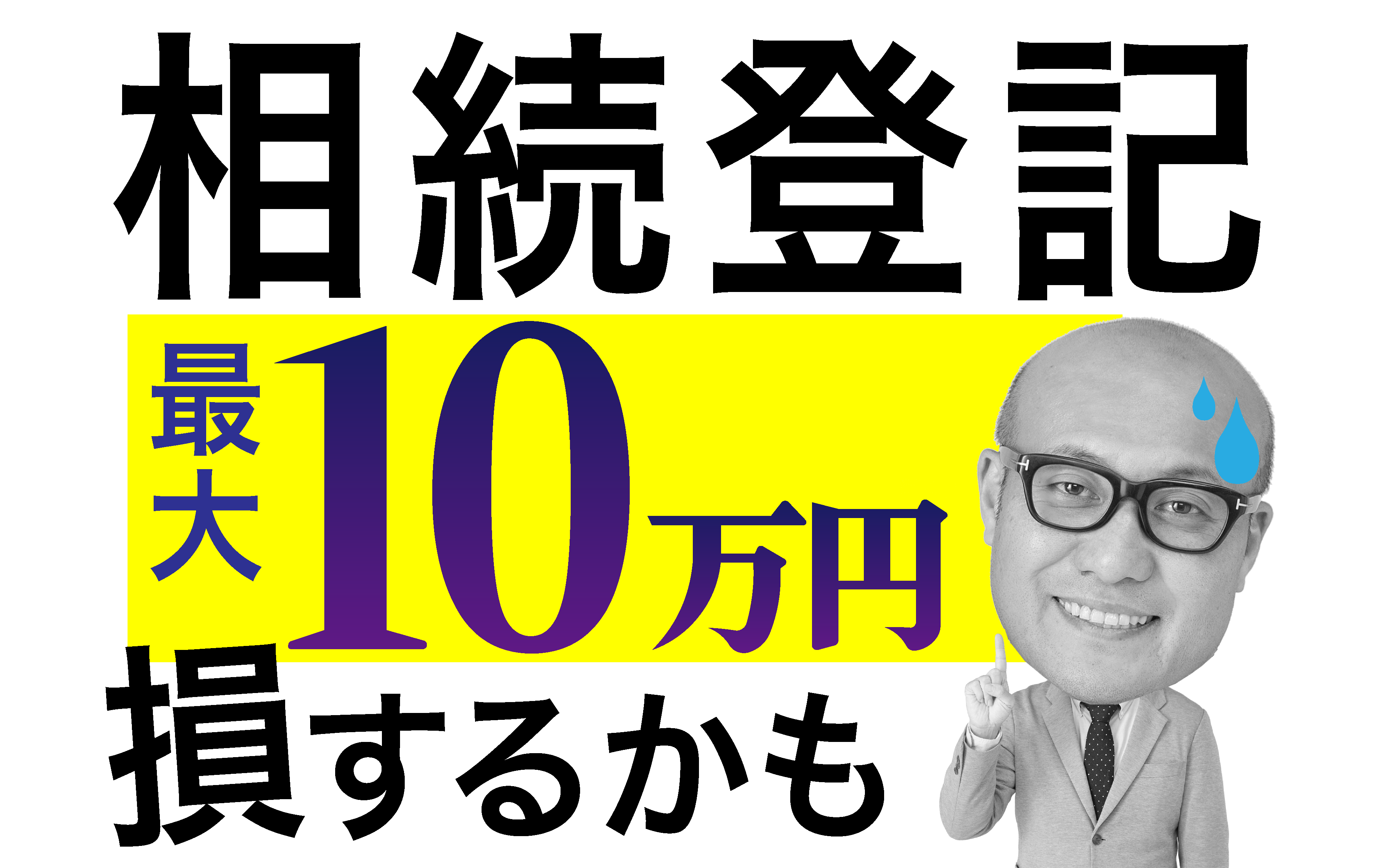
実家が空き家のまま放置されると、維持管理のためのコストがかかるだけでなく、固定資産税の負担が増えるリスクもあります。
特に注意すべき点
- 空き家が長期間放置されると「特定空き家」に指定される可能性がある
- 「特定空き家」に認定されると、固定資産税の優遇措置(住宅用地の軽減措置)が解除され、税額が最大6倍になる
- 放置期間が長くなるほど、解体や修繕の費用が増加する
例えば、「売却するかどうか決められない」と先延ばしにしているうちに、建物の老朽化が進み、売却時に解体費用が発生することもあります。
空き家のまま放置すると、建物の傷みが進み、売却時に大幅な値下げをしなければならなくなることがあります。
特に、築年数の古い住宅は早めに処分しないと市場価値が大きく下がるため注意が必要です。
また、空き家を長期間放置すると、近隣住民に迷惑がかかるケースもあります。
- 雑草が伸び放題になり、景観を損なう
- 建物の老朽化による倒壊リスク
- 不法投棄や空き巣被害の発生
このような問題が発生すると、自治体から改善指導や強制撤去の命令を受けることもあり、最終的には所有者の責任で対応しなければならなくなります。
空き家対策のさらに詳しい情報については、下記ブログからご覧いただけます
③の対策
相続が発生したら、できるだけ早く相続登記を行い、名義を確定させることが重要です。
特に、複数の相続人がいる場合、話し合いが長引くことで手続きが遅れるケースが多いため、早めに手をつけることが大切です。
- 遺産分割協議を早めに行い、名義変更を済ませる
- 必要書類をそろえ、専門家(司法書士など)に相談する
実家を放置せず、有効活用する方法を考えることも重要です。
- 売却する → 早めに売却することで、資産価値が下がる前に現金化できる
- 賃貸に出す → 賃貸収入を得ることで、固定資産税や維持費の負担を軽減できる
- リフォームして活用する → 空き家バンクやシェアハウスとしての活用も可能
どの方法が適しているかは、相続人の意向や実家の立地条件によるため、専門家に相談しながら検討することがベストです。
実家の相続で失敗しないために今すぐできること
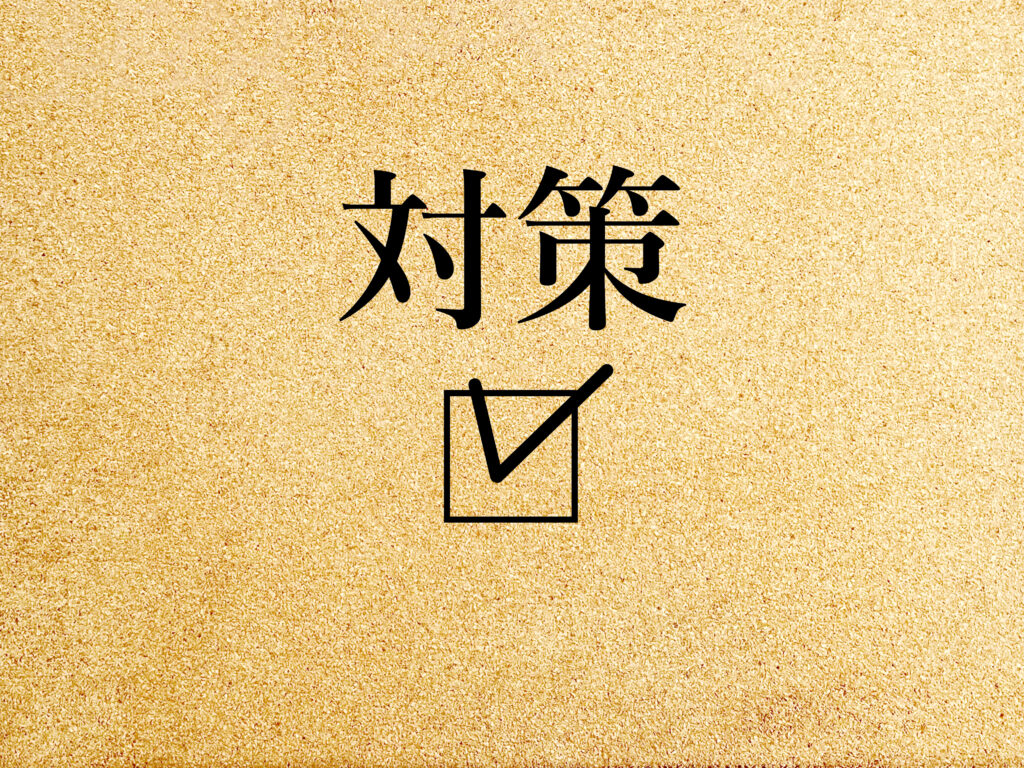
まずは家族で相続について話し合っておく
実家の相続でトラブルを避けるために、最も大切なのは家族で話し合うことです。
相続の話は「縁起が悪い」と思われがちですが、何も決めないまま親が亡くなると、兄弟間で意見が食い違い、大きな問題になる可能性があります。
話し合いのポイント
- 誰が実家を引き継ぐのか(誰かが住むのか、売却するのか)
- 不動産の評価額や維持費について知っておく
- 親がどんな考えを持っているのか確認する(遺言書があるかどうか)
相続の話は感情が絡みやすいため、冷静に話せるタイミングで進めることが重要です。
迷ったら相続の専門家(司法書士・行政書士・税理士)に相談する
相続の手続きは、法律や税金の知識が必要になるため、専門家に相談するのが最も確実な方法です。
特に、実家の相続には次のような問題が絡むことが多く、自己判断で進めるのは危険です。
専門家に相談すべきケース
- 遺言書がなく、どう分けるべきかわからない
- 不動産の評価額がわからず、相続税が発生するか不明
- 兄弟で共有にするか、売却するかで意見が分かれている
※相続は一度決まるとやり直しが難しいため、早めに専門家のアドバイスを受けることが重要です。
早めの相続対策でトラブルを回避する
相続の手続きを後回しにすると、時間が経つほど問題が複雑になります。
特に実家のような不動産は、対策が遅れると売却や活用が難しくなることもあります。
早めにできる相続対策
- 親が元気なうちに遺言書を作成してもらう
- 相続登記を期限内に行う(義務化されているため放置はNG)
- 実家をどうするか、家族で方向性を決めておく
不動産の相続は、事前の準備がスムーズな手続きを左右します。
「まだ大丈夫」と思わず、できることから始めておきましょう。
お気軽にLINEや電話でお問い合わせください
相続に関するご不安や疑問点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門家チームと連携しながら、最適な方法をご提案させていただきます。
 司法書士:本上
司法書士:本上お気軽にご相談ください!
自己紹介:本上崇(ほんじょう たかし)
皆様、はじめまして!
がもう相続相談センター代表の本上崇 ( ほんじょう たかし ) と申します。
簡単に自己紹介させていただきますと、 実は私、司法書士になる前は、プロサッカー選手を目指してブラジルに留学したり、お笑い芸人をしていたりと、少し変わった経歴の持ち主なんです。
「え、司法書士なのに?!」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。
でも、 これまでの経験を通して、どんな人とも “楽しく、わかりやすく” コミュニケーションをとることの大切さを学びました。
そして、その経験は、相続問題という複雑で、時にデリケートな問題を抱えたお客様と向き合う上で、大きな強みになっていると自負しています。
相続問題は、誰にとっても 不安や悩み がつきものです。「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが複雑そうで面倒だ」「費用がいくらかかるのか不安だ」…
そんな悩みを抱えたまま、一人で抱え込んでいませんか?
がもう相続相談センターは、「お客様に寄り添い、不安を解消し、笑顔になっていただく」ことを理念としています。
相続の専門家である司法書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて、わかりやすく丁寧 にご説明いたします。
- ・ご相談は何度でも無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- ・専門スタッフが親身になって対応いたしますのでご安心ください。
- ・「もっと早く相談すればよかった…」そう思っていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
がもう相続相談センターは、皆様の相続を、生涯にわたってサポートいたします。
まずはお気軽にご連絡ください!
代表司法書士 本上崇


