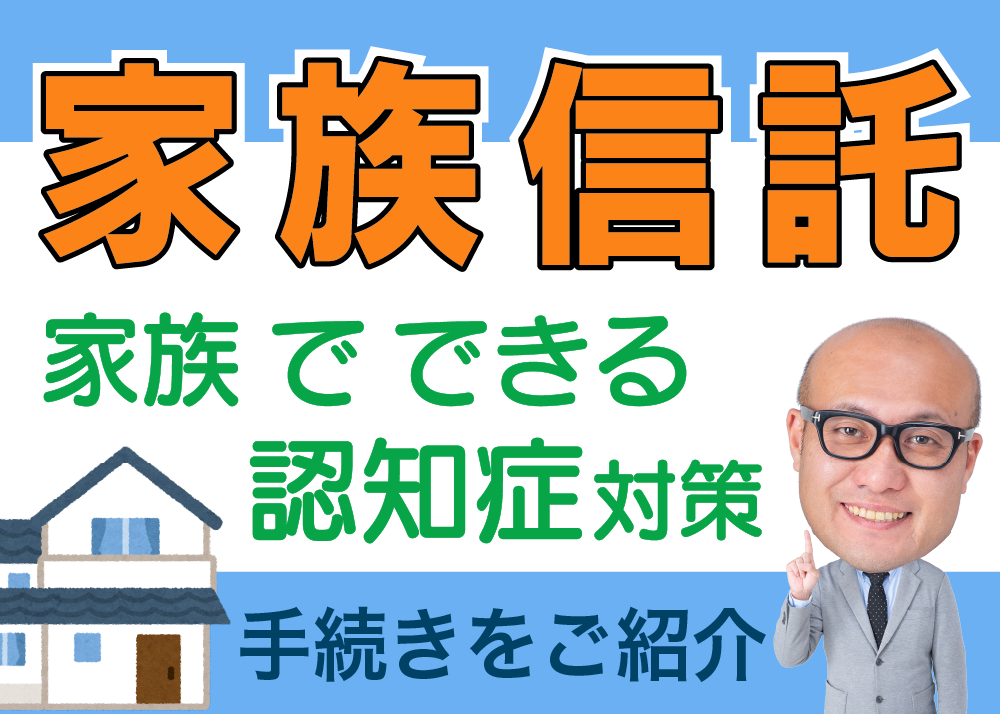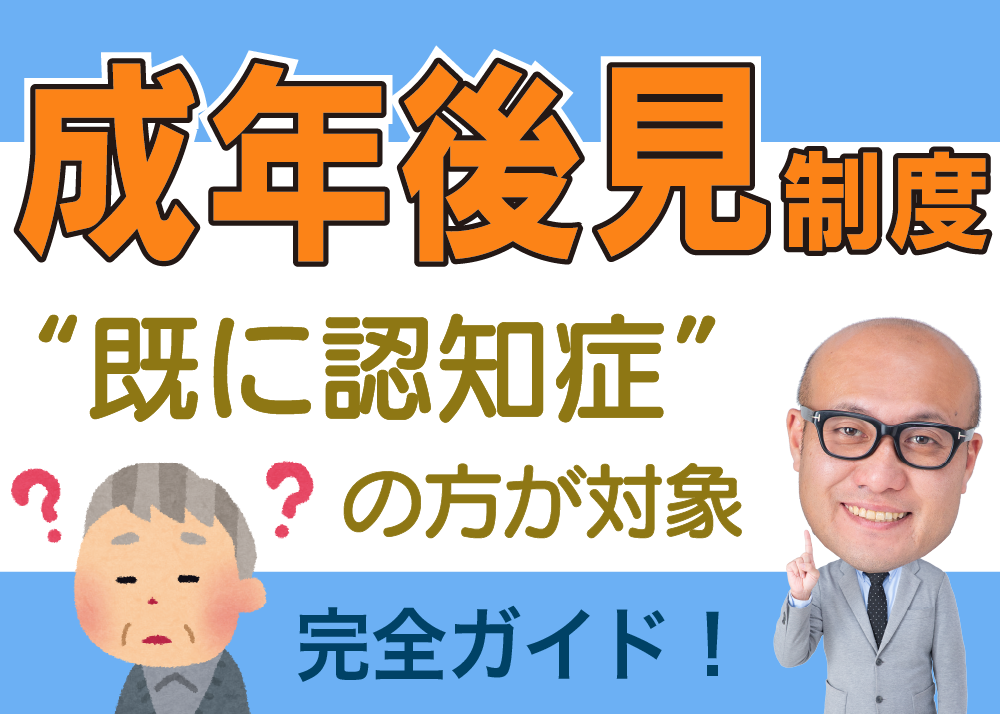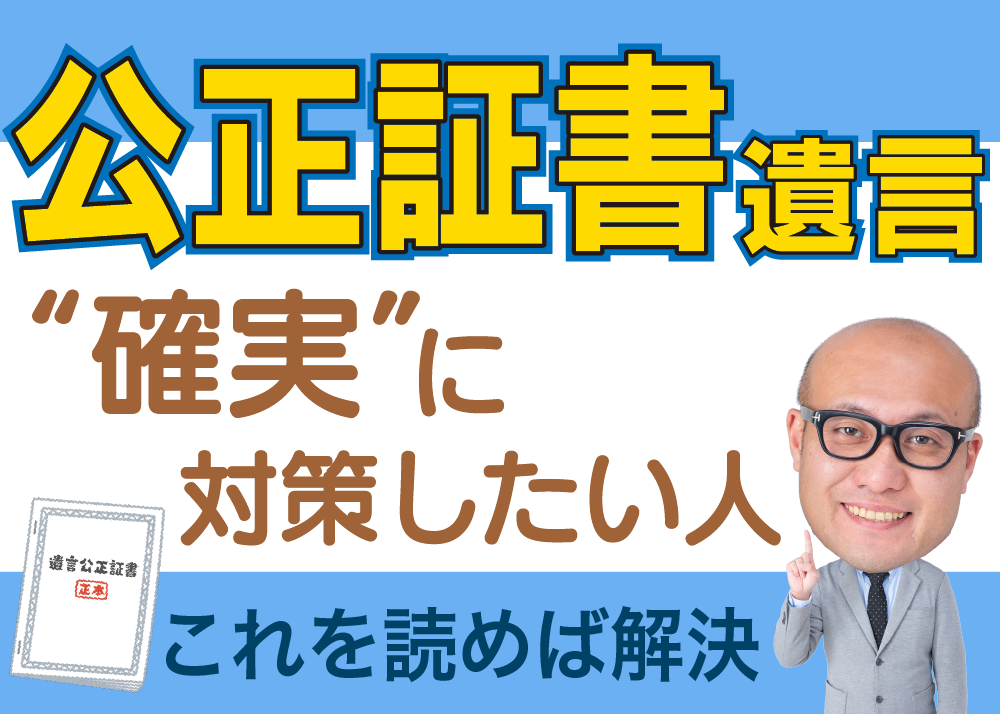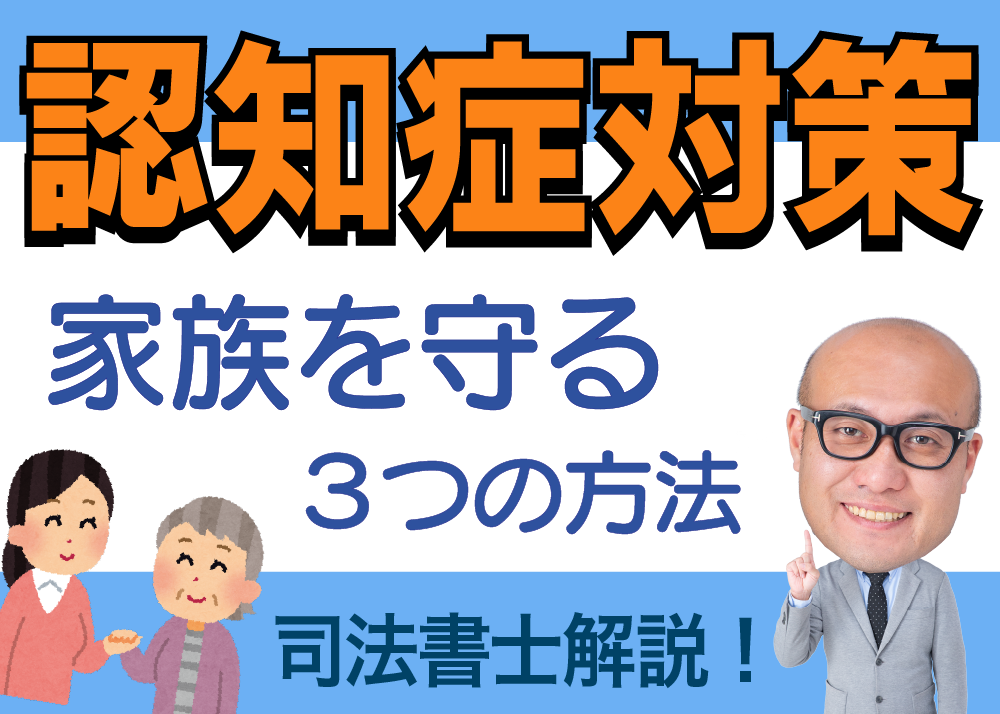
「認知症なんてまだ先の話」と思っていませんか?
しかし、実際には認知症の初期症状が現れると、財産の管理や相続の準備が格段に難しくなります。
例えば、認知症が進行すれば本人の意思確認ができなくなり、
銀行口座の凍結や、不動産の売却が困難になるケースも少なくありません。
さらに、準備不足が原因で家族間に深刻なトラブルが生じることもあります。
代表的な3つの認知症対策
・任意後見制度
・家族信託
・成年後見制度
上記の3つが代表的な認知症対策です。
本当はもっと色々な対策がありますが、こちらの記事では3つを中心にご紹介させていただきます。
ではまず、認知症になると相続が大変になる理由からご説明します。
認知症で相続が大変になる理由
認知症対策を行わなかった場合、次のようなトラブルが起きることがあります。
- 財産凍結:銀行口座や不動産が動かせず、相続が停滞する。期限つきの相続手続きに遅れる。
- 家族間の争い:財産分配を巡る意見の相違が、深刻な対立を引き起こす。
- 手続きの遅延:様々な手続きに時間がかかり、緊急対応ができなくなる。
事態が深刻化すると家族間でトラブルになり、調停や裁判に発展するケースもあります。
被相続人が認知症になった場合(生前対策が大変)
被相続人(財産を渡す側)の認知症が進行すると、財産に関する意思決定を行えなくなることがあります。
その結果、遺言書を作成できない、あるいは財産の管理が滞るといった問題が発生します。
例えば、銀行口座の凍結や、不動産の売却ができない状況に陥ることも。
早い段階で家族信託や成年後見制度を活用することで、こうしたリスクを軽減できます。
相続人が認知症になった場合(相続手続きが大変)
相続人(財産を貰う側)の中に認知症の方がいる場合、その方の法定相続分に関する意思表示が必要です。
しかし、意思能力が認められないと、成年後見制度が必要になり、手続きが複雑化します。
これにより相続全体が遅延し、家族間のストレスやトラブルが増加する可能性があります。
認知症の進行前に準備した方がいい理由
認知症が進行して意思能力が失われると、本人の希望を反映した財産管理が難しくなります。
早い段階で任意後見人を選任したり、遺言書を作成することで、本人の意思を尊重した財産分配が可能になります。
また、認知症の進行前に家族会議を開くことで、家族全員が対策について合意しやすくなります。
①任意後見制度とは?
任意後見制度とは、認知症などで判断能力が低下する前に、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)を選び、財産や生活に関する管理を委託する制度です。
この制度は、公正証書によって契約内容を明確にし、本人が元気なうちに準備できる点が特徴です。
任意後見契約は、将来的な安心を確保するために重要な選択肢となります。
任意後見の特徴と使えるタイミング、オススメの人
特徴
- 事前準備が必要:判断能力が低下する前に契約する必要があります。
- 本人の意思を尊重:任意後見契約により、誰に何を任せるかを自分で決められます。
- 柔軟な管理内容:財産管理だけでなく、生活支援なども含められるため、
個別のニーズに応じた内容が設定可能です。
使えるタイミング
- 認知症の兆候が出る前に契約する必要があります。
具体的には、50代~60代の間に検討するケースが一般的です。
オススメの人
- 認知症の進行リスクが心配な人
- 財産を自分の意思で管理したいと考えている人
- 家族間でトラブルを防ぎたいと考える人
さらに詳しい解説は別記事にてご紹介しております。下記をご覧くださいませ。
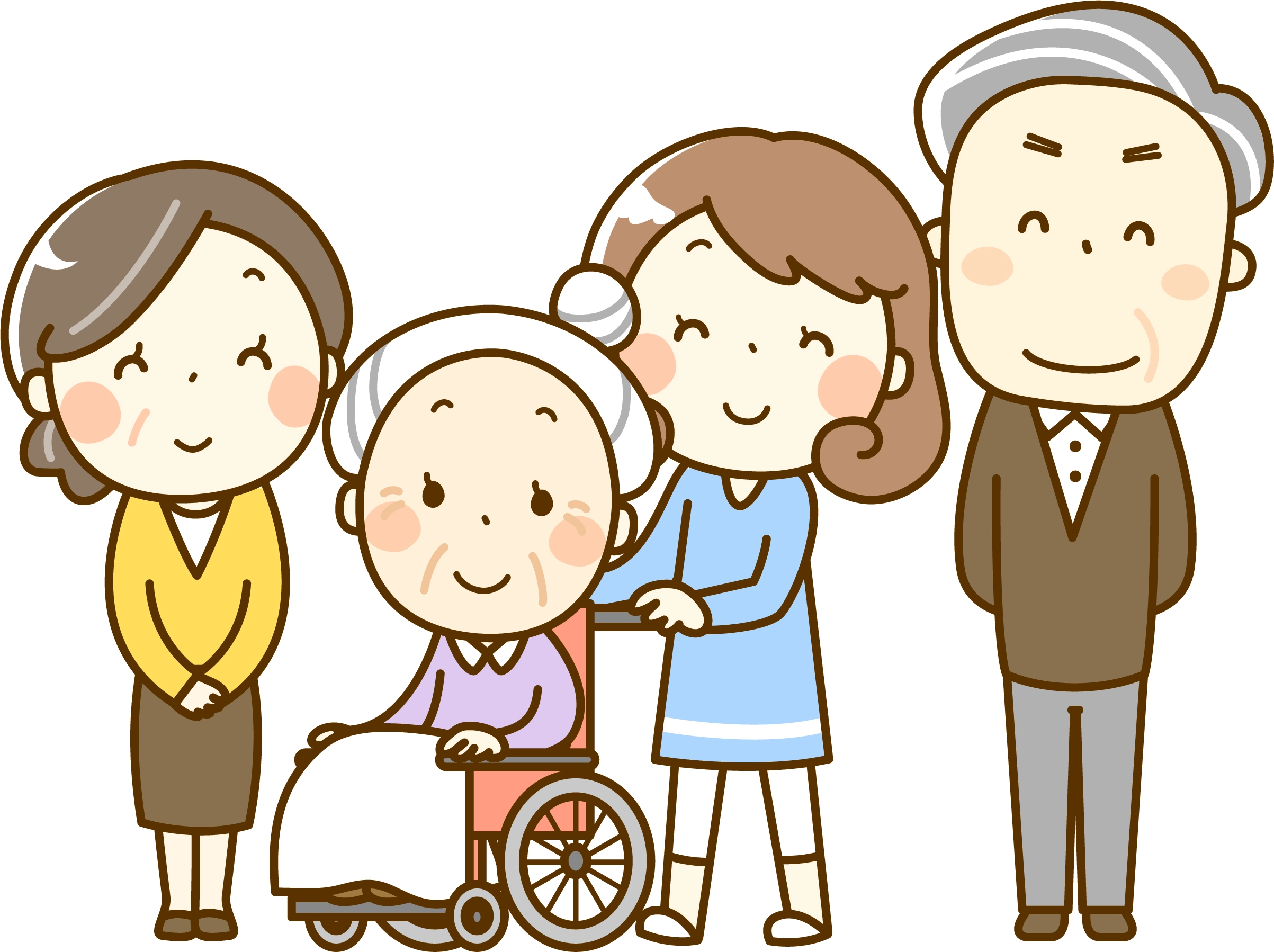
②家族信託とは?
家族信託とは、財産の所有者が信頼できる家族(受託者)に対して財産の管理、運用、処分を委託する仕組みです。
この制度は、認知症などで判断能力が低下した際にも、財産が凍結されることなくスムーズに管理や処分が行える点が特徴です。
例えば、不動産や預貯金の管理、生活費の捻出など、財産を「誰が」「どのように」管理するかをあらかじめ設定できるため、トラブルの回避につながります。
家族信託の特徴と使えるタイミング、オススメの人
特徴
- 柔軟性のある財産管理
家族信託では、契約内容を自由に設定できるため、個々の事情に応じた対策が可能です。 - 財産凍結の回避
判断能力が低下しても、受託者がスムーズに財産を管理できるため、相続や日常生活における経済的な停滞が防げます。 - 遺言書と併用可能
家族信託は財産の「管理」に特化しており、遺言書と併用することで、相続全体の計画を立てやすくなります。
使えるタイミング
- 認知症が進行する前
財産所有者が判断能力を持っている間に契約を結ぶ必要があります。 - 不動産管理が必要な場合
不動産の処分や賃貸など、具体的な運用が求められる財産がある場合に適しています。
オススメの人
- 認知症のリスクが高い人
高齢者や認知症の初期症状が見られる人にとって有効な制度です。 - 財産が複雑な人
複数の不動産や多額の預貯金を所有し、管理が煩雑になりがちな人に適しています。 - 家族間のトラブルを避けたい人
遺産分割の争いを未然に防ぎ、家族全員が納得する形で財産を管理したい人に最適です。
さらに詳しい解説は別記事にてご紹介しております。下記をご覧くださいませ
③成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで既に判断能力が低下した人を法的に支援するための制度です。
この制度を利用することで、本人の財産や権利が適切に保護され、財産の管理や契約手続きがスムーズに進められます。
日本では家庭裁判所の審判を経て、後見人が選任されます。
成年後見制度の特徴と使えるタイミング、オススメの人
特徴
- 法的保護が強力
成年後見制度は法律に基づいて運用されるため、財産の不正利用や不適切な契約を防ぐ効果があります。 - 家庭裁判所が後見人を選任
家族だけでなく、弁護士や司法書士などの専門職が後見人になる場合もあり、信頼性が確保されます。 - 財産管理だけでなく生活支援も可能
財産の管理に加え、医療や介護サービスの契約などもサポートします。
使えるタイミング
- 判断能力が低下してから
成年後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用できます。認知症が進行した後でも、後見人が財産や生活の管理を適切に行えます。 - 大きな契約や財産の管理が必要なとき
不動産の売却や大規模な介護契約が必要な場合に役立ちます。
オススメの人
- 判断能力が低下した親族を支援したい人
認知症や障害により財産管理が難しくなった親族を適切にサポートしたい場合に有効です。 - 法的にしっかりした保護を求める人
家族だけでは対応が難しい場合に、専門職や裁判所の支援を受けたい人に向いています。 - 信頼できる専門家を活用したい人
後見人として専門家を選ぶことで、透明性の高い財産管理が期待できます。
さらに詳しい解説は別記事にてご紹介しております。下記をご覧くださいませ
その他の認知症対策について
他にも様々な対策があります。
これまで紹介した3つの対策に加え、下記の対策を組み合わせて併用するとより確かな認知症対策になります。
※制度によっては併用できないものもあります。(例:任意後見と成年後見など)
生前贈与
生前贈与は、認知症が進行する前に財産を相続人へ分配する方法です。相続発生後のトラブルを減らし、相続税対策としても有効です。
公正証書遺言
公証役場で作成される遺言書で、法律的な有効性が高く、偽造や紛失のリスクが少ない特徴を持った遺言書です。正確に遺言書を作成したい人にオススメです。
見守り契約
高齢者の日常生活を見守るための契約で、認知症の進行状況に応じて適切な支援が受けられます。任意後見を開始するタイミングを見極めてもらう際にも役立ちます。
財産管理委任契約
病気やケガで身体が思い通りにいかなくなったときに、自分の財産管理を第三者に委任する契約です。
死後事務委任契約
自分が亡くなった後の事務手続きを第三者に委任する契約です。葬儀や遺品整理、相続手続きなどをスムーズに進めることができます。
認知症対策は併用がオススメ!
ここまで読んでいただいた方はもうお分かりかと思いますが、認知症対策には様々な手法があります。
そして、これらを単独で利用するよりも、状況に応じて複数の対策を併用することで、より強固な対策になることを覚えておいてください。
併用するには専門知識が必要になってきますので、しっかりと効果的に対策したい方は、まずは専門家の無料相談などで専門家のアドバイスを受けるのが得策でしょう。
まとめ:認知症対策は今が始めどき!
認知症対策は、認知症が進行して意思能力が低下してからでは遅すぎます。
特に、財産が凍結されてしまうリスクや家族間のトラブルを防ぐためには、早めの準備が重要です。
今すぐできる第一歩として、専門家に相談し、自分や家族の状況に合った最適な対策を考えましょう。
家族信託や成年後見制度、生前贈与などの併用を視野に入れ、柔軟に対策を進めることが安心できる未来への近道です。
お気軽にLINEや電話でお問い合わせください
相続に関するご不安や疑問点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門家チームと連携しながら、最適な方法をご提案させていただきます。
 司法書士:本上
司法書士:本上お気軽にご相談ください!
自己紹介:本上崇(ほんじょう たかし)
皆様、はじめまして!
がもう相続相談センター代表の本上崇 ( ほんじょう たかし ) と申します。
簡単に自己紹介させていただきますと、 実は私、司法書士になる前は、プロサッカー選手を目指してブラジルに留学したり、お笑い芸人をしていたりと、少し変わった経歴の持ち主なんです。
「え、司法書士なのに?!」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。
でも、 これまでの経験を通して、どんな人とも “楽しく、わかりやすく” コミュニケーションをとることの大切さを学びました。
そして、その経験は、相続問題という複雑で、時にデリケートな問題を抱えたお客様と向き合う上で、大きな強みになっていると自負しています。
相続問題は、誰にとっても 不安や悩み がつきものです。「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが複雑そうで面倒だ」「費用がいくらかかるのか不安だ」…
そんな悩みを抱えたまま、一人で抱え込んでいませんか?
がもう相続相談センターは、「お客様に寄り添い、不安を解消し、笑顔になっていただく」ことを理念としています。
相続の専門家である司法書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて、わかりやすく丁寧 にご説明いたします。
- ・ご相談は何度でも無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- ・専門スタッフが親身になって対応いたしますのでご安心ください。
- ・「もっと早く相談すればよかった…」そう思っていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
がもう相続相談センターは、皆様の相続を、生涯にわたってサポートいたします。
まずはお気軽にご連絡ください!
代表司法書士 本上崇