皆様こんばんみ!(懐かしい挨拶ですね♡)
がもう相続相談センターの司法書士のほんじょうです。
もう令和5年。
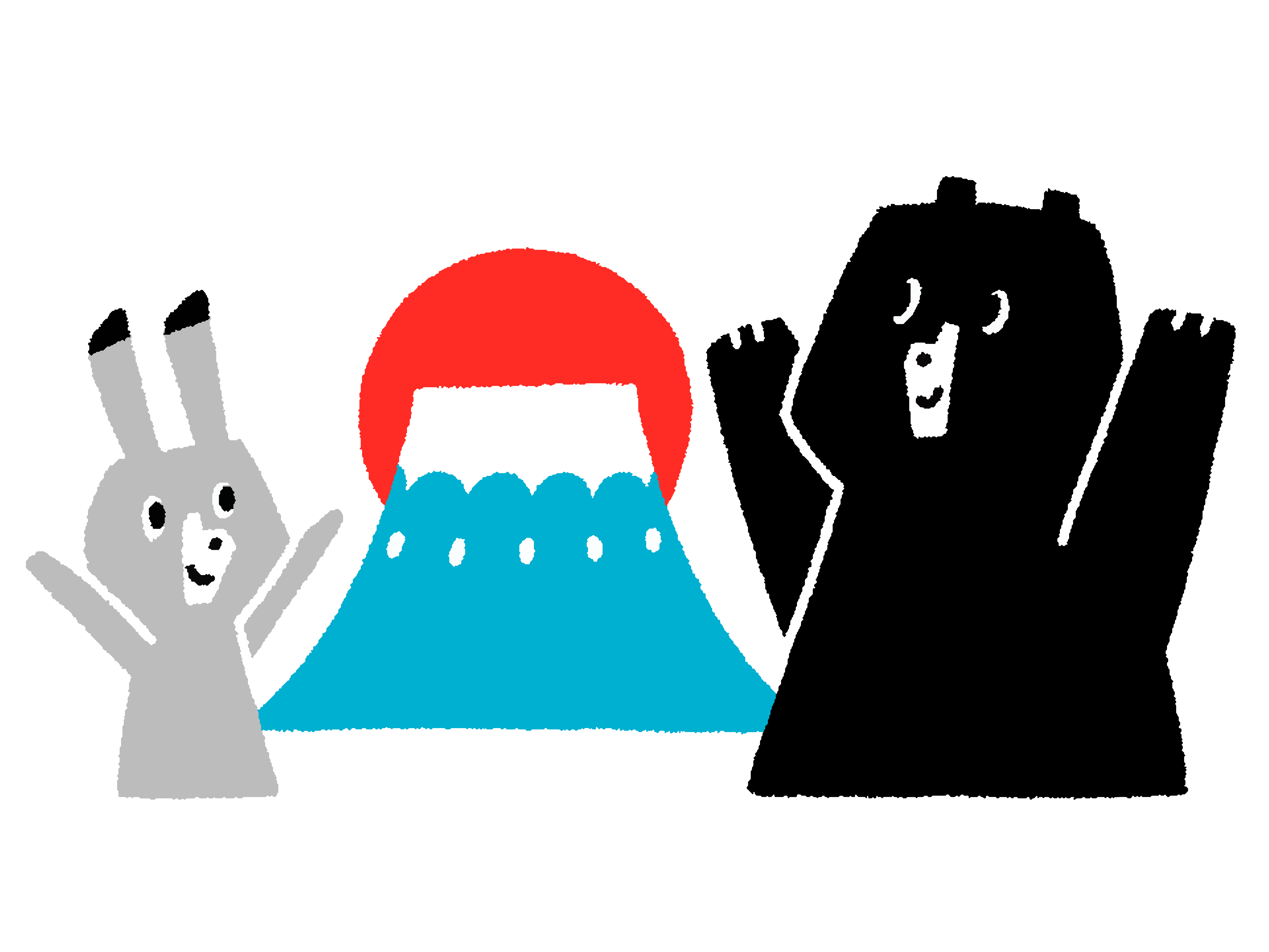
はやっ!言うてる間に1月も終わりそうです。
さて!今日のお話しは、贈与税改正についてです!
今年税法の改正があって、2024年4月1日から開始なんですが、現在の法律では、相続人に対する生前贈与が、お亡くなりになる直前3年分は、相続財産に含まれるとなっているんですが、それが7年まで遡るというお話しなんです。
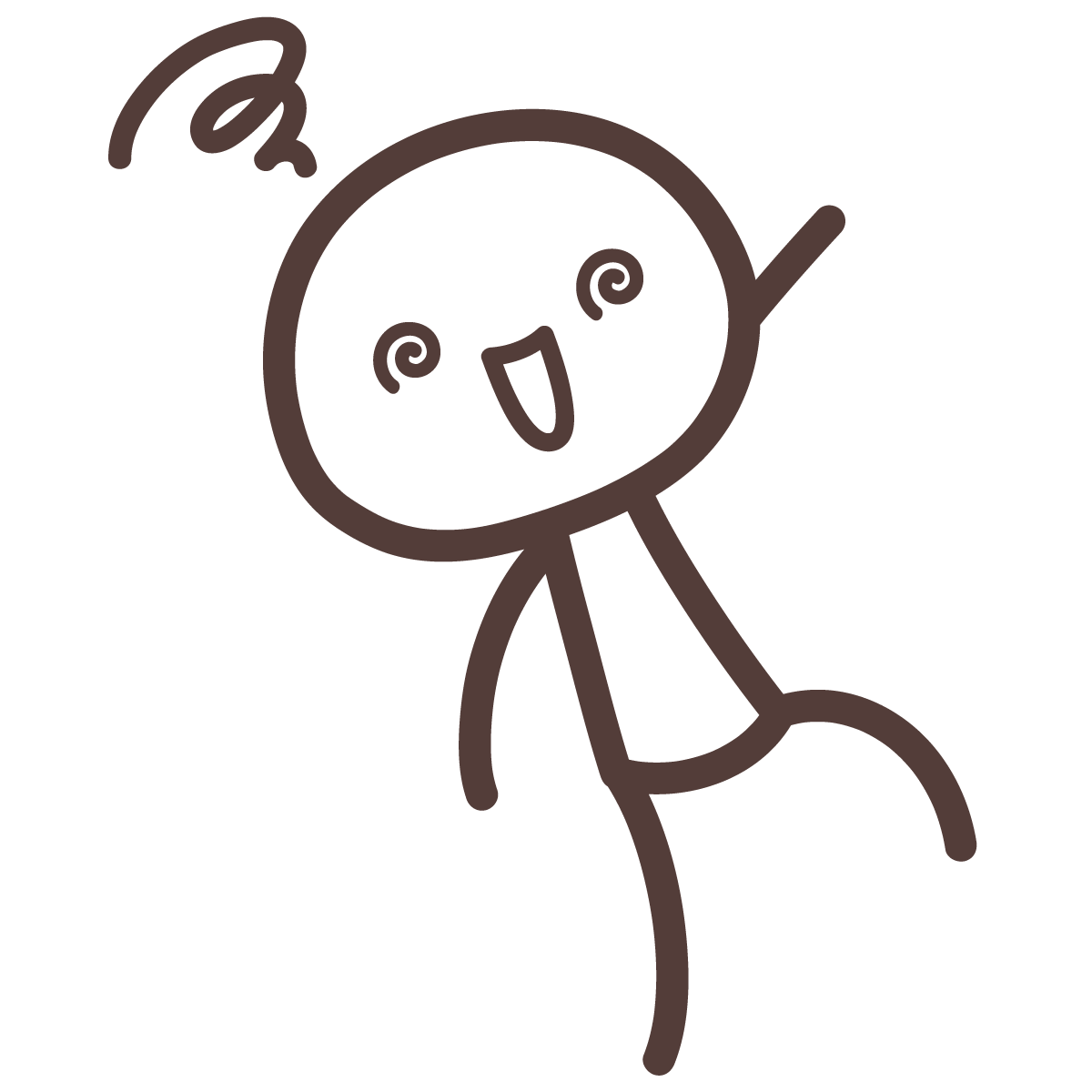
/ やめて~~ \
では!! その制度改正についてお話ししていきます。レッツゴー♪
令和5年相続税改正で生前贈与加算が7年に
生前贈与って、相続、ようはお亡くなりになった後の「遺産相続→相続税」とは関係ないのでは、と思っている方も多いと思います。
ただ、現行では、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象になります。これを、「生前贈与加算」といいます。
この生前贈与加算が改定され、2024年4月1日以降の贈与から、7年に延長されます。結果的に、相続税計算上の相続財産が増えることになり、相続税の増税となります。
また、延長した4年分については、総額100万円まで相続財産に加算しません。
なかなか、ややこしいですが、2024年1月1日以降の相続から、急に7年前の贈与が生前加算されるという意味ではないんです。
2024年1月1日以降の生前贈与から、この贈与税改正の対象になる、ということです。

相続税と贈与税の一体化
ではまず、相続税と贈与税の一体化について簡単に触れます。
年間110万円以下の贈与は、贈与税がかかりません。
もし110万円を超えても、贈与金額がそれほど高額でなければ税率が低いです。そのため、毎年、少しずつ贈与すれば、相続税対策になります。
ただ、そうすると、相続税対策のために、亡くなる時期が近づいたら、たくさん贈与して、相続税を節税しようとする人が増えてしまいます。
そこで、相続開始前の一定の期間の贈与については、相続財産に加算して相続税を課税します(「生前贈与加算」)。これは、少額でも課税対象になり、今までは3年間だけでしたが、今回の改定で7年に延長されることとなりました。

生前贈与加算の期間を延長する理由
生前贈与の期間が延長される背景ですが、日本の贈与税率は最高55%と、贈与税が高額なので、贈与する人が少ないです。
そのため、高齢者に資産が集中し、若い世代へ資産の移転が進まないことが大きな社会問題となっています。
そこで、相続税と贈与税を分けずに、いつ贈与しても、財産に同じ金額の税金がかかるようにすれば、贈与をしやすくなると考えました。この議論は、「相続税と贈与税の一体化」と呼ばれ、税法の改正へとつながりました。

贈与税と相続税
贈与税は相続税の補完的な役割を持っています。
現在、「贈与税法」というものは、ありません。贈与税は「相続税法」の中に記載されています。これからもわかるように、ある意味、相続税と贈与税は今でも一体なのです。
ところが、相続税と贈与税は課税されるタイミングや税率が異なるため、実態は別々の税金のようになっています。そのため、生前贈与をすることで相続税を減らすことが可能になっています。
生前贈与による相続税対策の仕組み
相続税と贈与税の一体化の目的を理解するためには、生前贈与による相続税対策の仕組みを理解しておく必要があります。
生前贈与をしない場合、所有している資産が、そのまま相続財産となり、そこに相続税がかかります。
もし、生前贈与をすると、その分、相続財産が減ります。よって、相続税が減ることになります。一方で、生前贈与した金額によっては、贈与税がかかってきます。
贈与税は、一般的に相続税より高いと認識しておいてください。
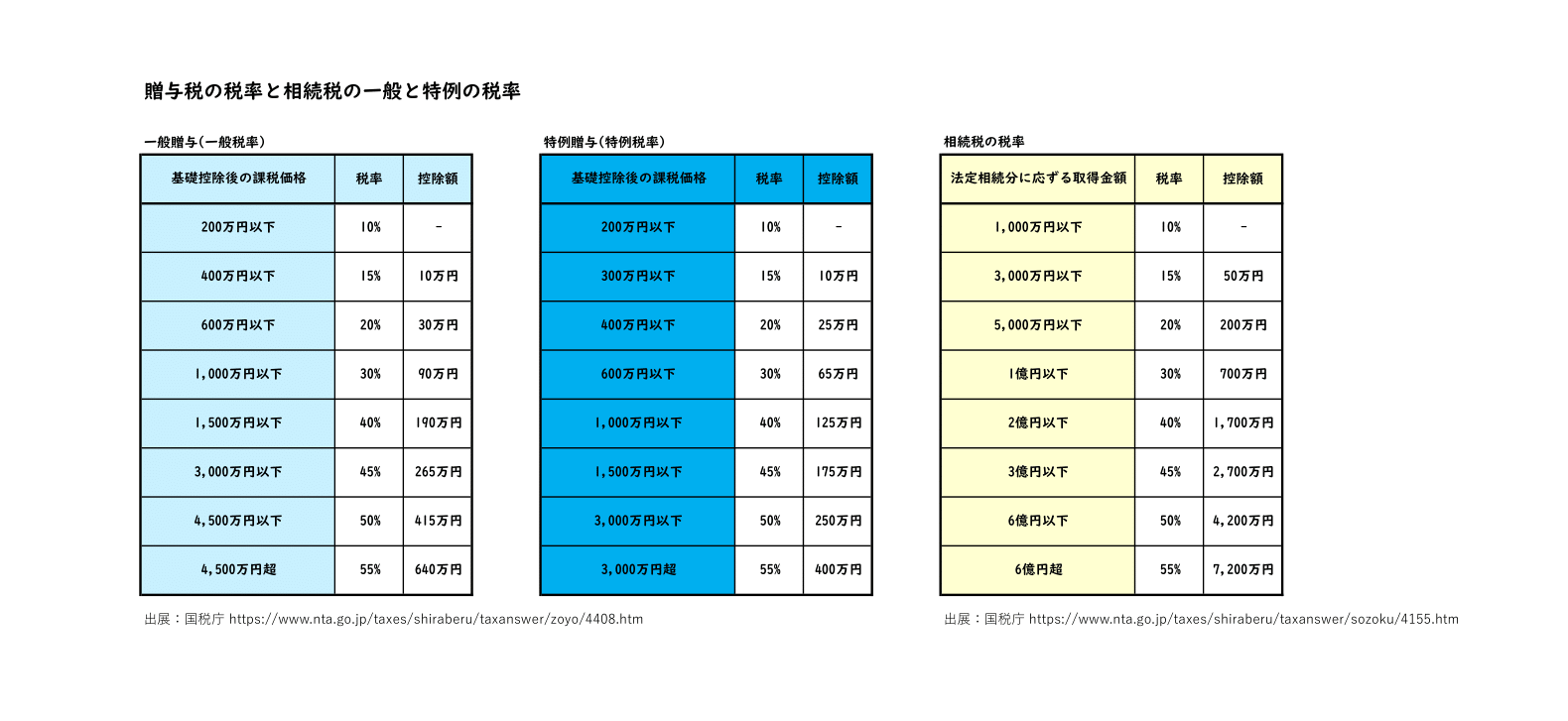
さて、今回の税法改正は、なぜ3年から7年変更されるのか。なんで、7年なんだと思いませんか?
この7年という期間は、外国の税法を参考にしました。
参考にしたのは、イギリスです。
イギリスが7年なので、日本も3年から7年に変更しようと考えたのです。
アメリカは、一生涯
フランスは、15年
ドイツは、10年
イギリスは、7年
そして、日本は、3年となっています。
今回の改正案として、5年、7年、10年、15年、生涯と、いろいろな案が出ていました。
たくさん議論がなされ、まずは、イギリスの7年と同じにすることになりました。
おそらく、一気に期間を10年、15年と長くすると、影響が大きくなると考え、それを防ぐために7年としたのだと推測されます。

相続税改正の議論の背景
内閣府のホームページをみると、相続税・贈与税に関する専門家会合が開かれていたことがわかります。
昨年10月に3回も開かれていて、かなりハイペースであるのが感じとれますね。
議事録や会議資料も掲載されているのですが、第3回目の資料は非公開となっています。
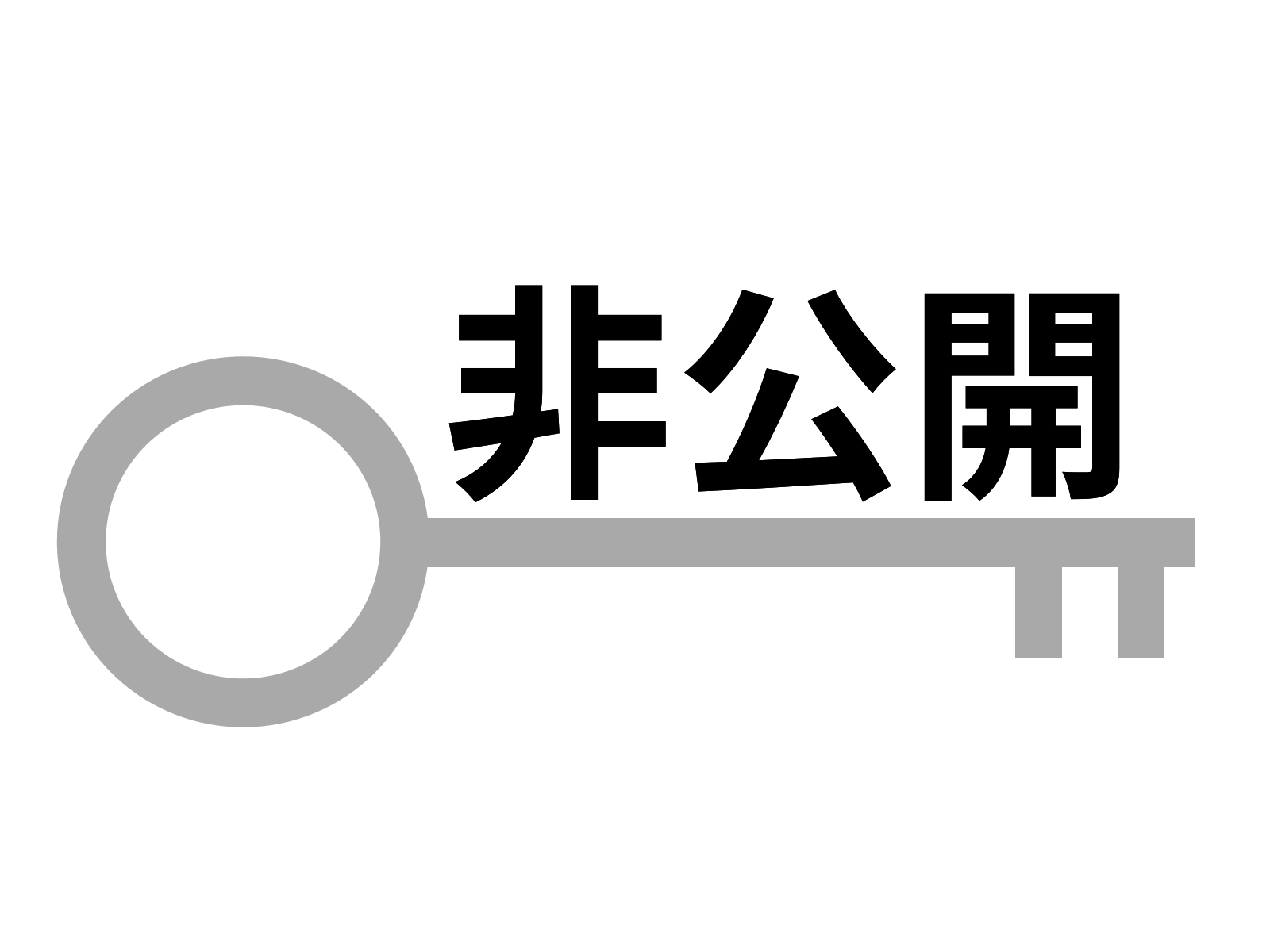
若い世代への資産移転が進まない
2019年時点で個人の金融資産は1900兆円とかなりの金額ですが、60歳以上が65%を持っています。
人口の半分以上が60歳以上ですね。
少子高齢化が進み、ここ20年間で、70歳以上も増え、その資産が急増している状況です。
最近発生している相続の多くは、80歳以上の人から50歳以上の人への、いわば、高齢者から高齢者への相続です。そのため、若い世代への資産移転が進まないことが問題となっています。

若い世代への資産移転が進まないと将来の日本が貧しくなる
若い世代へ、資産移転が進まないと、一体どうなるのでしょうか?
親の年収が高いほど子どもの大学進学率が高く、学歴が高いほど生涯賃金が多い、というデータがあります。逆にいうと、年収の低い家庭の子どもは学歴が低く、生涯賃金も低くて、その次の世代も同じく収入の低い傾向があることを示しています。
親の年収が高いほど子どもの学力が高い、というデータもあります。
そして親が貧しければ、子どもの学力もあがらないとされています。このデータでもわかるように、今の若い親世代が貧しければ、将来の日本がますます貧しくなってしまうのです。
そのため、若い世代への資産移転が必要だという風潮になっています。

欧米では贈与するタイミングに関わらず、同じ税額
アメリカ、フランス、ドイツでは、いつ贈与しても、しなくても、相続・贈与にかかる税金は同じです。だから、贈与しやすく、若い世代へ資産が渡りやすいとされています。
しかし、日本では、贈与をすると高額な贈与税がかかりますので、なかなか若い世代へ資産が渡らないのが現状です。

生前贈与加算延長への対策
贈与税について詳しくお話をしてきましたが、今回行われる生前贈与加算延長において、何か対策が、あるのでしょうか。
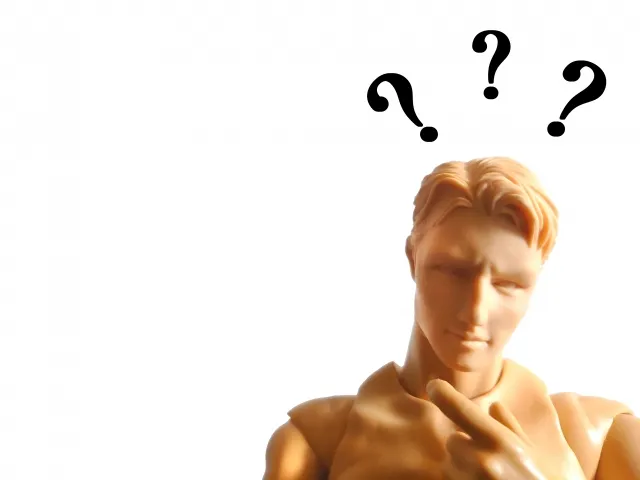
2023年までに生前贈与を
3年が7年延長に適用されるのは、2024年1月以降の贈与からです。
ということは、2023年12月31日までの贈与は今までどおり、3年間しか加算されません。
残された期間はあと1年(この原稿執筆時点)。
死期がそう遠くないと思われている方は、少し贈与税を払ったとしても、2023年中に贈与をしておくと良いと思います。

お孫様への生前贈与
生前贈与加算の対象は、相続人(財産をもらう人)です。相続人以外は対象になりません。
それなら、相続人ではない子の配偶者などに贈与すれば問題ありません(子の配偶者、内縁の妻、親戚への贈与もOKです。)。
ここで気を付けたいのでは、孫が財産をもらうことです。
孫が遺言書で財産をもらったり、生命保険金を受け取ると、生前贈与加算の対象になってしまいます。
孫への贈与ですが、抜け道がありますので、本来の目的を果たせません。これも将来的にはNGとなる可能性もあるので、頭に入れておいたほうが良いでしょう。
また、それでも孫へ贈与したいときは、名義預金に要注意です。
名義預金とは、子どもや孫の名義の口座に振り込んでいるのですが、その通帳や印鑑を、贈与している人が手元に持っている状態のことです。子どもや孫は、自分の口座のお金を自由に使えないばかりか、ひどいと、自分の口座の存在さえ知らないこともあります。
これでは、贈与とはみなされず、すべて相続財産になってしまい、相続税がかかります。期間制限はありませんので、過去何十年間にわたって贈与したつもりだったとしても、すべて否定されてしまいます。贈与契約書を作成したうえで、通帳や印鑑は、必ず子どもや孫が持つようにしましょう。
今までお話ししてきた内容の2024年4月1日から施工です。
なので、その間に生前贈与を出来る方は、早くにお手続きされた方がいいと思います。生前贈与をご検討の方は、ブログを見てお近くの相続相談センターにご相談ください。

お気軽にLINEや電話でお問い合わせください
相続に関するご不安や疑問点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門家チームと連携しながら、最適な方法をご提案させていただきます。
「税務相談をご希望のお客様は、弊社定型の税理士の先生をご紹介させていただきます」
 司法書士:本上
司法書士:本上お気軽にご相談ください!
自己紹介:本上崇(ほんじょう たかし)
皆様、はじめまして!
がもう相続相談センター代表の本上崇 ( ほんじょう たかし ) と申します。
簡単に自己紹介させていただきますと、 実は私、司法書士になる前は、プロサッカー選手を目指してブラジルに留学したり、お笑い芸人をしていたりと、少し変わった経歴の持ち主なんです。
「え、司法書士なのに?!」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。
でも、 これまでの経験を通して、どんな人とも “楽しく、わかりやすく” コミュニケーションをとることの大切さを学びました。
そして、その経験は、相続問題という複雑で、時にデリケートな問題を抱えたお客様と向き合う上で、大きな強みになっていると自負しています。
相続問題は、誰にとっても 不安や悩み がつきものです。「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが複雑そうで面倒だ」「費用がいくらかかるのか不安だ」…
そんな悩みを抱えたまま、一人で抱え込んでいませんか?
がもう相続相談センターは、「お客様に寄り添い、不安を解消し、笑顔になっていただく」ことを理念としています。
相続の専門家である司法書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて、わかりやすく丁寧 にご説明いたします。
- ・ご相談は何度でも無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- ・専門スタッフが親身になって対応いたしますのでご安心ください。
- ・「もっと早く相談すればよかった…」そう思っていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
がもう相続相談センターは、皆様の相続を、生涯にわたってサポートいたします。
まずはお気軽にご連絡ください!
代表司法書士 本上崇

