
親の様子が「少し変だな」と感じ始めると、不安になりますよね。
同じ言葉を繰り返したり、忘れ物が増えたり。
こんな時、 認知症と相続の問題を考えておくことをオススメします。
親が認知症になると、単に介護の負担が増えるだけではありません。
相続の場面でも、想像以上に厄介な事態が起こります。
遺産分割が進まない、預金が下ろせない、家の売却ができない。
そして、それらの原因の多くが「判断能力の低下」によって、法律上“本人の意思確認ができない状態”になることです。
こんな疑問はありませんか?
・認知症になると相続では何が困るのか?
・どこまで進むと手続きが止まるのか?
・家族ができる準備は何なのか?
・まだ軽度のうちに、やっておくべきことは何か?
そんな不安を整理しながら、今日から動ける5つの対策をまとめます。
どれも難しい言葉を先に出さず、状況とやる理由が自然に理解できるように書いています。
1. 親の財産の「全体像」をつかむ
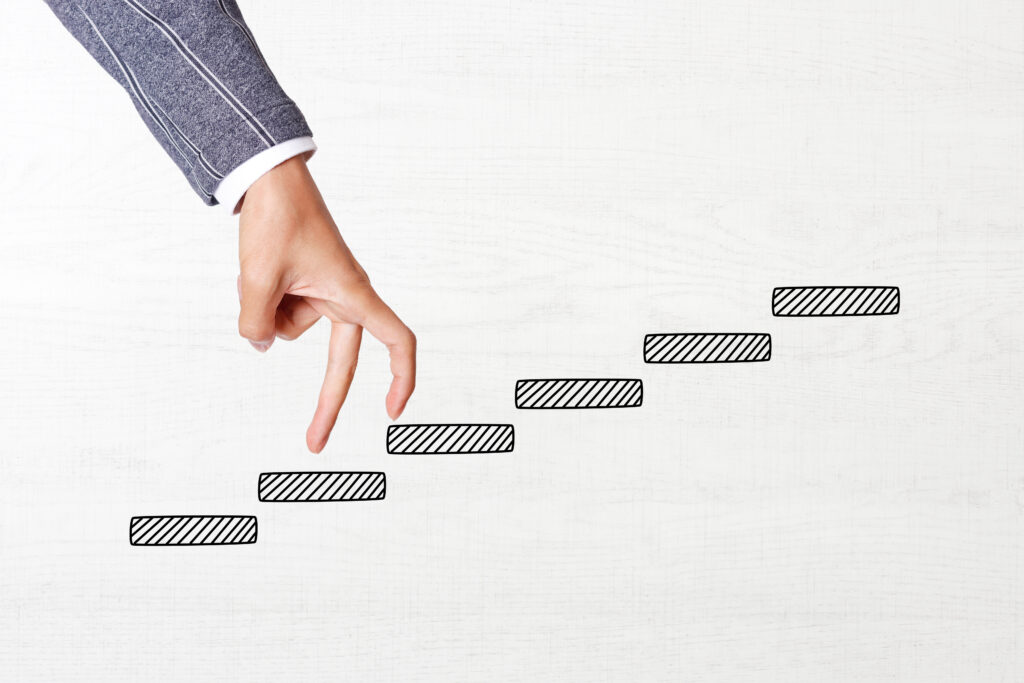
どこに何があるかわからないと相続で必ず詰まる
認知症によるトラブルで一番多いのが、財産の所在がわからない という問題です。
預金通帳だけでなく、ネット銀行、証券口座、保険、借入、土地、建物。
誰も場所を知らないまま親の判断能力が落ちてしまうと、家族は“探しようがない状態”に追い込まれます。
銀行は家族であっても勝手に照会できません。
仮に亡くなっても、相続人の代表が戸籍一式を揃え、金融機関ごとに手続きしなければなりません。
親が生きている間はさらに複雑で“本人の意思確認”が必須です。
判断能力が落ちると、口座凍結と同じ状態になります。
こんな状況を避けるために、軽い物忘れの段階から
・預金(銀行名・支店名)
・通帳やカードの保管場所
・証券や保険
・固定資産(自宅・土地)
・借金の有無
など、「一覧」を作っておくことが大切です。
紙でもエクセルでも構いません。
場所だけでも聞いておくだけで、相続の時に“ゼロからの探索”をしなくて済みます。
親に聞きにくい場合のコツ
「相続のため」ではなく、「もし入院した時に困らないように」と伝えると話しやすくなります。
いきなり全てを聞こうとせず、家の中の棚の場所や、よく使う銀行から順に聞いていくとスムーズです。

2. 早い段階から「遺言書」を作る

認知症が進むと、遺言が作れなくなる
親が認知症になると相続で一番困るのが、遺言書が作れなくなること です。
遺言は「本人の判断能力」が必要で、軽い認知症でも専門家が慎重に判断します。
症状が進むと、遺言そのものが無効になる可能性が高くなります。
遺言がないと、相続人同士で話し合う“遺産分割”が必要になります。
兄弟が複数いる場合、話し合いが難航することは珍しくありません。
とくに不動産が1つだけの場合、誰が住むか・売るか・分けるかで揉めます。
遺言は、親が元気なうちに作るほど、家族の負担が減ります。
内容はシンプルでも構いません。
「自宅を長男へ」「預金は子どもたちで等分」など、方向性が決まるだけで十分です。
公的に預けられる「遺言書保管制度」
字が書ける状態であれば、手書きの遺言を法務局で預かってもらえる制度があります。
改ざんの心配がなく、家族が遺言を見つけられないというリスクもありません。
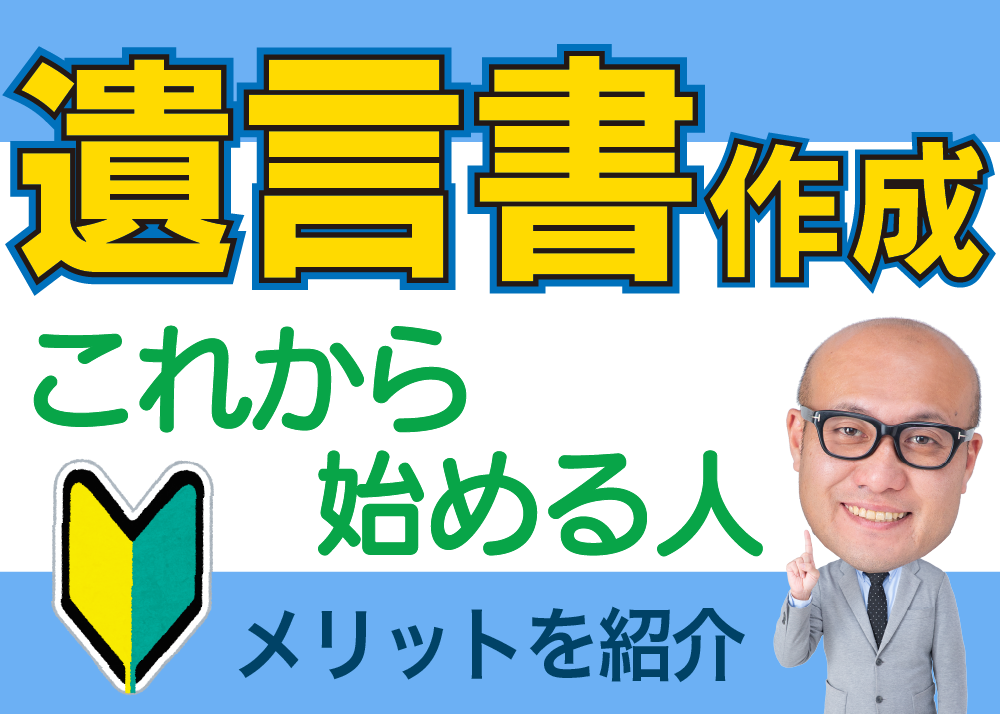

3. 判断能力の低下に備えて「任意後見契約」を結ぶ
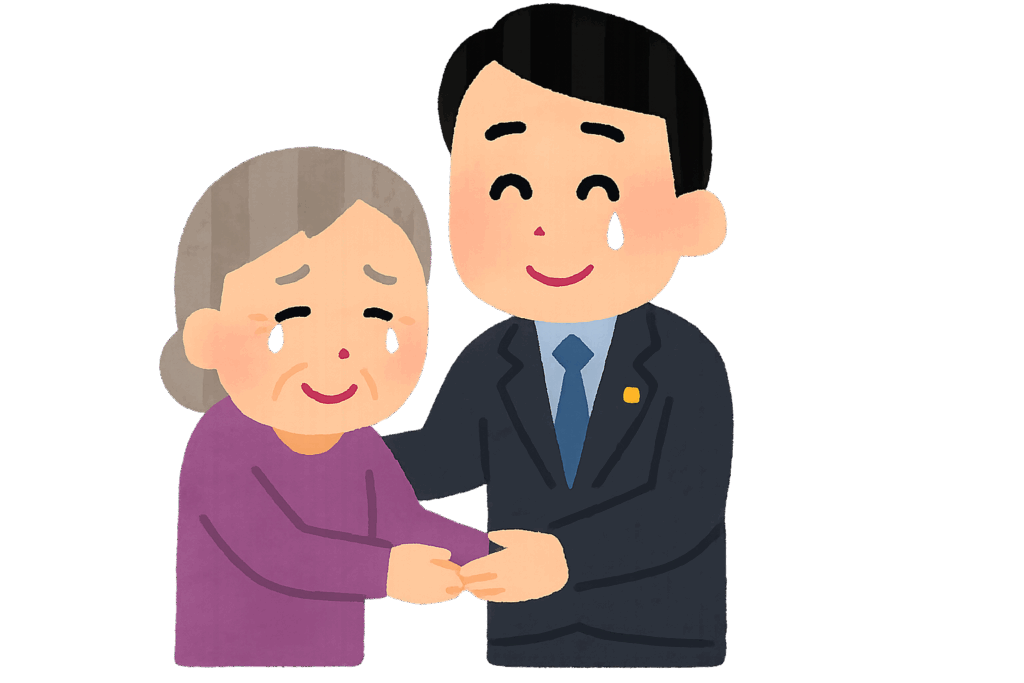
重くなった後見制度(成年後見)を避けるための“早期対策”
親の判断能力が落ちると、相続だけでなく、
・預金の引き出し
・不動産の売却
・施設への入所契約
など、日常生活の多くが“本人ではできない状態”になります。
このとき、家族が代わりに手続きをするには、公的な制度である 成年後見 を利用するしかなくなります。
しかし成年後見は、
・裁判所が後見人を選ぶ(家族が選べないことが多い)
・収支報告を毎年提出
・不動産売却などの度に裁判所の許可が必要
と、手続きが非常に重くなります。
こうした負担を避けるために、判断能力がまだあるうちに「任意後見契約」を結ぶ方法があります。
これは“親が自分で後見人を選ぶ”契約です。
判断能力が落ち始めたときに発動し、生活や財産管理を家族や専門家がスムーズに支えられます。
任意後見のメリット
・選びたい相手を自分で選べる
・将来の不安を軽減できる
・急な入院や施設入所の時にスムーズ
・相続手続き全体が止まらない
認知症と相続のトラブルを最小限にする“事前の保険”のような役割があります。
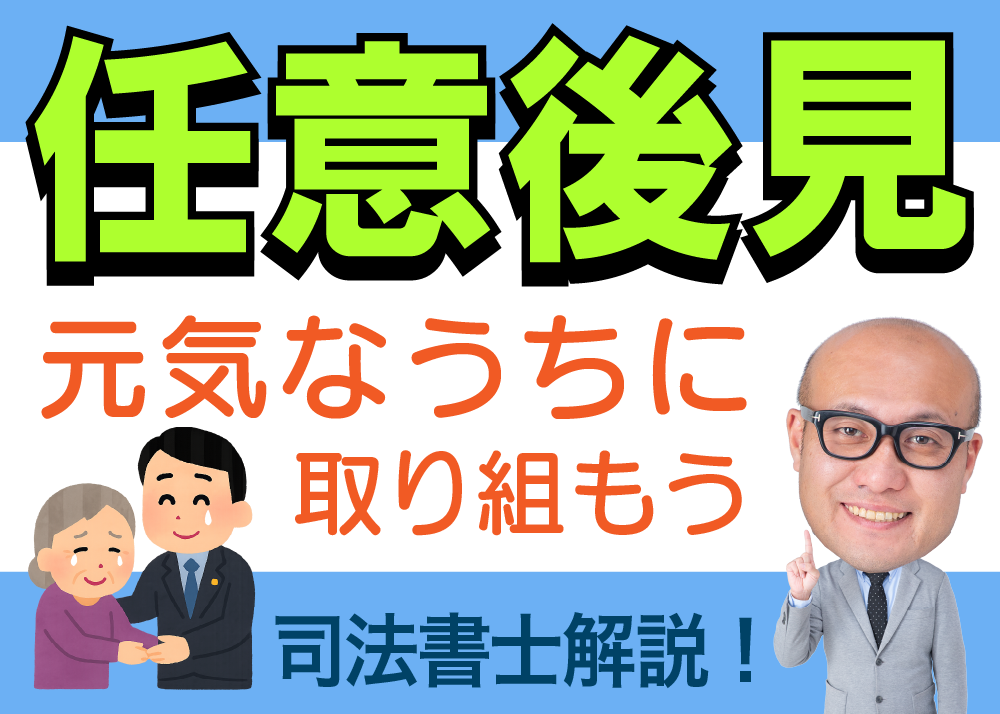
4. 実家の不動産をどう扱うか、家族で方向性を決めておく

認知症になると売却も名義変更もできなくなる
親が認知症になると、自宅や土地に関する手続きが大きく制限されます。
売却・名義変更・賃貸契約など、重要な判断ができないと、どれも手続きが進まなくなります。
不動産は相続でもっとも揉めやすい財産です。
複数の相続人の意見が分かれやすく、「誰が住むのか」「売るのか」「維持費は誰が払うのか」などで対立が起こります。
認知症をきっかけに家の管理が止まると、
・固定資産税の負担
・空き家化による劣化
・草木の管理
・近隣トラブル
といった問題も出てきます。
だからこそ、軽度の段階から「実家をどうするか」を家族で話しておくことが大切です。
住み続けるのか、売るのか、誰が管理するのか。
親の希望を聞きながら、方向性だけでも決めておくと、認知症が進んでからの混乱を避けられます。
売却を選ぶ場合
判断能力があるうちに売却するなら、
・必要書類
・相続関係者
・建物の状態
などを早めに確認しておくと、手続きが滞りません。

5. 介護・医療・相続の連携を「早めに」整える
認知症になると家族だけでは全部を把握できない
認知症が進むと、家族が“情報のハブ”になります。
病院、介護施設、自治体、社会福祉、金融機関、相続の専門家。
一つの家族だけで全体を把握していくのは限界があります。
親の状態が落ち着いている段階で、
・かかりつけ医
・ケアマネジャー
・地域包括支援センター
と連携を作っておくと、必要な介護サービスが早く受けられます。
その上で、将来の相続に関係しそうな情報も整理しやすくなります。
医療と介護の情報が整理されると、
・財産管理の負担
・施設入所時の契約
・費用の見通し
など、相続の準備にも直結します。
相続=亡くなる時の問題 ではありません。
認知症が進むと“生きている間”の財産管理ができなくなり、そのまま相続トラブルへつながっていきます。
家族が早い段階から連携をつくっておくことで、介護と相続の双方がスムーズに進みます。
まとめ
親が認知症になると相続で困る大きな原因は、「本人の意思確認ができない状態」になることです。
預金、不動産、契約…あらゆる場面で手続きが進まなくなり、家族の負担が一気に増えます。
今日からできる対策として、
- 財産の全体像を把握する
- 遺言書を早めに作る
- 任意後見契約で判断能力低下に備える
- 実家の方向性を話し合う
- 医療・介護と相続の連携を早めにつくる
この5つを押さえておくと、認知症と相続の両方で起こりやすいトラブルを大きく減らせます。
あなたの家族にとって、今日が一番動きやすい日です。
“まだ大丈夫”と思える今のうちに、少しずつ準備しておくことが、後の安心につながります。
がもう相続相談センターのサポート
がもう相続相談センターでは、
認知症によって相続手続きが止まってしまう前の早期対策から、
判断能力が低下した後の手続きサポートまで、
一連の流れをワンストップでご相談いただけます。
- 財産状況の整理サポート(預金・不動産・保険など)
- 遺言書作成サポート
- 任意後見契約・生前対策の相談支援
- 不動産の名義・売却に関する手続きサポート
- 医療・介護と相続が絡むケースへの総合的な案内
ご相談は何度でも無料です。
相続の不安を感じたときに、まず相談できる場所としてご利用ください。

弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。
ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

