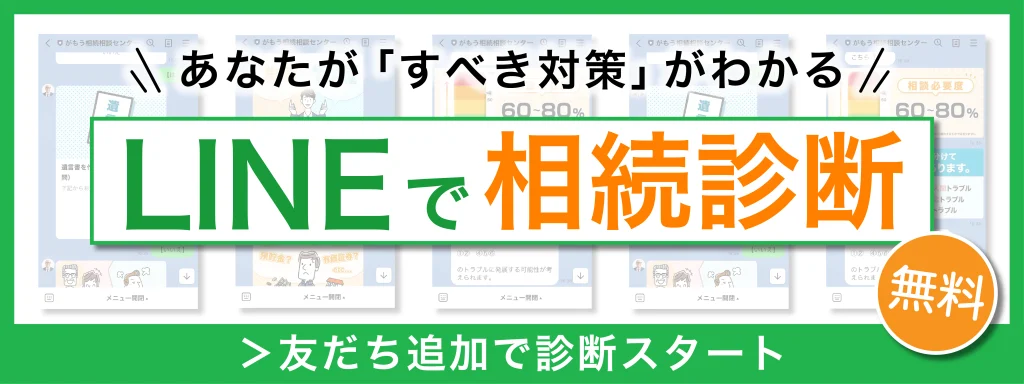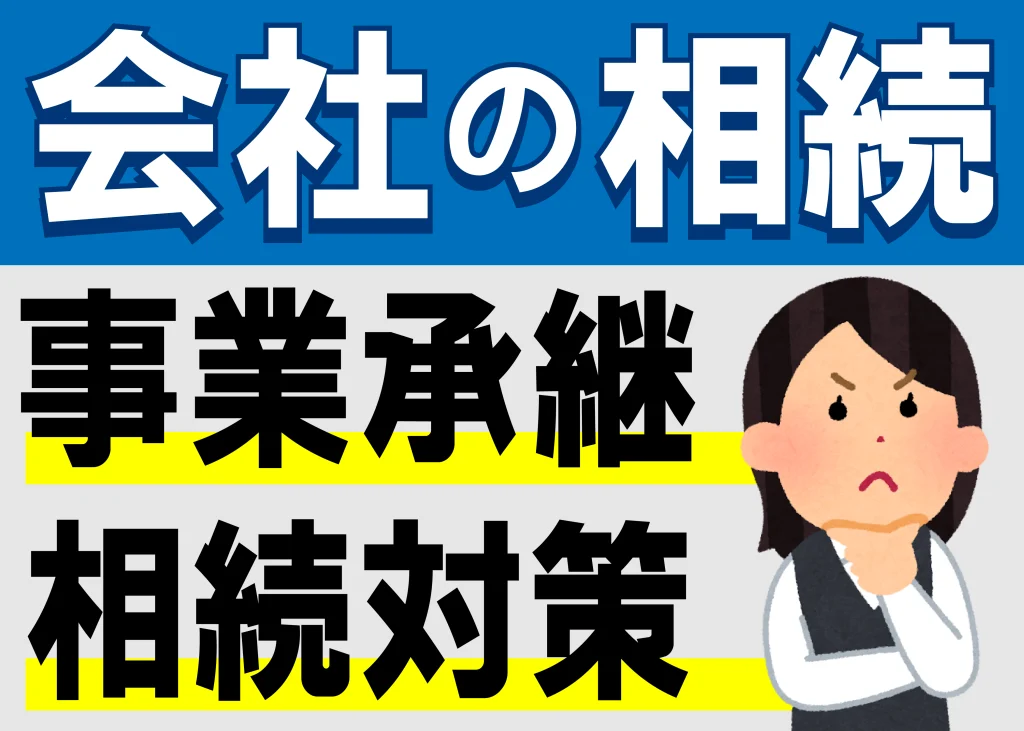
「うちの会社、将来どうしたらいいだろう…」
中小企業の経営者の多くが抱える悩み。それが、事業承継と相続の問題です。
後継者が決まらない、財産の分け方が難しい、家族に迷惑をかけたくない――。
実は、事業承継と相続は“似て非なる問題”。
それぞれに別の視点からの準備が必要です。
この記事では、
「事業承継の課題と対策」
「相続の課題と解決策」
この2点をわかりやすく整理します。
事業承継と相続は別物です

「社長が亡くなったら、会社は相続されるんでしょ?」
よくある誤解ですが、事業承継と相続はまったく別の制度です。
| 内容 | 目的 | 対象 |
| 事業承継 | 会社の経営を誰に引き継ぐか | 社長の地位・経営権など |
| 相続 | 財産をどう分けるか | 預貯金・不動産・株式など |
つまり、
会社を引き継ぐ相手(後継者)と、財産をもらう相手(相続人)は一致しないこともあるため、
両方を別々に考えることが必要になります。
中小企業の「事業承継」でよくある課題

以下のような悩みが中小企業の経営者からよく寄せられます:
- 👤「後を継いでくれる人がいない」
- 👤「子どもに継ぐ気がなく、第三者承継も考えている」
- 👤「後継者は決まってるけど、周囲とのバランスが気になる」
- 👤「会社の株は自分が持ってるけど、現場は別の人が仕切っている」
こうした悩みの裏には…
- 経営権の移譲タイミングの難しさ
- 会社の資産(株式・設備)の移転手続きの煩雑さ
- 後継者育成のための時間不足
といった、感情・法務・実務の三重苦が潜んでいます。
事業承継のために必要な対策とは?
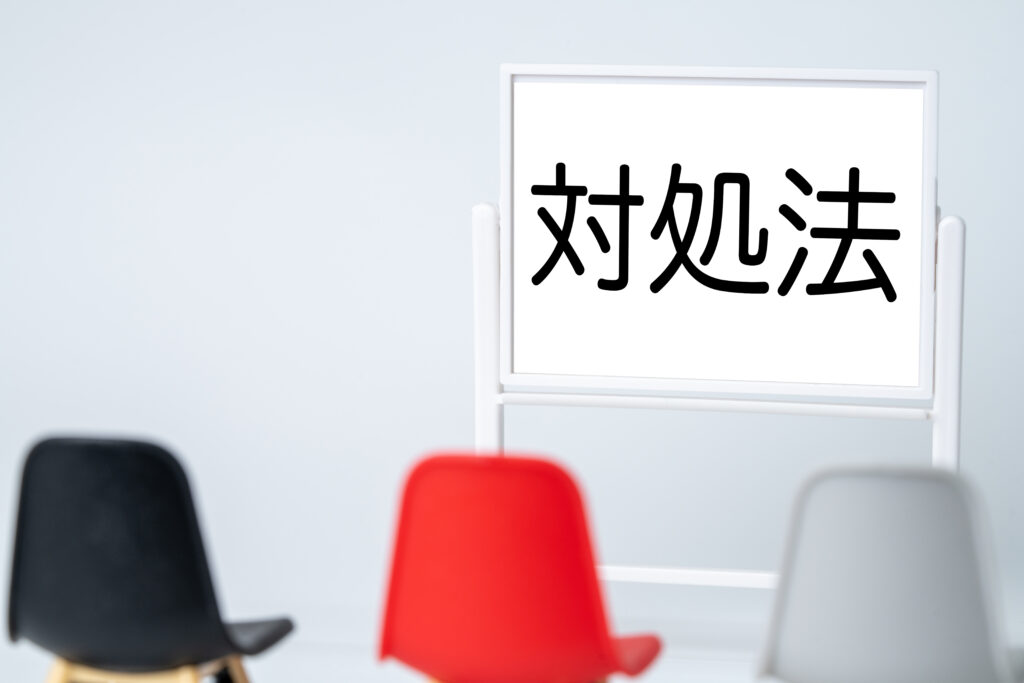
事業承継の成功には、次のようなステップが重要です。
✅ 1. 後継者の明確化
まずは、誰が会社を引き継ぐのかを明確にします。
子ども・親族・従業員・M&A(第三者)など、承継先のパターンを比較検討することが重要です。
✅ 2. 自社株の承継準備
中小企業では、社長が自社株の大半を保有していることが多く、自社株の相続=会社の支配権の行方に直結します。
後継者に集中的に株を移す方法(贈与・譲渡)を検討しないと、経営が分散・混乱する恐れがあります。
✅ 3. 関係者への共有
親族や従業員にも早い段階で方向性を伝えることで、トラブルを予防できます。
「いつ」「だれに」「どのように」バトンを渡すかを言語化し、計画に落とし込むことが成功のカギです。
相続で起こる課題とは?

事業承継とは別に、経営者の死後には相続の問題が待っています。
❌ 相続人が複数いて遺産分割でもめる
→ 会社の株や設備が分けにくく、経営に支障が出る
❌ 会社の株を平等に分けてしまい、後継者が経営しづらくなる
→ 意思決定に時間がかかり、経営の機動力が失われる
❌ 相続税が重くのしかかる
→ 自社株の評価が高くなると、納税資金に苦しむことに
事業と財産の線引きができていないことで、相続争いがそのまま会社崩壊につながるリスクもあるのです。
相続に向けた具体的な解決策

相続の課題には、次のような対策が有効です。
✅ 遺言書の作成
後継者に自社株を集中させたい場合、遺言書で明記することで、他の相続人との揉め事を回避できます。
遺言書の詳細はコチラ!
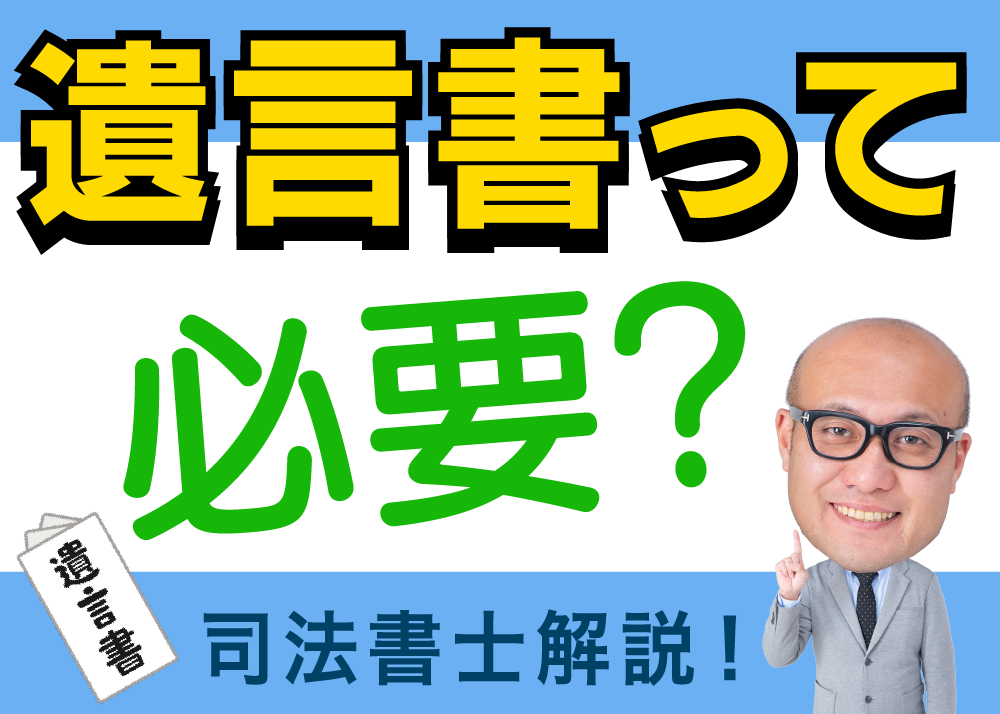
✅ 生命保険の活用
相続税の納税資金として、生命保険を活用する方法も有効です。相続人に現金を残せば、納税トラブルを防げます。
✅ 株価評価の見直し
事前に**株価の引き下げ策(退職金・役員報酬・持株会社設立)**を講じておけば、相続税対策にもなります。
まとめ:会社を守るには「二重の対策」が必要
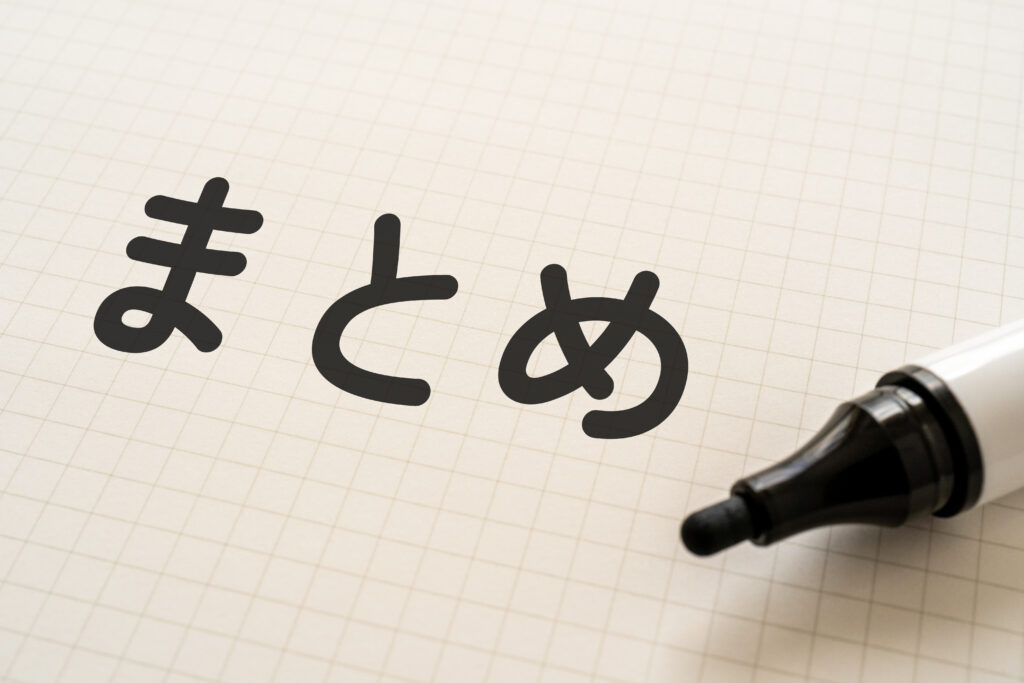
中小企業の経営者にとって、
「事業承継」と「相続」は別の課題でありながら、どちらも準備が欠かせません。
- 経営を誰に託すのか → 事業承継の視点
- 財産をどう分けるか → 相続の視点
この2つを混同せず、それぞれに合った対策を進めることで、
家族も会社も守ることができます。
「うちはまだ早いかな…」と思ったその時が、一番の始めどきです。
信頼できる専門家と一緒に、早めの準備を始めていきましょう。
弊社では何回でも何時間でも無料でご相談いただけます。
また、認知症対策以外の相続まで幅広くカバーしております。
「何から手をつけたらいいのか…」とお考えの方に弊社の無料相談はピッタリです!
あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。
\ この機会に是非ご登録ください! /