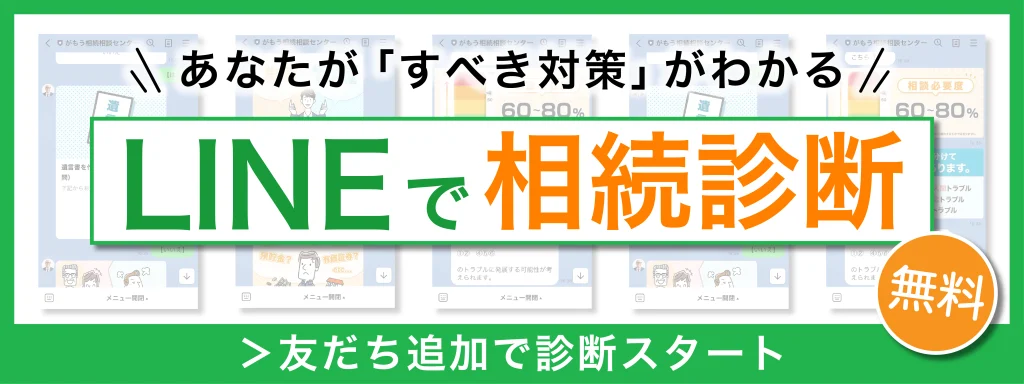「相続人の一人と連絡が取れないんです…」
遺産分割のご相談で、こうした声をいただくことがあります。
相続では、たった一人でも所在不明の相続人がいると、遺産分割協議が進まず、預金の解約も不動産の名義変更もできない——そんな事態に陥ってしまうことがあります。
とくに兄弟姉妹が相続人となるケースでは、「何十年も音信不通」「どこに住んでいるか分からない」といった状況も少なくありません。
この記事では、相続人の住所が分からないと起きる具体的なリスクや、解決のためにとれる法的手段について分かりやすく解説します。
執筆者:司法書士 ほんじょう たかし
若干18歳で単身ブラジルにサッカー留学に行き、帰国後、吉本NSCへ入学。お笑いの道では花咲かず、親戚の葬儀屋で働く中で司法書士と出会い、相続の仕事を志す。
司法書士の資格を取得し、経験を積んだのち「がもう相続相談センター」をオープン。現在では2000名以上のご相談を受け、城東区を中心に多くの相続問題を解決に導く。
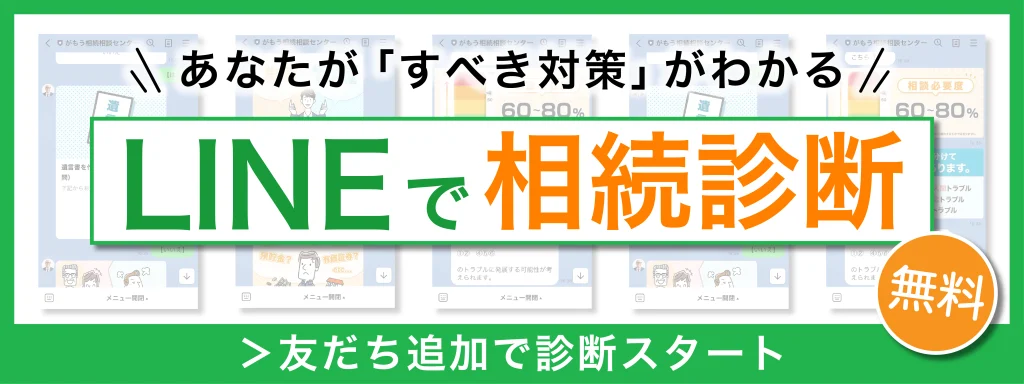
1.相続人の“所在不明”は意外と多い
相続手続きを進めるうえで、思わぬ壁となるのが「相続人の所在が分からない」という事態です。
とくに兄弟姉妹やその子どもが相続人になるケースでは、「何年も連絡を取っていない」「住所が古くて届かない」ということが実際に起こります。
相続は“相続人全員の同意”が必要な手続きが多いため、たった一人所在が不明なだけで、すべての手続きがストップする可能性があります。

2.なぜ「住所不明」だと手続きができないのか?
相続登記・預貯金の解約・遺産分割協議など、基本的に相続人全員の署名や実印、印鑑証明書が必要です。
住所が分からなければ、書類を送ることも本人確認をとることもできません。
これは法律的に“欠けた状態”とみなされるため、以下のような影響が出ます:
- 不動産の相続登記ができない
- 銀行から相続人全員分の同意書が要求される
- 売却や賃貸に進めず、財産が「凍結状態」になる
3.所在不明の相続人に対する法的手段とは?
どうしても連絡が取れない場合には、次のような手段が取られます。
(1)不在者財産管理人の選任申立て
家庭裁判所に申し立てることで、行方不明の相続人の代わりに手続きを進められる“代理人”を選任できます。ただし、時間と費用がかかります(数ヶ月~半年/報酬の支払いもあり)。
(2)失踪宣告(長期不在の場合)
7年以上生死不明の場合、法律上「死亡」とみなす制度もありますが、これは極端なケースです。
4.「分かっていれば避けられた」ケースも多い
下記の準備があれば、「所在不明の人がいて何もできない」という事態はある程度避けられます。
- 戸籍や住民票で追えるうちに連絡をとっておく
- 親の生前に、誰が相続人になるか洗い出しておく
- 遺言書を作成し、財産の行き先を指定しておく
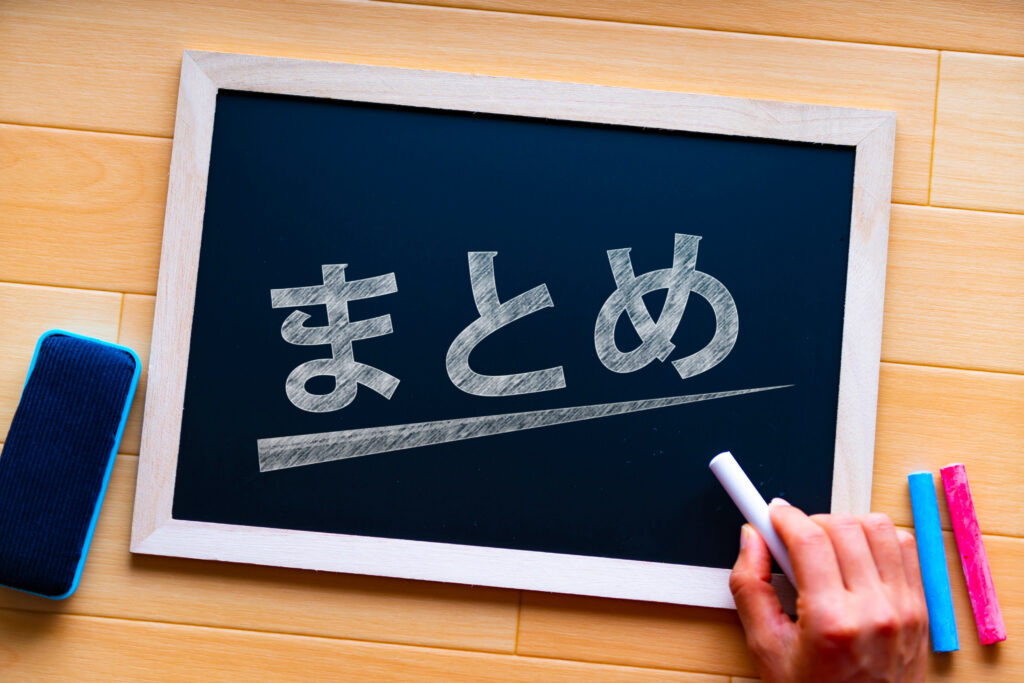
5.最後に。相続人の所在確認は“最初にすべきこと”
相続手続きは「誰が相続人か」「その人と連絡が取れるか」からすべてが始まります。
住所が不明な人がいると、手続きが止まってしまう――これは制度上避けられない現実です。
「面倒だから後回し」で済ませず、できるだけ早く、相続人の所在確認をしておくことが、スムーズな相続への第一歩となります。
お悩みの方は、ぜひ弊社の無料相談にお申し込みください!あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。
また、弊社のLINE公式アカウントでは、あなたに必要な相続対策がわかる診断や、あなたの相続のキケン度がわかる診断をご用意しています!お気軽にご相談もいただけます
\ この機会に是非ご登録ください! /