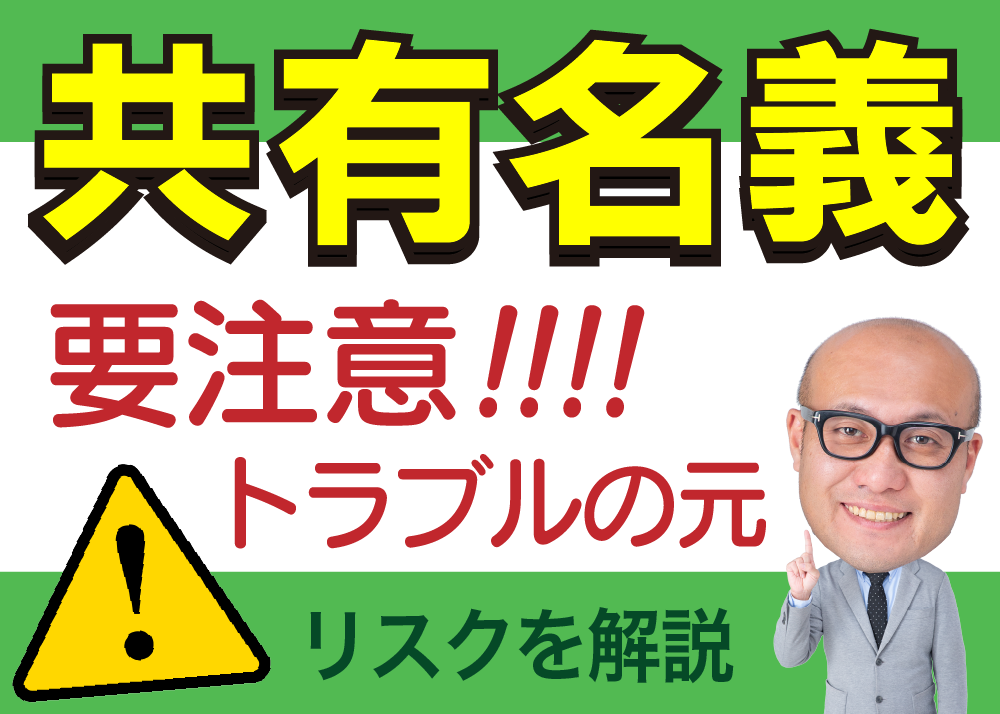
共有名義は一見平等に見えますが、
トラブルの元になることも少なくありません。
実際に、売却や管理で意見が合わず家族関係が悪化するケースも…。
この記事では、共有名義のリスクと解決策をわかりやすく解説します。
後悔しないために、今すぐチェックしましょう!
共有名義とは?相続で発生するリスクの基本知識
共有名義とは?仕組みと基本ルール
共有名義とは、1つの財産を複数の人が共同で所有する権利を持つ状態を指します。
相続においては、特に不動産の相続でよく見られる形態です。
例えば、親が亡くなった後、兄弟3人で実家の不動産を相続する場合、それぞれが持ち分を持つ形になります。これは「法定相続分」に基づいて分配され、兄弟が3人なら各自が1/3の所有権を持つことになります。
- 権利は平等に分配されるが、使用や処分には全員の同意が必要
- 単独での売却や改修はできない(全員の同意が必要)
- 持ち分は他の共有者の同意がなくても譲渡可能だが、他の共有者の利益に影響を及ぼす場合もある
このようなルールにより、共有名義は公平に見える一方で、管理や処分が難航しやすい特徴があります。
なぜ共有名義は相続トラブルの火種になりやすいのか?

共有名義は見た目の公平性が保たれる一方で、将来的なリスクを多くはらんでいます。
その理由として、以下の3つが挙げられます。
売却や大規模な修繕といった大きな決断を下すには、共有者全員の同意が必要です。
1人でも反対する相続人がいる場合、決定が先送りされ、管理コストや不動産価値の低下につながる可能性があります。
固定資産税や修繕費などの維持費用は、持ち分に応じて負担するのが原則です。
しかし、支払いに応じない共有者がいた場合、一部の共有者に負担が集中し、トラブルの元になります。
共有名義のまま次世代に引き継がれると、共有者の数が増加していきます。
例えば、兄弟3人の共有名義が次世代に引き継がれると、9人以上の共有者が発生するケースも。この増加により、意思決定がさらに難しくなり、相続人同士の意見の食い違いも生じやすくなります。
共有名義の不動産を売却する場合、全員の合意が必要です。
特に、相続人の関係が悪化している場合や、所在が不明な相続人がいる場合は、売却そのものが不可能になることも少なくありません。
放置すると危険!共有名義による相続トラブルの実例

意思決定の難しさが生む対立
共有名義の最大のリスクは、全員の同意が必要になることです。
不動産の売却、修繕、賃貸など、重要な決定を行うためにはすべての共有者の合意が不可欠です。しかし、相続人それぞれの経済状況やライフスタイル、価値観が異なるため、合意に至るのは簡単ではありません。
実例
3人兄弟で共有している実家のリフォームについて、1人が「必要ない」と反対したことで議論が紛糾。結局、決定が先送りされ、家の老朽化が進んでしまう結果に。このように、意思決定の停滞が資産価値の低下を招くリスクもあります。
維持費用や修繕費の分担で起こる問題
共有名義の不動産は、固定資産税や修繕費、維持費用がかかります。
持ち分に応じて費用を分担するのが原則ですが、全員が納得するわけではありません。
一部の共有者が支払いを拒否する場合、他の共有者の負担が増えることになります。
実例
兄弟3人で共有しているマンションの修繕積立金を巡り、1人が「使用していないから支払う義務はない」と主張。結果として、他の共有者が全額を肩代わりし、家族間の関係が悪化。最終的に裁判沙汰にまで発展するケースも存在します。
全員合意が必要な売却でのトラブル事例
共有名義の不動産を売却するには全員の同意が必要です。
しかし、共有者のうち1人でも売却に反対すると、手続きを進めることができません。
さらに、共有者が連絡を取れなくなるケースもあり、売却が事実上不可能になることもあります。
実例
実家を売却する話が持ち上がったものの、1人の兄弟が所在不明で連絡が取れなくなり、売却が完全にストップ。最終的に裁判所へ不在者財産管理人の申し立てを行う必要があり、解決までに数年以上の時間と費用がかかる事態に。
共有名義の対策とは?
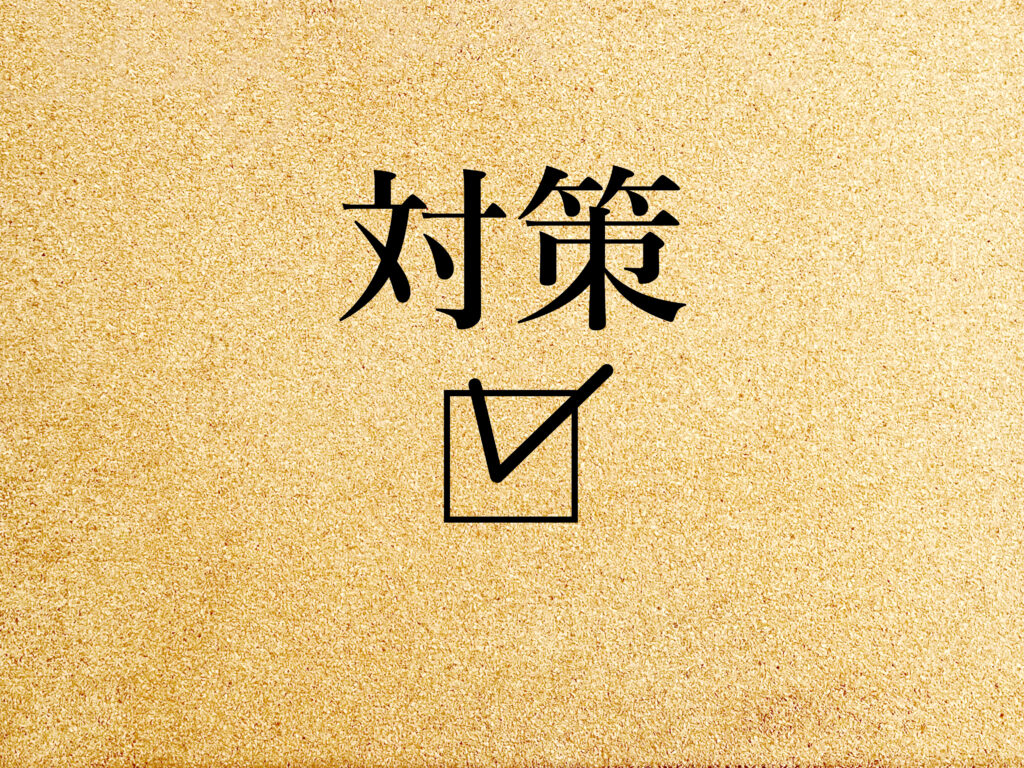
遺言書などで未然に防ぐ方法
相続トラブルを未然に防ぐ最も効果的な方法は、遺言書を作成することです。
遺言書には、遺産の分割方法や単独名義にする意向を明確に記載できます。これにより、相続人が共有名義になってしまうリスクを事前に回避することが可能です。
- 不動産の単独相続を明示することで、共有名義を回避
- 家族全員が納得できるよう、専門家と相談しながら内容を調整する
- 公正証書遺言として作成すると、法的効力が高まり、無効になるリスクを減らせる
共有名義を解消する方法
共有名義のまま放置するとトラブルが起こりやすくなります。
問題を未然に防ぐための解消方法には、以下のようなものがあります。
- 持ち分の買取
他の共有者から持ち分を買い取ることで、単独名義に変更できます。金銭的な負担は大きいものの、自由に意思決定ができるようになります。 - 分割協議
相続人全員が話し合い、不動産を物理的に分割したり、金銭的補償を行うことで共有状態を解消します。全員の合意が必要ですが、円満解決を目指す場合に有効です。 - 裁判所の調停・審判
共有者同士の合意が得られない場合、家庭裁判所に分割請求を申し立てることができます。時間と費用はかかりますが、法的に強制的に解消できます。
共有名義から抜ける方法
共有名義から抜ける方法として最もシンプルなのが、持ち分の売却です。
以下の2つのケースが一般的です。
- 共有者に売却
他の共有者が持ち分を購入することで、トラブルを避けやすく、円満に解決できるケースが多いです。 - 第三者への売却
共有者が同意しない場合でも、自分の持ち分を第三者に売却することが可能です。ただし、共有者に優先的購入権があるため、売却前に共有者へ通知しておかなければ法的な紛争が生じる可能性があります
- 持ち分のみの売却は、買い手がつきにくい場合がある
- 共有者同士の関係悪化を防ぐため、専門家のアドバイスを受けることが重要
要注意!相続登記で安易に共有名義にしてはいけない!
相続登記をする際、安易に共有名義にすることは避けるべきです。
一見平等に見える共有名義ですが、長期的に見ると以下のようなリスクがあります。
- 意思決定が難航:売却や修繕に全員の合意が必要
- 維持費用の不公平な負担:支払い義務が曖昧になりやすい
- 管理責任が分散:誰が何をするかが不明確になりやすい
相続登記の際は、可能な限り単独名義にすることが理想的です。
すでに共有名義になってしまっている場合は、早期に専門家に相談し、共有解消の方法を検討しましょう。
相続登記に関する詳しい解説は、下記からご覧いただけます
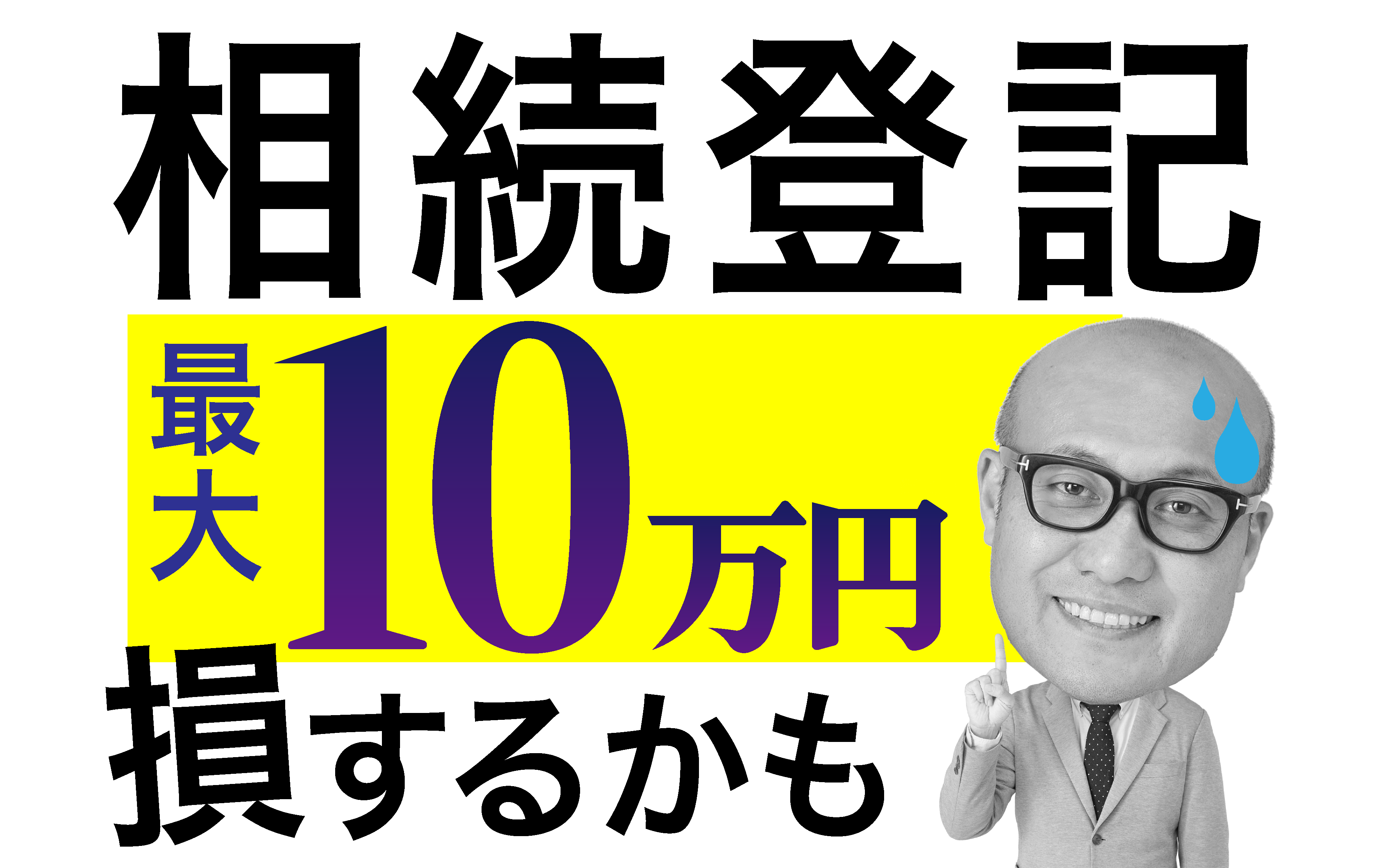
まとめ|共有名義は早めの対策がカギ!
共有名義を放置することは、将来的なトラブルの温床となります。
共有名義の問題は法的・感情的な要素が絡むため、専門家のアドバイスを受けることが最善策です。
まずは無料相談から始めることをおすすめします。
弊社では、無料相談を実施しており、現状の課題を明確にする良い機会になります。
お気軽にLINEや電話でお問い合わせください
相続に関するご不安や疑問点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門家チームと連携しながら、最適な方法をご提案させていただきます。
 司法書士:本上
司法書士:本上お気軽にご相談ください!
自己紹介:本上崇(ほんじょう たかし)
皆様、はじめまして!
がもう相続相談センター代表の本上崇 ( ほんじょう たかし ) と申します。
簡単に自己紹介させていただきますと、 実は私、司法書士になる前は、プロサッカー選手を目指してブラジルに留学したり、お笑い芸人をしていたりと、少し変わった経歴の持ち主なんです。
「え、司法書士なのに?!」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。
でも、 これまでの経験を通して、どんな人とも “楽しく、わかりやすく” コミュニケーションをとることの大切さを学びました。
そして、その経験は、相続問題という複雑で、時にデリケートな問題を抱えたお客様と向き合う上で、大きな強みになっていると自負しています。
相続問題は、誰にとっても 不安や悩み がつきものです。「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが複雑そうで面倒だ」「費用がいくらかかるのか不安だ」…
そんな悩みを抱えたまま、一人で抱え込んでいませんか?
がもう相続相談センターは、「お客様に寄り添い、不安を解消し、笑顔になっていただく」ことを理念としています。
相続の専門家である司法書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて、わかりやすく丁寧 にご説明いたします。
- ・ご相談は何度でも無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- ・専門スタッフが親身になって対応いたしますのでご安心ください。
- ・「もっと早く相談すればよかった…」そう思っていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
がもう相続相談センターは、皆様の相続を、生涯にわたってサポートいたします。
まずはお気軽にご連絡ください!
代表司法書士 本上崇

