
窓口1つで、相続問題・生前対策をまるっと解決します!

代表 ほんじょう たかし
自称世界一おもろい司法書士




相続問題ならお任せください。
不動産名義変更・遺言書・相続税対策・生前贈与・後見制度・不動産売却まで窓口ひとつで解決します。元芸人の経歴を持つ、私ほんじょうが、芸人時代に培ったコミュニケーション能力で皆様のお悩みを解決します。

電話、メール、LINE にてお問い合わせください。

都合のいい日時にご予約いただき、ご来店・ご訪問・オンライン相談を、ご選択していただけます。

お客様に合った最善の策をお伝えさせていただきます。
今後の流れやスケジュール感、手続き費用を、詳しくご説明させていただきます。

各専門家がお手続きを開始いたします。
進捗状況についてその都度ご報告申しあげます。
着手金として報酬の20%をお支払いいただきます。

すべての手続きが完了しましたら、完了報告と書類一式をお渡しさせていただきます。
費用については、残りの金額をお支払いいただきます。

お客様の相続でのお悩みを、「生涯」窓口1つでサポートさせていただきます。
弊社では、この度のご縁は一生涯と考えております。
また何か新しい問題や不安がありましたら、お気軽にご相談ください。
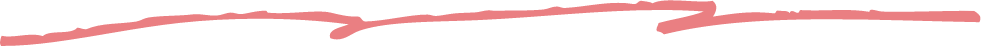
相続対策を何もしていない、又は何をしていいかもわからない
相続税がかかるかどうかもわからない、又は相続税対策できていない
などなど
遺産分割の方法が分からない、又は遺産分割で困っている
相続でトラブルになりそう、またはトラブルになっている
などなど
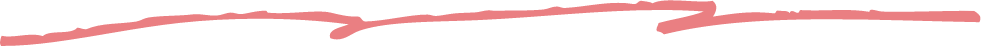


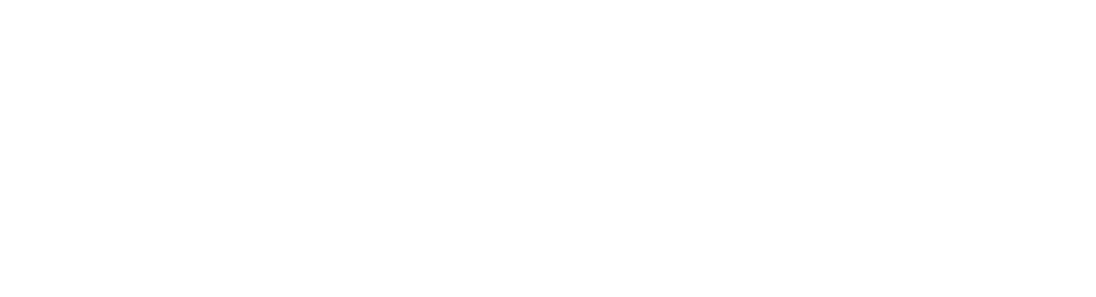








| サイト名 | がもう相続相談センター | 運営 会社名 |
株式会社 YAKUNITATSU (フリガナ ヤクニタツ) |
|---|---|---|---|
| 運営元 | 本上崇司法書士法人 | 所在地 | 〒536-0004 大阪市城東区今福西3丁目2番2号 プレジデント城東105号 |
| 電話番号 | 0120-892-102 | FAX番号 | 06-7507-2679 |
| 代表者 | 代表取締役 本上 崇 (フリガナ ホンジョウ タカシ) |
代表経歴 | ブラジル留学(約3年。ブラジル サンパウロ州2部のサッカーチームのユース所属) NSC(吉本総合芸能学院)24期生 例 エハラマサヒロ同期 |
| 企業理念 |
株式会社YAKUNITATSUは「人の役にたつ」という理念からの由来です。 人は誰かの役にたち、その方の笑顔を見て、自分も幸せになれると思っているからです。 弊社の誰もが、人の役にたち、お客様も自分達も幸せが溢れる企業へ成長していく所存です。 |
所属団体 | 大阪司法書士会 東支部(会員番号 大阪 4964号) 大阪府知事(1)第62654号 |
| 営業時間 |
平日 9:00~19:00 土日 9:00~19:00 定休日 水曜日 |
業務内容 |
不動産登記・遺産相続登記(相続・贈与) 相続税の申告・その他資産関連業務(資産シュミレーション) 遺言書作成業務(自筆証書・公正証書) 後見人選任業務(任意・成年) 裁判所関連業務(相続放棄・交渉手続・裁判業務) |
がもう本店
がもう相続相談センターは地下鉄/蒲生四丁目駅から徒歩1分の場所に位置しております。城東・鶴見近辺にお住まいの皆様はもちろんのこと、遠方の方でもアクセスしていただきやすい立地となっております。代表本上がお伺いすることも可能ですし、ご来社いただくことも可能です。お気軽にご相談ください。
〒536-0004
大阪市城東区今福西3丁目2番2号 プレジデント城東105号
地下鉄/長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅【6番出口 徒歩1分】
蒲生四丁目駅からの詳しい道順は下記をご確認ください。
川西支店
兵庫県川西市近辺にお住まいの皆様はもちろんのこと、遠方の方でもアクセスしていただきやすい立地となっております。
代表本上がお伺いすることも可能ですし、ご来社いただくことも可能です。
お気軽にご相談ください。
〒666-0012
兵庫県川西市絹延町1番5号
能勢電鉄妙見線 絹延端 徒歩5分
阪急電鉄・能勢電鉄 川西能勢口 徒歩15分